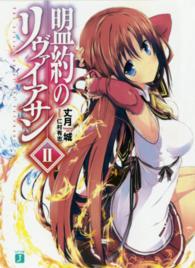出版社内容情報
自社製品の安全性を自主的に確認し、消費者に正しく伝えるうえで必要な最新の科学的知見と規格基準、その根拠を示した必携の実務書!
■ 主要構成
第1章 食品の安全性確認の新しい視点
第1節 食生活の変化とリスク
第2節 食品の安全性をめぐる国際議論の潮流
第3節 消費者の期待する食品
第2章 食品添加物の安全確認の実用的評価法
第3章 動物用医薬品の安全確認の実用的評価法
第4章 残留農薬の安全確認の実用的評価法
第5章 汚染化学物質の安全確認の実用的評価法
第1節 カビ毒
第2節 ダイオキシン
第3節 PCB
第4節 環境ホルモン
第5節 重金属
第6章 微生物学的リスクアセスメント
第1節 微生物学リスクアセスメントの考え方
第2節 FAO/WHOによる微生物学的リスクアセスメント
第3節 微生物学的リスクアセスメントの実際
第7章 食の安全管理システム
第1節 行政からみた食の安全管理の課題
第2節 消費者サイドからみた食品の安全管理の現状と期待
第3節 HACCPシステムをめぐる動き
第4節 トレーサビリティの現状と動向
第5節 トレース技術の実際
第8章 消費者にいかに正確に安全情報を伝えるか
第1節 消費者が求める食品の安全情報とは
第2節 食品産業の対応策
第3節 リスクコミュニケーションの考え方
--------------------------------------------------------------------------------
【発刊にあたって】
社会的な重要課題となっている「食の安全・安心問題」に真摯に取り組み、消費者の信頼に応えようとする農業関係者や食品産業従事者の存在は、国民全員の願いである。食品の安全・安心の考え方は決して画一的なものではなく、各国・各地域の歴史、風土、文化に深く関わる多様性を含んでいる。 FAOとWHOが合同で設立したコーデックス国際食品規格委員会における討議内容を尊重し、さらに日本の食文化の伝統を生かし育てることを願って、食品衛生に関する世界の流れと安全や安心確認の趨勢の紹介を本書では試みた。
本書はコーデックスの合意事項や考え方、あるいは検討状況をベースに、食品の安全性確認のための評価法の解説を行った。食料の一次生産、流通、加工等に携わる方々、特に最終食品製造加工者としての責任を問われる食品産業の読者が本書により自社製品の安全性を自主的に確認する際の参考となるよう執筆、編集を行った。また、食品の供給あるいは流通に携わる方々が、自社製品の安全性に関する情報を購入者や消費者に正しく伝え、納得を得るうえで必要な科学的知見とその根拠を出来る限り平易に示すよう心がけた。
1995年のWTO発足により、コーデックス規格が食品貿易時の判断基準であることが明らかになり、またコーデックス加盟国であるわが国は、国内基準もコーデックス規格と整合性をもたせることが必要になっている。 歴史的な経緯もあり、各国間で異なる食品添加物や残留農薬等の考え方やそれらの規格基準設定について、コーデックスおよびわが国の現状の解説を試みた。必要に応じて諸外国の事例や今後の展望も書き加えた。
本書は8章からなる。第1章「食品の安全性確認の新しい視点」では、食生活の変化やリスクについての考察や国際動向、消費者が求める食品についての解説を行った。第2章以降では、食品添加物、動物用医薬品、残留農薬、汚染化学物質等について最新情報を踏まえた報告を順次行った。第6章では、食中毒対策を中心に微生物学的リスクアセスメントに関する解説を行った。第7章では、食の安全管理システムを取り上げ、消費者サイドからの要望やトレーサビリティに関する情報も盛り込んだ。第8章では、消費者と安全情報についての考察を行った。
各章の執筆者は、それぞれの専門分野での実務担当者や研究者であり、長年の経験を有する方々である。それぞれの専門分野を関連付けた本書の試みが、食べ続けなければならない人間の食生活とその食糧供給の行方を照らす小さな灯火となることを願っている。
編集委員一同(本書序文より抜粋)
--------------------------------------------------------------------------------
■ 内容目次
第1章 食品の安全性確認の新しい視点
第1節 食生活の変化とリスク<一色 賢司>
従属栄養動物としての宿命
食性病害
我々の食べているもの
食生活とリスク
食品の安全性評価と確保
第2節 食品の安全性をめぐる国際議論の潮流<遠藤 芳英>
主な国際機関の活動
1.1 FAO/WHO合同食品規格委員会(コーデックス委員会)
1.1.1 概要と組織
1.1.2 コーデックス委員会の主要部会での議論の動向
1.2 FAOとWHO
1.2.1 FAO/WHO開催の食品安全に関するグローバルフォーラム
1.2.2 FAO/WHO合同専門家会合
各国の新たな取組み
2.1 欧州委員会の「食品安全に関する白書」
2.2 新しいEU食品規制と欧州食品安全機関
2.2.1 本規制による新政策
2.2.2 欧州食品安全機関
国際的な注目を集めた食品安全に関する話題
3.1 国際規格作成の困難さ - アフラトキシンの基準値
3.1.1 議論全般の経緯と最終合意
3.1.2 牛乳のM1基準値に関する議論
3.1.3 WTOでの議論
3.2 新しい危機管理の考え方 - 予防原則
3.2.1 EUの主張
3.2.2 コーデックス委員会での議論
3.2.3 米国等の反応
3.3 食品の安全性に関する国際規格と各国の企画の調和 - WTOでの紛争事例
3.3.1 経緯
3.3.2 第三条1項と3項の関係に関する上級委員の判断
3.3.3 科学的正当性の実証の困難性
3.3.4 科学的評価に関する意見の相違
3.4 トレーサビリティに関する議論
3.5 遺伝子組換え農産物の安全性審査
3.5.1 コーデックスバイオテクノロジー応用食品特別部会での議論
3.5.2 OECDでの議論
3.5.3 援助食料物資への遺伝子組換え産品の混入をめぐる事件
3.6 抗生物質の使用をめぐる問題
3.6.1 問題の概観
3.6.2 EU等先進国の国境措置規制強化
3.6.3 輸出途上国の対応
第3節 消費者の期待する食品<西島 基弘>
消費者の不安材料
食品添加物
残留農薬
遺伝子組換え食品
内分泌かく乱化学物質・アレルギー食品
リスクアナリシス
6.1 リスクアセスメント
6.2 リスクマネジメント
6.3 リスクコミュニケーション
第2章 食品の添加物の安全確認の実用的評価法 <石井 健二>
規格基準設定の考え方と方法
1.1 食品添加物の安全性評価
1.1.1 JECFA
1.1.2 日本
1.1.3 米国
1.1.4 欧州連合
1.2 成分規格
1.2.1 基本的考え方
1.2.2 日本
1.2.3 国際規格
1.3 使用基準
1.3.1 基本的考え方
1.3.2 日本
1.3.3 コーデックス
規格基準設定の実例
2.1 アセスルファムカリウム
2.2 亜硫酸塩の使用基準改正
2.3 次亜塩素酸水
検討中事項、および今後の動向
3.1 既存添加物の安全性確認と規格・基準設定
3.2 リスクアナリシス導入
3.3 国際的整合化
第3章 動物用医薬品の安全確認の実用的評価法 <三森 国敏>
規格基準設定の方法と考え方
1.1 ADIの設定
1.1.1 ADI設定のための毒性試験法
(1) 単回投与毒性試験
(2) 反復投与毒性試験
(3) 二世代生殖毒性試験
(4) 催奇形性試験
(5) 変異原性試験
(6) 発がん毒性試験
1.1.2 ADI設定のための微生物学的リスク評価法
1.1.3 ADI設定のためのアレルギー性誘発リスク評価法
1.1.4 ADIが設定できる場合
1.1.5 ADIが設定できない場合
1.2 MRLの設定
1.2.1 残留物がすべて抽出可能な場合
1.2.2 結合型残留物が多い場合
1.2.3 TMDIの算定
残留基準値設定の代表例
2.1 総残留のほとんどが抽出性残留物で、毒性学的NOELからADI設定がなされる場合
2.2 総残留のうち結合型残留物が多い場合
現在検討されている事項および今後の動向
第4章 残留農薬の安全確認の実用的評価法 <鈴木 勝士>
農薬の種類と許可システムの現状
1.1 農薬の種類
1.1.1 殺虫剤
1.1.2 殺菌剤
1.1.3 除草剤
1.1.4 殺鼠剤
1.1.5 植物成長調整剤
1.2 農薬の許可システム
1.3 登録時に求められる安全性関係のデータ
食物残留との関わり
2.1 ADI
2.2 残留基準値
国内および輸入食品の残留基準
今後の動向と課題
第5章 汚染化学物質の安全確認の実用的評価法
第1節 カビ毒<芳澤 宅實>
国際機関による安全性評価の経緯と現状
1.1 FAO/WHO/UNEP合同マイコトキシン国際会議
1.2 IPCS
1.3 JECFA
1.4 CAC:CCFAC
1.5 IARC
主要マイコトキシンの安全性評価の考え方
2.1 アフラトキシンB1(AFB1)
2.2 アフラトキシンM1(AFM1)
2.3 その他の主要マイコトキシン
世界各国の規格基準の現状
わが国の現状と今後の動向
4.1 アフラトキシン
4.2 アフラトキシンM1
4.3 デオキシニバレノール
4.4 パツリン
4.5 コウジ酸
4.6 今後の動向
第2節 ダイオキシン<広瀬 明彦>
ダイオキシン類の毒性
1.1 ヒトに対する毒性
1.2 実験動物に対する毒性
1.2.1 一般毒性
1.2.2 免疫毒性
1.2.3 生殖および発生毒性
1.2.4 発がん性
1.3 毒性発現メカニズム
1.4 ダイオキシンの体内動態
ダイオキシン類の安全性評価
2.1 TDI設定の国際的現状
2.1.1 1997年以前の評価
2.1.2 WHO-IPCS(1998年)による評価
2.1.3 わが国の評価(1999年)
2.1.4 EC食品科学会議による評価(EC-SCF)(2000~2001年)
2.1.5 JECFA(2001年)による評価
2.1.6 米国(2000年)や英国(2001年)での評価
2.2 曝露評価
2.2.1 TEFとTEQ
2.2.2 わが国における曝露評価
2.2.3 わが国と諸外国における曝露状況の比較
2.2.4 CACの状況
今後の課題
第3節 PCB<友国 勝麿>
PCB汚染とヒトへの負荷量
PCBの代謝と毒性
2.1 代謝
2.2 毒性
安全確認とリスク評価
第4節 環境ホルモン<菅野 純>
内分泌かく乱化学物質問題
1.1 受容体原性毒性としての内分泌かく乱作用
1.2 内分泌かく乱化学物質のスクリーニング・テスティング
食の安全という立場から
2.1 食品に含まれる成分
2.2 経口摂取
考察
第5節 重金属<諏訪園 靖/能川 浩二>
カドミウム
1.1 物理化学的性質、用途と環境汚染
1.2 食品中Cd濃度と1日摂取量
1.3 毒性
1.4 許容値
鉛
2.1 物理化学的性質、用法と環境汚染
2.2 鉛の摂取とその代謝
2.2.1 鉛の摂取量
2.2.2 吸収、排泄
2.3 毒性
2.4 鉛の耐容摂取量と各食品の許容値
2.4.1 鉛の耐容摂取量と日本人の鉛摂取の現状
2.4.2 コーデックスの最大許容基準値案
2.4.3 日本の食品中鉛濃度とコーデックス基準値案
第6章 微生物学的リスクアセスメント
第1節 微生物学リスクアセスメントの考え方<山本 茂貴>
概要
微生物学的リスクアセスメント
第2節 FAO/WHOによる微生物学的リスクアセスメント<豊福 肇>
背景
国際的アプローチによるメリットと限界
JEMRAの主な活動
3.1 科学的な情報の創生
3.2 ガイドラインの作成
3.3 データ収集およびデータ生成
3.4 情報および技術移転
成果
今までに学んだこと
リスクマネジメントにおけるリスクアセスメントの活用
6.1 目的
6.2 リスクアセスメントの活用分野
6.3 MRAが貢献できる分野
第3節 微生物学的リスクアセスメントの実際<春日 文子>
微生物学リスクアセスメント開始の手順
海外での微生物学的リスクアセスメントの例
2.1 アメリカ農務省による殻付き卵と液卵によるサルモネラ・エンテリティディス感染のリスクアセスメント
2.2 FDAによる調理済み食品によるリステリア・モノサイトジェネス感染のリスクアセスメント
2.3 FDAによるカキの生食による腸炎ビブリオ感染のリスクアセスメント
2.4 FAO/WHOによる鶏肉と卵におけるサルモネラ属菌のリスクアセスメント
国内での微生物学的リスクアセスメント
微生物学的リスクアセスメントの適用と将来
第7章 食の安全管理システム
第1節 行政からみた食の安全管理の課題<鈴木 富男>
食品の安全性問題をめぐる状況の変化
1.1 多様化する危害要因
1.2 高度化する食品供給と消費
食品の安全・安心確保のための新たな理念と対応方向
2.1 リスク分析手法の導入
2.2 組織再編の動き
2.3 予防的な対応の強化
2.4 リスクコミュニケーション 2.5 「農場から食卓まで」の安全性確保
2.6 トレーサビリティ
今後の課題 3.1 「農場から食卓まで」の一貫したリスク管理対策の構築
3.2 製造物責任に則った企業の自主管理の助長
3.3 情報収集・分析力の強化、調査・研究や検査の充実
3.4 国民に対する分かりやすい情報提供と正しい知識の普及
第2節 消費者サイドからみた食品の安全管理の現状と期待<板倉 ゆか子>
消費者センターに寄せられる食品に関する相談や苦情の特徴
食品苦情の要因
消費者の様相とその対応
食品関係キーワード別にみた問題点
4.1 食品の保存と日付表示
4.2 食品添加物
4.3 原産国、産地
4.4 環境ホルモンなど
4.5 遺伝子組換え食品
4.6 栄養成分表示
4.7 薬効を期待させる食品
4.8 アレルギー成分
安全管理システムの構築に望まれるもの
5.1 消費者教育
5.2 情報の共有化
5.3 マスメディアの責任
5.4 事業者のコンプライアンス
5.5 事故情報収集システムの構築
第3節 HACCPシステムをめぐる動き<池戸 重信>
わが国におけるHACCPシステムの導入
1.1 HACCPシステムを取り入れた総合衛生管理製造過程制度
1.2 わが国のHACCPの特徴
1.3 わが国におけるHACCPの今後の動向
HACCPシステム導入促進施策
2.1 HACCP支援法の制度
2.1.1 仕組み
2.1.2 金融・税制上の特例による支援措置
2.2 HACCP等マニュアル・ガイドラインの作成
2.3 安全性確保に関する技術開発
HACCPの国際的動向
3.1 コーデックスガイドライン
3.2 アメリカにおけるHACCP
3.3 EUにおけるHACCP
ISOとHACCP
第4節 トレーサビリティの現状と動向<新山 陽子>
トレーサビリティとは -定義-
トレーサビリティの確立の動き
トレーサビリティの目的
制約と課題
何を備えるべきか
5.1 各事業者の行うこと
5.2 食品チェーンにおける事業者の組織
カナダの製品回収プログラムとトレーサビリティ
第5節 トレース技術の実際
(1)実用的なトレーサビリティ技術<杉山 純一>
トレーサビリティとは
食品に必要な実用トレーサビリティとは
トレーサビリティの課題
現実解であるオープン・システムの勧め
Webサービスの実用例-青果ネットカタログ「SEICA」
5.1 登録
5.2 検索
(2)青果物のトレース技術の実際<渡辺 勉>
流通情報管理システムの概要
流通情報管理システムの情報管理の仕組み
2.1 基地識別のIDの付与
2.2 IDタグの付随単位
2.3 生産者での取扱い
2.4 中継流通基地での取扱い(集荷場、市場など)
2.5 輸送車での取扱い
2.6 最終流通基地での取扱い
システムの特長
3.1 IDタグとインターネット、分散サーバの利用
3.2 インターネットメールの利用
3.3 分散サーバ方式の採用
3.4 分散サーバによる青果物の経路における温湿度管理
3.5 NTT無線通信システムによる輸送車の管理
3.6 表示端末
3.7 青果物流通情報
システム付加価値と流通コスト低減
4.1 野菜レシピの提供
4.2 生産者情報
4.3 青果物流通情報
将来展望
第8章 消費者にいかに正確に安全情報を伝えるか
第1節 消費者が求める食品の安全情報とは<宇津木 義雄>
表示に関わる各種調査にみられる消費者の意識
クレーム件数の推移とクレーム情報の公開
食品事故(事件)と消費者の求める情報提供
3.1 BSEの発生
3.2 食肉偽装事件
3.3 残留農薬報道
3.3.1 中国産冷凍野菜
3.3.2 無登録農薬
消費者の声にみる表示の課題
4.1 遺伝子組換え食品の表示
4.2 期限表示について
4.3 食品添加物の表示
4.4 容器包装の材質表示
商品検査情報の提供
食の安全に関わる法律改正の要望
第2節 食品産業の対応策<門間 裕>
食品の安全性を考える
1.1 食品への信頼は本当に揺らいでいるか
1.2 豊かさゆえの欠乏感とリスクへの不安
消費者への情報提供
2.1 食品表示について
2.2 消費者とのコミュニケーションとその課題
食品事故と企業行動規範
3.1 食品事故への対応
3.2 食品企業の行動規範
3.2.1 作成の経緯
3.2.2 行動規範の構成と実効性の確保
第3節 リスクコミュニケーションの考え方<長島 實>
安全の社会認識、今日の課題
リスクマネージメントの定義と運用
レギュラトリーサイエンス議論
消費者参加問題
リスク認知の社会的側面
食の安全性、健常性に向けて
リスクコミュニケーションとメディアの役割
食の安全に応えるコミュニケーションを