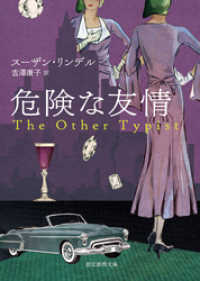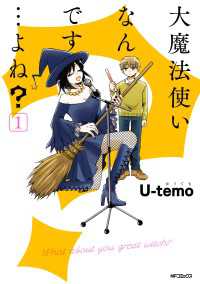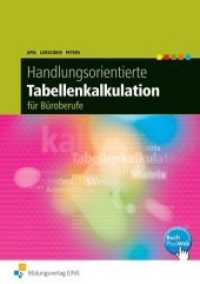出版社内容情報
発刊にあたって
生食用カット野菜は1970年代後半にアメリカで開発された。2000年にはそのアメリカで数千億円
規模の産業にまで成長し、イギリスやフランスでは1千億円近い規模を確保している。またわが国に
おいてもカット野菜産業全体で1千億円程度の規模があると思われる。
カット野菜は簡便性、衛生性、廃棄物の減量、価格安定など食生活上大きな利点がある。しかし、
価格が割高であるとか、褐変、萎れ、異臭の発生、細菌の繁殖などの一般野菜と比べて品質保持
上の難しさがある。
さらに近年、カット野菜の需要の伸びに伴い、鮮度、安全性、高品質などの特性を備えたものが、
従来にも増して要求されるようになってきた。
しかし、カット野菜を全体像として紹介されている例はほとんどなく、また個々の技術については多
くの文献があるが、全体をまとめ、生産から流通・消費までを一望し、しかも現場に役立つ使いやす
い形でまとめたものはなく、 これらの必要性は重要かつ緊急である。
そこで本書では、カット野菜の生産から流通・消費までを4部構成に分け、基礎的な理論から実態
把握、今後の進むべき方向まで、国内のカット野菜に携わる第一人者の方々に執筆頂いた。生産
者、加工業者、流通業者、消費者、研究者まで、多くの人に幅広く役立つハンドブックとしてまとめる
ことができたと自負する。
多くの方々に利用して頂けることを期待する。
発刊日
2002年8月31日
発刊にあたって
生食用カット野菜は1970年代後半にアメリカで開発された。2000年にはそのアメリカで数千億円
規模の産業にまで成長し、イギリスやフランスでは1千億円近い規模を確保している。またわが国に
おいてもカット野菜産業全体で1千億円程度の規模があると思われる。
カット野菜は簡便性、衛生性、廃棄物の減量、価格安定など食生活上大きな利点がある。しかし、
価格が割高であるとか、褐変、萎れ、異臭の発生、細菌の繁殖などの一般野菜と比べて品質保持
上の難しさがある。
さらに近年、カット野菜の需要の伸びに伴い、鮮度、安全性、高品質などの特性を備えたものが、
従来にも増して要求されるようになってきた。
しかし、カット野菜を全体像として紹介されている例はほとんどなく、また個々の技術については多
くの文献があるが、全体をまとめ、生産から流通・消費までを一望し、しかも現場に役立つ使いやす
い形でまとめたものはなく、 これらの必要性は重要かつ緊急である。
そこで本書では、カット野菜の生産から流通・消費までを4部構成に分け、基礎的な理論から実態
把握、今後の進むべき方向まで、国内のカット野菜に携わる第一人者の方々に執筆頂いた。生産
者、加工業者、流通業者、消費者、研究者まで、多くの人に幅広く役立つハンドブックとしてまとめる
ことができたと自負する。
多くの方々に利用して頂けることを期待する。
■ 主要構成
第1部 カット野菜市場の実態
第1章 わが国のカット野菜
第2章 諸外国におけるカット野菜市場
第2部 カット野菜の品質特性とその制御
第1章 カット野菜に適した品種選定と品質保持性の要点
第2章 嗜好適性
第3章 品目別に見た適性品種と品質特性
第3部 カット野菜の微生物制御の手法と実際
第1章 品質に配慮したカット野菜の微生物制御のポイント
第2章 消費者の期待に応えるカット野菜工場の品質管理手法
第3章 カット野菜の洗浄殺菌の実際
第4章 電解水を用いたカット野菜の洗浄殺菌
第5章 各種洗浄・殺菌装置と薬剤の最近の動向
第6章 カット野菜における冷却の必要性と技術ポイント
第4部 カット野菜の生産加工・包装・流通技術の実際
第1章 原料野菜の調達と仕入れ安定化方策
第2章 カット野菜の生産加工
第3章 カット野菜の計量と包装
第4章 カット野菜の流通技術
第5章 カット野菜の廃棄物対策
付属資料 製造機器類および関係資材一覧
■ 内容目次
第1部 カット野菜市場の実態
第1章 わが国のカット野菜
第1節 カット野菜事業の課題と将来展望<舘本 勲武>
1. カット野菜事業の現状と問題点
1.1 品質面からみたカット野菜事業
1.2 経済面から見たカット野菜事業
1.3 安全、衛生面から見たカット野菜事業
2. 野菜が主役になった時代背景-カット野菜の将来展望-
3. お客様の変化
3.1 外食産業の動向
3.2 スーパーの動向
4. 安全面の動向
4.1 野菜の評価基準に問題あり
4.2 原料の安全と製造の安全
5. カット野菜事業の将来展望
第2節 カット野菜の市場実態と業界の取り組み
2-1 カット野菜製造の実態:アンケート調査から<藤枝 洋二>
1. カット野菜製品に対する需要環境
2. カット野菜の種類
3. カット野菜の特質
4. カット野菜製造の実態
4.1 カット野菜製造事業の概要について
4.2 原料野菜について
4.3 カット野菜製品の製造、販売について
4.4 カットフルーツの製造について
5. カット野菜、製造上の留意点と今後の方向
2-2 カット野菜業界発展のための協議会の取り組み<藤枝 洋二/林 翼>
1. 青果物カット事業協議会設立の背景
2. 青果物カット事業協議会の活動
3. カット野菜をめぐる直近3カ年の動き
4. 青果物カット事業協議会活動における今後の課題
第3節 カット野菜製造業の経営的性格<清水 隆房>
1. カット野菜製造業の特徴
2. 立地別事業の経営的性格
3. 用途別事業の経営的性格
4. 企業の系列化
第2章 諸外国におけるカット野菜市場<阿部 一博>
1. アメリカ合衆国における販売・消費
2. その他の諸国における販売・消費
第2部 カット野菜の品質特性とその制御
第1章 カット野菜に適した品種選定と品質保持性の要点<長谷川 美典>
1. 品種・系統と品質
2. 栽培条件と品質
2.1 土壌養分
2.2 生育温度・日較差など
3. 収穫時期と品質
第2章 嗜好適正
第1節 カット野菜とおいしさ<大谷 貴美子>
1. カット(切断)とは
1.1 切断の意義
1.2 切断(カット)の調理科学
1.3 食の条件から見たカット野菜
1.4 時代の流れとカット野菜
2. おいしさとは
2.1 おいしさを決める要因
2.2 おいしさと野菜
2.3 カット野菜のおいしさと価値
第2節 栄養学・嗜好から見たカット野菜<吉田 企世子>
1. なぜ野菜を食べるのか
1.1 栄養素の供給源としての機能
1.2 嗜好性に関する機能
1.3 生理機能性成分の供給源としての機能
2. 野菜接種の現状
3. カット野菜の活用
3.1 カット野菜の成分変動
3.2 食生活へのカット野菜の導入
第3章 品目別に見た適性品種と品質特性
第1節 レタス<永田 雅靖>
1. レタスの品種群
2. カットレタス研究
3. まとめと今後の課題
第2節 キャベツ<永田 雅靖>
1. キャベツの品種群
2. 矢野らの研究
2.1 加工歩留り
2.2 カットキャベツの品質
2.3 品質保持性
3. カットキャベツにおける品質保持機構
4. その他の研究
5. 実際の流通
6. 今後
第3節 カボチャ・サツマイモ<岡田 大士>
1. カボチャ
1.1 カボチャの原料特性
1.2 加工歩留まり
1.3 カボチャのカットに伴う品質劣化とその対策
2. サツマイモ
2.1 サツマイモの原料特性
2.2 加工歩留まり
2.3 サツマイモのカットに伴う品質劣化とその対策
2.4 カットサツマイモの流通温度
第4節 ニンジン<角田 志保>
1. カット後の色調変化と微生物汚染からみた適正品種(鹿児島県農業試験場)
2. 高品質なカット用ニンジンを生産するための肥培管理法(長崎県総合農林試験場)
2.1 堆肥施用の有無および収穫時期による品質の違い
2.2 堆肥の施用量によるカット後の色調変化と官能特性の違い
第5節 バレイショ<高田 明子>
1. カットバレイショを取り巻く状況
2. カットバレイショの製造工程
3. カットバレイショに適する品質特性
3.1 歩留り
3.2 剥皮後の変色
3.3 打撲による変色
3.4 生理的障害
3.5 周年供給と周年出荷
4. カットバレイショの適正品種
4.1 さやか
4.2 ホッカイコガネ
4.3 とうや
4.4 ベニアカリ
4.5 マチルダ
第6節 タマネギ<田中 静幸>
1. 生産と流通
2. 北海道産タマネギの特徴
2.1 作型
2.2 品種
2.3 加工特性
2.4 原料タマネギの障害
第7節 ゴボウ<西田 忠志>
1. カットゴボウにおける品質保持性
2. ゴボウの生理生態と特性
3. 主な産地
4. 栽培日数による形状及び内部成分の変動
5. 内部成分の産地間差異
6. 窒素施肥量が内部成分に及ぼす影響
7. 貯蔵による品質保持
8. 根の形状と加工歩留りの関係
第8節 トマト<石井 孝典>
1. トマトの品質特性
2. カットトマトの加工歩留り
3. 加熱調理材料用トマトの品質特性
第9節 カットフルーツ<松浦 恵>
1. カットフルーツの現状
2. カットフルーツの問題点
3. カットフルーツ今後の方向
第3部 カット野菜の微生物制御の手法と実際
第1章 品質に配慮したカット野菜の微生物制御のポイント<泉 秀実>
1. カット野菜の微生物汚染度
1.1 原料野菜の微生物汚染
1.2 カット野菜製造中の微生物汚染
1.3 カット野菜流通中の微生物汚染
2. 原料野菜の衛生管理と微生物制御
2.1 米国における青果物安全法案
2.2 適正農業規範(GAP)
3. カット野菜製造中の衛生管理と微生物制御
3.1 米国における衛生管理法
3.2 化学的殺菌の利用
3.3 物理的殺菌の利用
4. カット野菜流通中の微生物制御
4.1 化学薬剤の利用
4.2 Controlled atmosphere(CA)/Modified atmosphere packaging(MAP)の利用
第2章 消費者の期待に応えるカット野菜工場の品質管理手法<土肥 由長>
1. 消費者意識の急激な高まり
2. 消費者に“安全、安心”をお届けするために
3. カット野菜の品質管理
3.1 前提はトップの“志(こころざし)”
3.2 組織
3.3 製品規格
3.4 製造マニュアル
3.5 “原料受け入れ”から“製品出荷”までの主なチェックポイント
3.6 社員からパートさんまで、一体感に満ちた従業員教育
3.7 検査分析のための“検体”、万一のための“検食”
3.8 最終製品の検査を待たずに出荷、これはHACCPシステムそのもの
3.9 決め手はトップの抜き打ちチェック
3.10 “継続は力”
4. 信頼獲得には時間がかかる、しかし信頼失墜は一瞬に
5. 努力は報いられる
第3章 カット野菜の洗浄殺菌の実際<石黒 厚/力野 加津子/吉田 淳/中嶋 博>
1. カット野菜の微生物汚染と微生物事故事例
1.1 カット野菜の微生物汚染の実態
1.2 米国による微生物の事故事例
2. カット野菜の洗浄殺菌技術とそのポイント
2.1 目的
2.2 方法
2.3 結果
3. グリセリン脂肪酸エステルの除菌効果とそのメカニズムの解明
3.1 グリセリン脂肪酸エステルの特性
3.2 グリセリン脂肪酸エステルの除菌効果
3.3 グリセリン脂肪酸エステルの効果的使用方法と今後の展開
4. 次亜鉛素酸ナトリウムの製造現場での効果的な活用方法
4.1 製造現場での使用の実際
4.2 殺菌効果を上げるための条件設定
4.3 条件設定における問題点
5. 次亜塩素酸真トリウムを活用した洗浄菌のマニュアルの実際
5.1 学校給食・病院・集団給食その他の洗浄菌マニュアルの実際
5.2 カット野菜の種類別洗浄菌マニュアルの実際
第4章 電解水を用いたカット野菜の洗浄殺菌<伊藤 和彦>
1. カット野菜の洗浄,殺菌
2. 強酸性電解水によるカット野菜の殺菌
2.1 強酸性電解水の生成方法と特性
2.2 強酸性電解水の保存条件と特性値変化
2.3 強酸性電解水によるカット野菜の殺菌
第5章 各種洗浄・殺菌装置と薬剤の最近の動向
第1節 洗浄機
1-1 シリンダー式自動反転洗浄装置(細田工業(株))<山田 健一/榊 孝>
1. 野菜洗浄機の殺菌工程による野菜の損傷と鮮度保持
2. ラクーン(シリンダー式自動反転洗浄装置)ウオッシュマン付
2.1 特徴
2.2 洗浄条件
2.3 レタス洗浄における菌数結果
2.4 レタス洗浄における褐変状況
3. 殺菌水供給システム
4. 活性水製造装置(活性水素水)
1-2 高水圧ジェットキャビテーション洗浄(ショウワ洗浄機(株))<松下 雄介>
1. 高水圧ジェットキャビテーション洗浄機による洗浄方法
2. 洗浄効果
3. まとめ
1-3 異物除去洗浄機(小嶺機械(株))<増田 一郎>
1. 小嶺式異物除去洗浄機の特長
2. 従来の方法との比較
3. 洗浄・殺菌方法
3.1 均一連動型
3.2 殺菌効率を高める
3.3 殺菌効果を管理する
3.4 鮮度保持効果
3. 洗浄機を使用した冷却方法
4. 導入の可否
6. 環境対応
第2節 殺菌装置
2-1 強電解水生成装置(1)(アマノエコテクノロジー)<両角 久>
1. 強酸性電解水生成装置
1.1 α900(FW-900)
1.2 α2000(FW-2000)
1.3 FW-10K(FW-10K)
2. 電解次亜水生成装置
2.1 β8000(FWK-8000)
2-2 強電解水生成装置(2)(ホシザキ電機(株))<阿知波 信夫>
1. 電解水の特徴
1.1 強酸性電解水
1.2 強アルカリ性電解水
2. 装置の特徴とラインナップ
3. 使用実績
4. 今後の展開
第3節 洗浄・除菌剤
3-1 フマル酸製剤 (サラヤ(株))< 上田 明宏>
1. 「シャキシャキ」について
1.1 「シャキシャキ」単独処理の除菌効果
1.2 「シャキシャキ」と次亜塩素酸ナトリウムとの連続処理の除菌効果
2. 「シャキシャキ」処理の実用上の問題点と対策
2.1 食味およびテクスチャーへの影響
2.2 生鮮野菜栄養価の低減
2.3 「シャキシャキ」の処理回数にともなう老化性
3. カット野菜の鮮度保持
3-2 野菜・果実用洗浄剤((株)アルボース )<豊永 正博>
1. アルサワーVの組成
2. 外観及び液性
3. 使用時における前処理方法と留意点
4. 殺菌効果
5. 排水
3-3 カット野菜専用除菌剤(太陽化学(株))<増田 卓也>
1. カット野菜の現状と問題点
2. カット野菜専用除菌剤の開発
3. カット野菜の洗浄・除菌試験
4. 今後の展望
第6章 カット野菜における冷却の必要性と技術ポイント<柳原 伸章/坪田 吉民>
1. 野菜の品質保持と温度の関係
1.1 食中毒菌の増殖制御について
1.2 品質基準と温度の影響
1.3 呼吸及び栄養素の分解と温度
2. 過冷却水製造技術
2.1 冷水製造装置の種類と特徴
2.2 過冷却水を用いた畜氷型チラー
3. カット野菜冷却システムの実際
3.1 カット野菜の冷却計算
3.2 畜氷型チラーの導入事例
第4部 カット野菜の生産加工・包装・流通技術の実際
第1章 原料野菜の調達と仕入安定化方策<清水 隆房>
第1節 原料野菜の商品的性格
第2節 原料野菜の調達方法
第3節 原料野菜の周年仕入安定化方策
第2章 カット野菜の生産加工
第1節 カット野菜生産加工の実務ポイント<村越 正晴>
1. カット野菜を加工するに当たって検討すべき事項
1.1 生産目的及び販売先のニーズの明確化
2. カット野菜の品質保持
2.1 温度管理
2.2 細菌数の制御
2.3 褐変防止対策
2.4 アルコール発酵の制御
2.5 萎れの防止
2.6 その他の品質向上のための法則
2.7 製品、機器類および作業員の手指の洗浄度確認
2.8 その他
第2節 カット野菜加工の実際
2-1 デリカフーズ・グループの取組み<澤田 清春>
1. カット野菜製造の留意点
2. カット野菜加工の実際
3. カット野菜の目標
2-2 サンポー食品株式会社の取組み<岩崎 政男>
1. おいしさ、それは鮮度
2. HACCPシステムに対応した新工場設立
3. 自主規格と品質会議
3.1 自主規格
3.2 品質会議
4. 品温管理は野菜の命
4.1 野菜は生きている
4.2 野菜の特徴をそのまま活かす
5. 安全な食品を作るために
5.1 見た目の5S
5.2 微生物制御
5.3 異物がないこと
5.4 工程管理の実際
2-3 株式会社サラダクラブの取組み<佐藤 明>
1. カット野菜の種類
2. パッケージサラダの製造方法
2.1 微生物の管理
2.2 代表的な製造工程
3. パッケージサラダの包装適性
第3節 カット野菜のスライス技術<榎村 紀彦>
1. スライス技術の基礎
1.1 「切る」って何?(漢字のいい話)
1.2 「切る」「切さい」のバリエイション
1.3 刃物の形状と切れ味
2. 機械装置の標準的種類
2.1 素材供給方法による分類
2.2 切さい方法による分類
2.3 機械装置の具体例とその利用
3. 野菜カット加工技術の実際
3.1 切さいの方法
3.2 野菜カットの実際
4. 野菜カットにおける留意点
4.1 後処理よりも前処理を大切に
4.2 ハード面での配慮
5. 試してみよう!引切りと押切り
第3章 カット野菜の計量と包装
第1節 カット野菜計量のポイント<牧野 伸哉>
1. 最近の計量機の動向
2. 組み合わせ計量機の仕組み
3. カット野菜計量機の設計上のポイント
3.1 国内・海外の食生活の違いによる影響
3.2 性状による影響
3.3 室温による(生野菜の為設置環境による)影響
3.4 カット方法(シュレッド:千切り・短冊・ザク切り)による影響
3.5 水分含有量による(洗浄後の為、脱水具合)影響
3.6 ミックス製品かどうかによる影響
3.7 名前とイメージの違いによる影響
3.8 収穫時期・産地による影響
3.9 供給具合による影響
3.10 計量値による影響
4. 清掃性に関して
第2節 カット野菜包装のポイント
2-1 真空包装<竹田 忠道>
1. 真空包装概要
2. 真空包装機
3. チャンパー式真空包装機
4. 真空包装機の種類
2-2 ピロー包装<武川 廣次>
1. 縦ピロー包装機の概要
2. カット野菜包装
3. 包材
4. 供給方法
5. 包装機
5.1 横シールでの野菜の噛み込み
5.2 横シールのガセット
5.3 ホッパー部でのブリッジ
5.4 袋内の脱気
5.5 カット野菜の付着
6. 環境
7. メンテナンス
第3節 包装材料を選定する設計理論<石川 豊>
第4節 カット野菜の鮮度保持包装の実際
4-1 住友ベークライト<中田 信也>
1. カット野菜の生理
2. カット野菜の鮮度保持
3. MA包装フィルム
4. 「P-プラス」フィルム
5. カット野菜包装材料の現状
6. MA包装の包装設計
7. MA包装と美味しさ・栄養成分の維持効果
4-2 東洋紡<井坂 勤>
1. カット野菜の鮮度保持の基本
1.1 品質管理
1.2 ガス透過性包装の重要性
1.3 ガス充填包装
1.4 防曇性
1.5 密封包装
1.6 蓋材機能
2. 包装上の問題点
2.1 ガス透過性
2.2 防曇性
2.3 ヒートシール性
2.4 密封性
3. 現在の市販カット野菜包装の実態
3.1 包装
3.2 タイプ
3.3 包装形態
3.4 流通温度
3.5 賞味期限
3.6 通気孔
3.7 ガス充填の有無
3.8 防曇性
3.9 印刷数
4. 開発品の特徴
4.1 ガス透過性
4.2 防曇性
4.3 ヒートシール性
4.4 製袋性
5. 鮮度保持効果
5.1 パウチ包装のケース
5.2 カップ蓋材のケース
6. 今後の問題と対策
第4章 カット野菜の流通技術
第1節 カット野菜の流通システム<椎名 武夫>
1. カット野菜の急速冷凍
1.1 カット野菜の冷水冷却
1.2 カット野菜の真空冷却
2. 輸送における品質保持
2.1 保冷
2.2 振動
第2節 鮮度保持技術
2-1 タマネギ搾汁液による褐変抑制<細田 浩>
1. カットレタスの褐変抑制
2. カットリンゴの褐変抑制
3. タマネギ搾汁液中の褐変抑制成分
2-2 ヒノキチオール、コウジ酸<大友 日出男>
1. カット野菜・カットフルーツの鮮度保持
2. ヒノキチオールの性能と機能
3. ヒノキチオール含有保鮮紙
4. ハイテックHCA
第5章 カット野菜の廃棄物対策<鈴木 昌治>
1. 植物性残さの処理対策の状況と課題
2. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)の概要
3. カット野菜残さ対策の基本的考え方
3.1 青果物残さの問題点と利点
3.2 発生抑制
3.3 再生利用技術
3.4 処理形態の諸類型
3.5 循環システムの諸類型
3.6 再資源化事業にかかる経費と採算性
4. まとめ
■執筆者
長谷川美典 独立行政法人 農業技術研究機構 総合企画調整部 研究管理官
舘本 勲武 青果物カット事業協議会 会長
デリカフーズ・グループ代表取締役 社長
藤枝 洋二 青果物カット事業協議会 顧問
林 翼 青果物カット事業協議会 理事
清水 隆房 千葉大学 名誉教授
阿部 一博 大阪府立大学大学院 農学生命科学研究科 教授
大谷貴美子 京都府立大学 人間環境学部食保健学科 助教授
吉田企世子 女子栄養大学 栄養学部実践栄養学科 教授
永田 雅靖 独立行政法人 農業技術研究機構 野菜茶業研究所 収穫後生理研究室長
岡田 大士 鹿児島県農産物加工研究指導センター 流通保蔵研究室 主任研究員
角田 志保 長崎県総合農林試験場 加工化学科
高田 明子 独立行政法人 農業技術研究機構 北海道農業研究センター畑作研究部 ばれいしょ育種研究室
田中 静幸 北海道立北見農業試験場 研究部畑作園芸科長
西田 忠志 北海道立十勝農業試験場 作物研究部てん菜畑作園芸科
石井 孝典 独立行政法人 農業技術研究機構 九州沖縄農業研究センター 畑作研究部 主任研究官
松浦 恵 農林リサーチセンター 代表取締役
泉 秀実 近畿大学生物理工学部 助教授
土肥 由長 どい事務所 所長
石黒 厚 (株)ドンク 品質環境安全管理センター センター長
力野加津子 (株)ドンク 品質環境安全管理センター九州支所
吉田 淳 (株)ドンク 品質環境安全管理センター神戸支所
中嶋 博 (株)ドンク 品質環境安全管理センター名古屋支所
伊藤 和彦 北海道大学大学院 農学研究科農産物加工工学研究室 教授
山田 健一 細田工業(株)営業部統括部長
榊 孝 細田工業(株)関東支店 営業技術課
松下 雄介 ショウワ洗浄機(株)代表取締役
増田 一郎 小嶺機械(株)営業部部長
両角 久 アマノ・エコ・テクノロジー(株)執行役員
阿知波信夫 ホシザキ電機(株)本社製品開発本部
上田 明宏 サラヤ(株)バイオケミカル研究所 次長
豊永 正博 (株)アルボース 技術開発部技術課長
増田 卓也 太陽化学(株)F?T事業部研究開発副主任研究員
柳原 伸章 三浦工業(株)食機事業部 食機技術部部長
坪田 吉民 三浦工業(株)特機技術部
岩崎 征男 サンポー食品(株)事業本部品質管理室長 兼 物流担当チーフマネージャー
村越 正晴 (株)日京クリエイト フードサービス事業本部購買部部長代理
澤田 清春 東京デリカフーズ(株)製造部部長
佐藤 明 (株)サラダクラブ 専務取締役
榎村 紀彦 (株)エムラ販売 代表取締役社長
伊藤 静夫 (株)榎村鐵工所研究開発部取締役技術部長
牧野 伸哉 (株)イシダ 技術部
竹田 忠通 (株)古川製作所 営業部次長
武川 廣次 (株)三和自動機製作所 取締役開発部長
石川 豊 独立行政法人 食品総合研究所 流通安全部 食品包装研究室 主任研究官
中田 信也 住友ベークライト(株)P-プラス開発部 研究統括部長
井坂 勤 東洋紡パッケージング・プラン・サービス(株)代表取締役社長
椎名 武夫 独立行政法人 食品総合研究所 食品工学部 流通工学研究室長
細田 浩 独立行政法人 食品総合研究所 流通安全部 品質制御研究室長
大友日出男 (株)セイワテクニクス 営業部長
鈴木 昌治 東京農業大学 応用生物科学部醸造科学科 教授