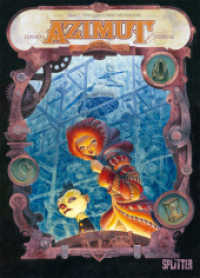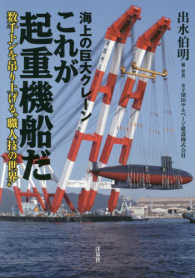出版社内容情報
今求められる中国の環境問題に関する正確な情報と実情。中国環境政策の第一人者による最高の執筆陣をここに結集!現実的対策・技術を中国環境問題解決の指針書として完全網羅!
目次
序章 中国の環境保全に対する政策と行政・研究組織
1 中国の環境政策
2 環境関連法体系
3 環境管理体制・研究組織
4 中国の社会状況
5 中国における経済・社会発展計画及び環境保護政策
第1篇 中国の環境問題の現況と課題
第1章 エネルギー問題と大気汚染
第1節 エネルギー源とエネルギー消費の現況
1 エネルギー源の構成
2 エネルギー消費量の推移
3 エネルギー消費量とSOx,NOx,CO2排出量
第2節 大気汚染
1 煤塵汚染(粉塵とSO2)
2 酸性雨(主としてSO2由来の酸性物質)
3 光化学スモッグ(主としてNOx,HC)
4 大気汚染の建造物と材料への影響
5 大気汚染と呼吸疾患
6 越境汚染と地球環境問題
第2章 水質汚濁
第3章 植生破壊
第1節 中国の植生
第2節 植生の破壊の現状
1 大気汚染と農作物被害
2 大気汚染地域の森林被害
3 森林と植被の破壊及び土壌の流出
第3節 植生破壊の原因
第4章 廃棄物問題
第5章 都市問題
第1節 騒音
第2節 悪臭
第3節 都市への人口移動と過密化
第2篇 中国の環境問題への取り組みと対策技術
第1章 中国の環境問題解決への新しい視点~今後開発すべき技術課題
第2章 エネルギー問題と大気汚染
第1節 燃焼管理-中国のエネルギー消費、環境汚染と燃焼管理-
第2節 クリーンコール化技術
1 選炭
2 ブリケット化
3 ガス化
第3節 燃焼技術の開発(燃焼効率の改善と炉内脱硫)
1 固型炭燃焼技術の開発(民生、中小ボイラ用)
2 循環流動床
3 内部循環流動床ボイラ
第4節 排ガス処理技術の開発
1 集塵技術
2 排煙脱硫技術
第3章 水質汚濁
第4章 植生破壊
第5章 廃棄物問題
第1節 一般廃棄物処理技術
第2節 産業廃棄物
第6章 国際協力
1 発展途上の中日友好環境保全センター
2 東アジア酸性雨ネットワーク
内容目次
序章 中国の環境保全に対する政策と行政・研究組織
1 中国の環境政策(曲 格平)
1 予防を中心とする
1.1 環境保全と資源保護を国家の総合企画と発展計画の中に導入
1.2 都市環境の総合整備を実行
1.3 建設プロジェクトに対する環境管理の強化と新しい、汚染の制御
2 汚染したら、処理
2.1 技術改造と結びつけて工業汚染を予防
2.2 工業汚染に対して期限を決めて処理
2.3 汚染物排出費を徴収
3 環境管理を強化
3.1 法規の制定
3.2 環境管理機関を設立し監督管理を強化
2 環境関連法体系(解 振華)
1 中国における環境関連法体系の形成及び進展
1.1 初期(1973~1978年)
1.2 形成段階(1979~1988年)
1.3 進展段階(1989~1994年)
1.4 完成段階(1994年~)
2 中国における環境関連法体系の構成
2.1 多様な仕組みの中国環境法体系
2.2 豊富な内容の中国における環境関連法体系
3 環境保全における基本的法制度
3.1 環境影響評価制度
3.2 「三同時」制度
3.3 汚染物質排出許可制度
3.4 汚染物質排出費徴収制度
3.5 期限付き改善制度
3.6 旧式工程・設備に係る廃止制度
3 環境管理体制・研究組織(胡 保林)
1 中国における環境管理体制
1.1 立法機関における環境管理体制
1.2 行政機関における環境管理体制
1.3 環境保護委員会について
2 国家環境保護局の責務及び組織
2.1 環境保全の政策について
2.2 環境保全計画について
2.3 環境基準について
2.4 環境管理について
2.5 自然環境保全について
2.6 環境管理制度の実施について
2.7 環境科学及び環境技術について
2.8 環境モニタリングについて
2.9 環境教育について
2.10 環境保全に携わる職員の管理について
2.11 国際環境協力について
2.12 国務院環境保護委員会の実務について
4 中国の社会状況(氷見康二)
1 国土・地理・気象
1.1 地形
1.2 気候
1.3 河川
2 人口・民族・言語・教育
2.1 人口
2.2 民族
2.3 言語
2.4 教育
3 エネルギー・資源
3.1 石油・天然ガス
3.2 石炭
3.3 金属
3.4 電力
3.5 森林
4 交通輸送・通信網
4.1 鉄道
4.2 道路、航空路
4.3 電話、郵便
5 経済状況・産業構造・消費
5.1 対外開放政策と経済改革
5.2 工業
5.3 農業、漁業
5.4 都市と農村の所得格差
6 中国の環境問題特記事項
6.1 松花江の水銀汚染
6.2 黄河の水銀汚染
6.3 「南水北調」政策
6.4 煤塵汚染
5 中国における経済・社会発展計画及び環境保護政策(王 永治/石 康)
1 「八五」計画期問における中国の経済・社会発展及び経済改革
1.1 国民経済の急速な成長
1.2 対外経済の速やかな発展
1.3 国民の生活水準の著しい向上
1.4 経済体制改革の重大な進展
2 「九五」計画期間及び2000年国民経済発展目標
2.1 農業と農村経済の持続的、安定的な発展の確保
2.2 基礎施設と基礎工業の継続的な強化
2.3 中堅産業の振興及び軽工業・紡績工業の調整と向上
2.4 第3次産業の積極的な発展
3 持続可能な発展に関する戦略の推進、環境、経済及び社会の
協和的発展の促進
第1篇 中国の環境問題の現況と課題
第1章 エネルギー問題と大気汚染
第1節 エネルギー源とエネルギー消費の現況
1 エネルギー源の構成(魏 賢勇/宗 志敏/村田逞詮)
1 石油、石炭、ガス、バイオマス、水力、原子力
2 地域別石炭の生産量と硫黄含有量
2.1 地域別石炭の産出量
2.2 硫黄含有量
2 エネルギー消費量の推移(外岡 豊)
1 急成長する中国のエネルギー需要
2 概要
3 エネルギー源別消費動向
4 バイオマス燃料
5 需要部門別エネルギー消費動向
6 工業
7 運輸
8 民生業務
9 民生家庭
10 発電用エネルギー構成の動向
11 地域
3 エネルギー消費量とSOx,NOx,CO2排出量(東野晴行)
1 排出構造の現況
2 排出の地域分布と特徴
3 中国と日本の排出構造比較
第2節 大気汚染(王 璋/高 世東/坂本和彦)
1 煤塵汚染(粉塵とSO2)
1 中国における大気汚染の元凶~石炭燃焼
2 中国における大気エアロゾルによる大気汚染
3 中国におけるSO2による大気汚染
3.1 中国におけるSO2の排出1及び排出強度
3.2 中国における大気中のSO2濃度
2 酸性雨(主としてSO2由来の酸性物質)
1 中国における酸性雨の状況
1.1 全国の状況
1.2 酸性雨の典型的地域~重慶市の状況
2 中国における酸性雨の化学的特徴及び酸性降水の成因と起源
2.1 酸性雨の化学的特徴
2.2 降水酸性化の成因と起源に関する解析
3 光化学スモッグ(主としてNOx,HC)
1 中国におけるNOxによる大気汚染
2 中国における光化学スモッグ汚染
3 光化学スモッグ汚染及びその特徴
4 大気汚染の建造物と材料への影響(前田泰昭/辻野善夫)
1 調査方法
2 結果及び考察
2.1 気象要素
2.2 乾性降下物
2.3 湿性降下物
2.4 腐蝕生成物の観察
5 大気汚染と呼吸疾患(溝口次夫)
1 重慶市の呼吸器疾患
1.1 調査方法
1.2 調査結果
2 考察
6 越境汚染と地球環境問題
1 黄砂の発塵と長距離輸送(全 浩)
2 酸性物質の長距離輸送(池田有光)
2.1 長距離輸送モデル
2.2 硫酸イオン沈着1
2.3 硝酸イオン沈着1
2.4 今後の課題
第2章 水質汚濁(小倉紀雄/馮 延文)
1 水質汚濁の指標と総台評価法(総合水質汚染指数)
2 水質の現状と特性
2.1 雨水
2.2 河川
2.3 地下水
2.4 湖沼
3 水質汚濁の現状と特性
3.1 有機汚濁(COD,BOD)
3.2 富栄養化(N,P)
3.3 重金属
3.4 微量有機汚濁物質
4 水質保全に関するトピックス
4.1 酸性沈着物による南西湖沼の酸性化に関する研究
4.2 西湖の水質改善対策とその効果(河川水の導入)
第3章 植生破壊
第1節 中国の植生(戸塚 績)
第2節 植生の破壊の現状(単 運峰)
1 大気汚染と農作物被害
1 SO2の影響について
2 酸性雨の影響について
3 光化学オキシダント(オゾン)の影響について
4 フッ化水素(HF)の影響について
5 複合汚染の影響について
2 大気汚染地域の森林被害(単 運峰/戸塚 績)
1 都市緑化の樹木の被害
2 重慶市南山における馬尾松林枯損状況
3 四川省万県市奉節県における華山松人工林の立ち枯れ
4 四川省峨帽山における冷杉(Abie sfabri)自然林の立ち枯れ現象
5 柳州市における馬尾松林の被害
3 森林と植被の破壊及び土壌の流出(唐 鴻寿)
1 森林と植被の破壊及び水力の侵食
2 森林植被の破壊及び風力による侵食
第3節 植生破壊の原因
1 酸性雨~重慶市におけるケーススタディ(戸塚 績)
1 重慶市の概要
2 調査方法とその結果
2 柳州市における大気汚染の状況と森林被害(唐 鴻寿)
1 柳州市の背景
2 大気汚染の現状
第4章 廃棄物問題(王 イ/村瀬 広/李 金昌)
1 廃棄物に関する法体系と組織図
2 産業廃棄物の発生と処理処分状況
3 都市ゴミの発生と処理処分状況
3.1 都市ゴミの発生量と組成
3.2 都市ゴミの処理・処分現状
3.2.1 都市ゴミの収集・運搬
3.2.2 都市ゴミの埋立処分
3.2.3 都市ゴミのコンポスト化と焼却処理
第5章 都市問題
第1節 騒音(仲山伸次)
1 騒音問題の現状
2 騒音問題の対策
第2節 悪臭(仲山伸次)
1 悪臭問題の現状
2 悪臭問題の対策
第3節 都市への人口移動と過密化(井村秀文)
1 経済発展と都市化
2 都市化の現状
3 人口移動の状況
4 都市基盤施設の整備
第2篇 中国の環境問題への取り組みと対策技術
第1章 中国の環境問題解決への新しい視~今後開発すべき技術課題点(定方正毅)
1 中国の環境汚染の特徴
2 中国の環境汚染の原因
3 環境汚染解決への技術課題
第2章 エネルギー問題と大気汚染
第1節 燃焼管理-中国のエネルギー消費、環境汚染と燃焼管理-(徐 旭常)
第2節 クリーンコール化技術
1 選炭(村田逞詮/石田 徹)
1 中国における選炭普及の重要性
2 原炭の評価
3 選別装置
4 付帯装置
5 選炭工程の選択法
2 ブリケット化(王 軍/坂本和彦)
1 中国におけるブリケット技術の現状とその展開
1.1 中国における石炭の生産現状及びその問題点
1.2 中国における民生用石炭の使用現状及びその需要予想
1.3 中国ブリケット生産技術及びその特徴
2 バインダレス石炭ブリケットの高圧成型技術(丸山敏彦)
2.1 バイオブリケットの成型特性
2.2 バイオブリケットの燃焼特性
3 ガス化 (安原敬明)
1 テキサコ法石炭ガス化技術
2 プロセスの概要
2.1 基本的化学反応
2.2 プロセスの説明
2.3 テキサコ法の特長
2.4 合成ガスの利用
第3節 燃焼技術の開発(燃焼効率の改善と炉内脱硫)
1 固型炭燃焼技術の開発(民生、中小ボイラ用)(橋本吉昭)
1 はじめに
1.1 固型炭の定義と存在理由
1.2 世界人口100億時代の固型炭の役割
1.3 固型炭の分類
2 中国における固型炭(民生用)
2.1 中国における固型炭の起源
2.2 中国における固型炭の現状
2.3 中国における成型炭製造工場の具体例
2.4 環境への影響
3 日本における固型炭(民生用)
3.1 日本における固型炭の起源
3.2 日本における固型炭の現状
3.3 環境への影響
3.4 日本における固型炭の技術
3.5 日本における固型炭のための燃焼器の技術
2 循環流動床 (友保純直)
1 循環流動床ボイラ開発の経緯
2 循環流動床ボイラの基本原理と特徴
2.1 循環流動床ボイラの構成要素
2.2 コンバスタ及び外部熱交換器
2.3 粒子分離装置
2.4 粒子循環量の制御及び燃焼温度の制御
2.5 対流伝熱部及び煤塵除去装置
3 中国における循環流動床ボイラ
3.1 中国国産の循環流動床ボイラの現状
3.2 中国向け循環流動床ボイラヘの配慮事項
3 内部循環流動床ボイラ(大下孝裕)
1 内部循環流動床ボイラ(ICFB)
1.1 構造と機能
1.2 層温制御
1.3 炉内脱硫
2 ICFBの特異な実施例
3 中国製ICFBによる中国炭の燃焼
4 加圧内部循環流動床ボイラ(PICFB)
第4節 排ガス処理技術の開発
1 集塵技術(牧野尚夫)
1 サイクロン
1.1 サイクロンの特徴
1.2 サイクロンの性能向上
2 電気集塵機
2.1 電気集塵機の特徴
2.2 電気集塵機の性能向上
2.2.1 電気抵抗を低下する方法
2.2.2 電気集塵機の改良
2 排煙脱硫技術(城戸伸夫/定方正毅)
1 現状の脱硫技術とその評価
1.1 排煙脱硫技術の現状
1.1.1 石灰スラリー吸収法
1.1.2 水酸化マグネシウムスラリー吸収法
1.1.3 その他の湿式法
1.2 現状の排煙脱硫技術の評価
1.2.1 建設コスト
1.2.2 運転費
1.2.3 副生品
1.2.4 工業用水の確保とその処理
2 期待される脱硫技術の開発と実用化の展望
2.1 中国向けの新たな脱硫技術
2.2 中国向け脱硫技術の内容
2.2.1 炉内への石灰石直接吹込法
2.2.2 スプレードライヤー法
2.2.3 簡易型石灰石膏法
2.2.4 その他の簡易湿式法
2.2.5 電子ビーム照射法
2.3 中国における排煙脱硫技術の展望
第3章 水質汚濁(徐 開欽/須藤隆一)
1 中国における水資源の不足と緩和対策
1.1 水資源不足
1.2 地下水と地盤沈下
1.3 水資源不足の緩和対策
2 中国における水質汚濁と排水処理の動向
2.1 水質汚濁の現状
2.2 中国における給・排水処理システムの発展動向
3 中国の水質汚濁対策
3.1 水質汚濁への行政的取り組み
3.2 水質汚濁監視活動
3.3 水質汚濁対策技術
4 水域の富栄養化とその対策
4.1 富栄養化の影響
4.2 中国における富栄養化の被害実態
4.3 中国の富栄養化の防止対策
5 環境基準と環境政策への取り組み
5.1 中国の環境基準
5.2 中国における環境政策と環境教育への取り組み
第4章 植生破壊(唐 鴻寿/楼 雪芳)
1 大気汚染による植生破壊に対する対策
1.1 主要な汚染物質の排出抑制
1.2 面源汚染を減少し、郷鎮企業を厳しく規制
1.3 都市ガス、天然ガスと液化石油ガスに切り替える
1.4 粉塵の除去及び石炭の脱硫
1.5 目動車の排ガスを抑制する
1.6 大気汚染の監測ネットワークの設立
1.7 土壌酸化性に対する臨界負荷量についての研究
1.8 抵抗性種を利用する
1.9 特別な樹種を保護し育成する
1.10 抵抗性植物の選定
1.11 科学研究の成果の普及
2 植生破壊に伴う土壌流出の防除対策
2.1 造林面積を拡大し、植栽した幼木の保護育成を強化
2.2 高木、低木、草木種を混植させる植被群を開発する
2.3 自然法則に従い科学的造林をする
2.4 保安林の建設及び小流域の総合整備
2.5 造林と草地造成を民衆の必要性と経済収入の増加に結合させる
2.6 水資源を合理的に分配し、総合的に生態影響を考える
2.7 関連法制を完備し、法律の執行を強化する
2.8 採鉱チームに対する監督を強める
2.9 天然草原の家畜の数を厳格に制限し、過度の放牧を禁止
2.10 薪の採取及び過度の薬剤採取の規制
2.11 荒地の開墾の規制
2.12 人口増加の厳格な規制
2.13 全意識の強化
3 三峡ダム建設で水没する地域の植物保護対策
3.1 ダム地域の現状
3.2 植生に対する水没の影響
3.3 水没地域の植物保護対策
第5章 廃棄物問題
第1節 一般廃棄物処理技術
1 埋立処分技術
1.1 埋立処分の現状
1.2 衛生埋立技術の概要
1.3 埋立技術の今後の課題
2 収集システムの改革
3 生物処理技術(コンポスティング)
3.1 中国のゴミ質の現状と日本との比較
3.2 収集/前処理
3.3 コンポスト化
3.4 原料について
3.5 中国で普及促進されているコンポストプラントのフロー
4 生物処理技術(し尿処理)
5 燃焼炉の技術的展望
5.1 ストーカ式焼却炉
5.2 流動床式焼冢?
5.3 灰処理技術問題と廃棄物のガス化溶融炉等の新技術動向
5.4 廃棄物焼却排ガス処理問題
5.5 熱利用技術
第2節 産業廃棄物(村瀬 広/王 偉/南原健二/鈴木隆幸/川上 亨/半田 均/石井 昇)
1 産業廃棄物処理対策技術とリサイクル
2 プラスチックとリサイクル
2.1 マテリアルリサイクル
2.2 RDF(ゴミ固形燃料)
2.3 プラスチック油化、分解再生
3 中国における石炭灰の有効利用技術の現状と展望
4 中国における有害廃棄物処理処分技術の動向
第6章 国際協力 1 発展途上の中日友好環境保全センター(張 坤)
1 建設の基礎の定め
1.1 プロジェクトの形成
1.2 基本建設の実施
2 稼働は穏やか、契機はスムーズ
2.1 稼働し始めは基礎を良くする
2.2 管理を強め、基本保障を確保
2.3 科学研究を進め、国際協力の歩みを進める
3 未来を展望して、自信満々
3.1 いい発展の勢い
3.2 中日間の技術協力は深めになる
3.3 「中心」はAPECに向けてオープンする見通しは人々を奮い立たせる
2 東アジア酸性雨ネットワーク(柳下正治)
1 酸性雨について
2 我が国における酸性雨の現状
2.1 酸性雨モニタリング結果
2.2 我が国としての酸性雨問題に対する今後の対応
3 東アジア酸性雨モニタリングネットワーク
3.1 経緯
3.2 専門家会合の開催とコンセンサスづくり
3.3 束アジア酸性雨モニタリングネットワーク構想
[付属資料]
[この頁の先頭へ]
執筆者一覧
*所属・肩書き等は発刊当時のものです
■編集委員長
定方正毅 東京大学工学部化学システム工学科教授
■編集委員
戸塚 績 江戸川大学社会学部環境情報学科教授
坂本和彦 埼玉大学大学院理工学研究科教授
村田逞詮 三井造船(株)技術本部技術総括部主査
全 浩 中国国家環境保護局中日友好環境保護中心総工程師
■執筆者
曲 格平 全国人民代表大会常務委員会環境と資源委員会主任
解 振華 中国国家環境保護局局長
胡 保林 中国国家環境保護局行政体制・人事司司長
氷見康二 東京薬科大学生命科学部講師/麻布大学環境保健学部講師/(財)日本環境衛生センター技術顧問
王 永治 中国国家計画委員会宏観経済研究院副院長
石 康 中国国家計画委員会宏観経済研究院副研究員
魏 賢勇 中国砿業大学能源利用化学工程系教授
宗志 敏 中国砿業大学能源利用化学工程系講師
村田逞詮 三井造船(株)技術本部技術総括部主査
外岡 豊 埼玉大学経済学部社会環境設計学科教授
東野晴行 通商産業省工業技術院資源環境技術総合研究所安全工学部化学物質安全研究室
王 中国環境科学研究院
高 世東 重慶市環境保護科学研究所
坂本和彦 埼玉大学大学院理工学研究科教授
前田泰昭 大阪府立大学工学部機能物質科学科教授
辻野善夫 大阪府公害監視センター主任研究員
溝口次夫 佛教大学社会学部社会学科教授
全 浩 中国国家環境保護局中日友好環境保護中心総工程師
池田有光 大阪府立大学工学部エネルギー機械工学科教授
小倉紀雄 東京農工大学農学部環境・資源学科教授
馮 延文 東京農工大学大学院農学研究科専攻
戸塚 績 江戸川大学社会学部環境情報学科教授
単 運峰 日本学術振興会外国人特別研究員
唐 鴻寿 中国科学院生態環境研究中心助理研究員
王 偉 清華大学環境工程系助教授
村瀬 広 (株)荏原製作所エンジニアリング事業本部企画調査室部長
李 金昌 北京金昌環境研究所所長
仲山伸次 (財)日本環境衛生センター総局企画部企画調整室専門官
井村秀文 九州大学工学部附属環境システム工学研究センター教授
定方正毅 東京大学工学部化学システム工学科教授
徐 旭常 中国清華大学熱能工程系教授
石田 徹 三井鉱山エンジニアリング(株)海外第四事業部副部長
王 軍 沈陽環境科学研究所
丸山敏彦 (財)北海道科学産業技術振興財団理事・研究開発部長
安原敬明 宇部興産(株)化学・樹脂事業本部監理部主席研究員
橋本吉昭 橋本産業(株)取締役副社長
友保純直 三井造船(株)エネルギープラント事業部技師長
大下孝裕 (株)荏原製作所環境開発センターセンター長
牧野尚夫 (財)電力中央研究所エネルギー化学部部長・上席研究員
城戸伸夫 資源環境技術総合研究所統括研究調査官
徐 開欽 東北大学大学院工学研究科土木工学専攻助教授
須藤隆一 東北大学大学院工学研究科土木工学専攻教授
楼 雪芳 東京農工大学農学部応用生物学科
南原健二 (株)荏原製作所エンジニアリング資源再利用事業部プロジェクト計画技術部
鈴木隆幸 (株)荏原製作所エンジニアリング事業本部企画調査室部
川上 亨 (株)荏原製作所エンジニアリング事業本部環境プラント事業部技術第二部
半田 均 (株)荏原製作所エンジニアリング事業本部環境プラント事業部プロジェクト部部長
石井 昇 (株)荏原製作所エンジニアリング事業本部環境プラント事業部技術第一部副部長
張 坤 中国国家環境保護局中日友好環境保全中心主任
柳下 正治 環境庁企画調整局地球環境部企画課課長
明日香壽川 東北大学東北アジア研究センター助教授