内容説明
内務省の検閲とGHQの検閲、戦中と戦後に無残なまでの書き直しを強いられた太宰治の小説。米国メリーランド大学のプランゲ文庫検閲資料の現地調査を踏まえ、その数奇な運命を探る。
目次
大宰治の単行本における本文の問題―戦後の検閲を中心に
「鉄面皮」と「右大臣実朝」―「変更」と「変更しないこと」が意味するもの
『佳日』から『黄村先生言行録』へ
『新釈諸国噺』―第四版の「凡例」と「人魚の海」
『津軽』―本文と挿絵の異同が物語る戦中戦後
『惜別』―再版本における削除を中心に
『お伽草紙』
「パンドラの匣」
「貨幣」―戦後の検閲の揺らぎ
著者等紹介
安藤宏[アンドウヒロシ]
東京大学大学院人文社会系研究科教授
斎藤理生[サイトウマサオ]
大阪大学大学院文学研究科准教授
小澤純[オザワジュン]
慶應義塾志木高等学校教諭、同大学・恵泉女学園大学非常勤講師
吉岡真緒[ヨシオカマオ]
國學院大學ほか非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
56
作家はより良く仕上げるためだけでなく、権力による検閲を逃れるため改稿する。日本でも戦前は軍や警察、戦後は占領軍が厳しい目を光らせた。一貫して検閲のある時代に生きた太宰治の文章がどう変遷したか、変えざるを得なかったかを辿っていく。価値観が逆転した戦前戦後で、言葉の専門家である作家が本を刊行するのに苦労する様が浮かび上がる。担当者の気分や時々の政治情勢で変化する基準に太宰も振り回され、検閲を見込んで忖度した改稿も見受けられるなど格好悪い部分も露呈する。太宰の弱さ、人間臭さを政治的側面から見られるかもしれない。2021/03/15
-

- 電子書籍
- 本物の娘が帰ってきた【タテヨミ】第32…
-

- 電子書籍
- 脱いで触って愛して【マイクロ】(71)…
-
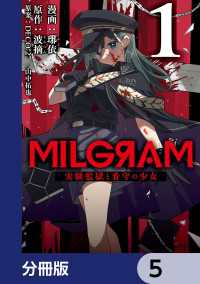
- 電子書籍
- MILGRAM 実験監獄と看守の少女【…
-
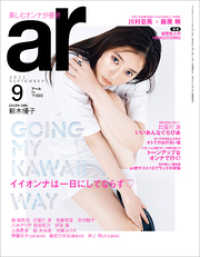
- 電子書籍
- ar 2022年 09月号 ar
-

- 電子書籍
- 青野くんに触りたいから死にたい 分冊版…




