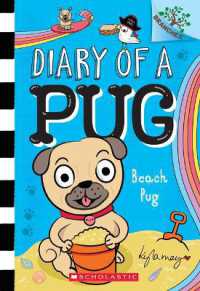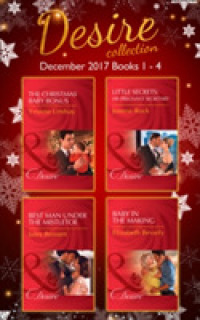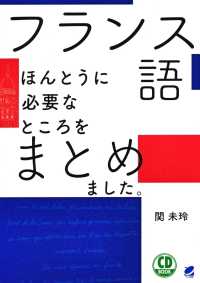著者等紹介
舘石昭[タテイシアキラ]
1930年、千葉県に生まれる。千葉大学工学部工業意匠学科に在学中、毎日新聞社主催の全国学生油絵コンクールで毎日新聞社賞受賞。1956年に、絵のモチーフを水中に求めてダイビングを始める。やがて手作りのハウジングで水中撮影を始め、アートを感じさせる彼の水中写真は、ほどなく新たな芸術表現となっていく。1957年、日本で最初の水中写真展を開催。同じ年、日本初の長編カラー海底映画「海は生きている」(岩波映画・羽仁進監督)の水中撮影を担当。水中撮影におけるこうした成功を機に、1958年、水中造形センターを設立する。1960年に初めての16mm水中記録映画「海底の動物」を制作。その後6つの映画それぞれで水中撮影を担当する。1966年4月には、羽田空港の沖、水深28mで全日空機墜落事故をスクープ。朝日新聞、TBSなどで発表。同年4月、「タテイシブロニカマリンI」を試作。また、9月には著書『水中撮影1000時間』(秋田書店)が発売される。業界での実績と名声は上がり、1967年11月には総理府、(財)海中公園センターの依頼で、日本初の海中公園適地の探査のために専門調査員の一人として沖縄へ派遣される。水中撮影に関する技術面への探究も続き、同年には「タテイシブロニカマリンII」のデザイン。1968~1969年にかけては、フィリピン・ルソン島沖で第二次世界大戦時の海軍巡洋艦「熊野」の撮影、琉球政府(現在の沖縄県)のPR映画「沖縄の海」の企画、制作、撮影を担当。さらに、PR映画「沖縄をたずねて」の企画、制作、撮影も担当する。1969年、スクーバーダイビングのさらなる普及を目的に、日本初のダイビング雑誌『マリンダイビング』を創刊。こうした活動の傍ら、「週刊朝日」「アサヒカメラ」「アサヒグラフ」といった雑誌にも作品を発表し続ける。他媒体の仕事を通して、日本にモルディブやその水中世界の作品を紹介していく。やがて水中ヌードの作品を発表し、日本の写真界にセンセーションを巻き起こし、テレビをはじめ映像の世界でも数々の作品を手がける。1971年4月、「タテイシブロニカマリンII」が発売され、銀座の富士フォトサロンでは、舘石昭写真展「サンゴ礁の造形」が開催される。同じ年、コカ・コーラ主催イベントのため、オーストラリアのヘロン島に招待される。その後、カンタス航空のPR映画やサンボアンガにて撮影のフィリピン航空のPR映画などを手がける。1972年、西ドイツPutnam社出版の英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語表記の写真集『The Coral Sea』に日本でただ一人、作品を掲載される。この年、2冊の写真集『海のさかな』『沖縄のサンゴ礁と熱帯魚』を刊行。同年銀座和光ホール、富士フォトサロンで写真展開催。さらに、1975年には写真集『青い世界の仲間たち』を発表。1973~1975年、銀座、原宿など東京各地で写真展を開催。1975年にはまた、オーストラリアの地底湖のダイビングに挑戦。これが話題になり、日本テレビ「11PM」に出演し、シンクホール・ダイビングを日本に紹介する。さらに舘石昭のアイデアで開発された「タテイシ キャノン マリンM」が発売される。同年、朝日カルチャーセンターで水中写真コースの講師を務める。1977年、巨大カスリハタを撮影にバハカリフォルニアへ出かける。1978年、ビーチ&リゾートのベストマガジン『海と島の旅』を創刊。1976年には東京美術館に水中写真の作品が初めて展示(JPS第1回展)されるなど、これまでの活動で、舘石昭は水中写真の先駆者としての地位を確かなものにしていく。作品が、沖縄の西表国立公園記念切手になったこともある。1977年、水中造形センター(1958年に設立)は、株式会社に改組
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。