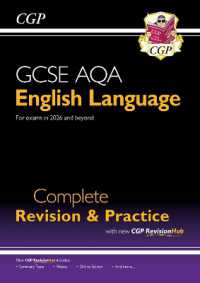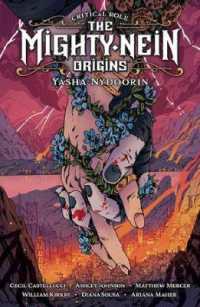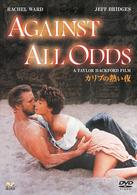内容説明
気仙沼のリアス・アーク美術館には東日本大震災の「被災物」が展示されている。この展示に触発された著者が大阪で「被災物ワークショップ」を始めると、被災物を見た人々は思わず自らの記憶を語り出した。阪神大震災、幼い日の傷、亡くなった娘のぬいぐるみ、広島の経験…痛みでつながることで、当事者/非当事者の境界を越えて、命と記憶は語りつがれていく。「復興」の物語からはみだす、小さな“モノ語り”の記録。志賀理江子の撮り下ろし写真カラー16頁。
目次
1 終わりと始まり(「被災物に応答せよ」―第三者による記憶の継承という問い;モノ語り集1 ほか)
2 「モノ」語りは増殖する(「被災物」は記憶を解き放つ―記憶のケアとしての「モノ語り」;モノ語り集2 ほか)
3 氾物語―躊躇なく触る(リアス・アーク美術館に眠るもの;土の時間、水の時間―志賀理江子との対話)
4 恵比寿の到来(ナニカが海からやってくる;えべっさま、ようきてくれましたな ほか)
5 新しい祭りへ(南三陸集会+気仙沼への旅;エビスが語りて命をつなぐ)