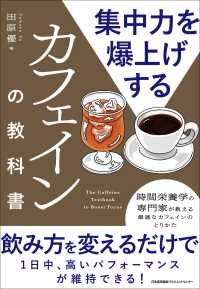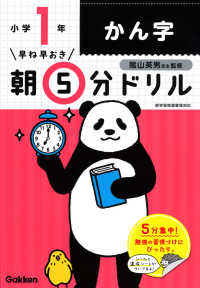内容説明
140年前の宮廷ドレスと資料から近代国家への歩みを紐解く。和装から洋装へ―宮内庁担当記者が見た近代日本の栄華と影。
目次
序章 よみがえる明治の大礼服(傷だらけのマント・ド・クール修復プロジェクトの発足;最古の大礼服に残る国産のあかし ほか)
第1章 皇后とドレス―日本近代化の象徴(大礼服の文様はバラから菊花へ;肖像写真に残るドイツ製大礼服第一号 ほか)
第2章 皇后の側近が見た宮中の国際化(皇后のスタイリスト誕生;総理大臣から妻への手紙 ほか)
第3章 近代日本の栄華の舞台裏(和洋折衷の仕事場兼お住まい;立憲国家の船出と皇后のドレスの値段 ほか)
終章 宮廷ドレスのこれから(自然消滅か復元・保存か―所蔵者の悩み;記録保存と情報発信を―三笠宮家の彬子さま)
著者等紹介
吉原康和[ヨシハラヤスカズ]
東京新聞編集委員。1957年、茨城県生まれ。立命館大学卒。86年に中日新聞社(東京新聞)入社。水戸支局を経て、92年から東京社会部。警視庁、運輸省(現在の国土交通省)、警察庁、宮内庁などを取材した。その後、特別報道部デスク、水戸、横浜両支局長、写真部長を経て、2015年から現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
くさてる
29
あたりまえのことながら、皇室の人々が洋装、それもドレスを着用し始めたのは明治時代。いわゆる大礼服の美しさと桁違いの費用を知り、現在行われている当時のドレスの復元と修復のレポートを興味深く読んだ。近代日本が西洋文化を取り入れていくための工夫と苦労、伝統と技術を生かしたドレス作りはドキュメンタリーになりそう。美しくも面白い一冊でした。2022/12/14
ふう
28
ちょうど今日開幕の、「受け継がれし明治のドレス」展にあわせて。今日はシンポジウムもあり、近ければ拝聴したかった。昨秋テレビでも紹介された大聖寺のドレスを含め、鹿鳴館を彩った美しいドレスの数々が紹介され、また神格化に伴い外出が減った天皇に対し、洋装して女学校や病院への訪問が増えた皇后の写真だけでなくドレスの値段まで、なかなか興味深い資料が収められている。華族の女性たちのドレスもドイツ、フランス、イギリス、そして国産のもの、それぞれに美しい。西洋化を受け入れながら、伝統文化と国内産業を守る姿勢にも感じいった。2024/04/06
meru
21
図書館で目にとまったので読んでみた。なんと明治時代の皇后さまが国策の為に着用された大礼服。明治憲法が発令され これからは日本も世界と並ぶ国だと胸をはって古来からの和装に代わって皇后が自ら発信したものであった。美しいドレスにまつわる物語は日本の世界への幕開けでもあったのだ。なんと深い!そして今では制作出来ない芸術品だったとは!感動2025/09/06
hirorin
10
京都のお寺に保存されていた昭憲皇太后のドレスを再現する番組を見て、本があったので読んでみた。ドレスの写真も多いのだけれど、興味を引いたのは、それまで着物で過ごしていた皇后がドレスを着るのに「お国のため」と深く強い思いで臨まれたこと。初めは、ヨーロッパで注文していたけれど皇后自ら、できるだけ日本製をと言われたこと。だから柄も薔薇から菊や藤に。そんな悲壮な覚悟でドレスに袖を通していたとは。そして、昔の女性がとても細くて小さい。えええ~子供が着るの?って。私なんか、腕すら通らないよ。2023/04/15
hitotak
9
戦前の皇室女性の最高礼装だったマント・ド・クール(大礼服)について、明治期の苦労話や各地に残るドレスの保存状況、驚きの価格などその歴史的価値について語られている。著者はドレスそのものについてはあまり興味がないのか、ドレスのデザインや刺繍、本場ヨーロッパ王室のドレスなど、私が見たい・知りたい部分については殆ど取り上げられていないのが残念。新年の参内など、大礼服着用の儀式にドレスが作れないために出席できない華族夫人も多かったというのは興味深い。無理をしてでも西洋の慣習に合わせ、近代化を進めていたことがわかる。2022/12/11