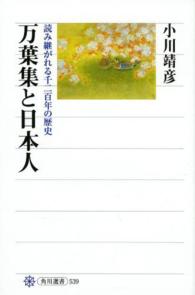内容説明
死者の尊厳を改めて問い直す。変容する死生観―これからの私たちは故人をどう見送り、どう弔うのか?
目次
葬式が消滅していく
なぜ葬式は消滅するのか
お弔いが葬儀社依存になった理由
江戸時代の寺請制度はなぜ今に影響するのか
現代の葬式が抱える数々の矛盾
余計なものは次々と省かれていく
死生観の変容―死は昔ほど重要ではない
家族葬から家庭葬へ
墓はすっかり時代遅れになった
これから葬式はどうなっていくのか
今、葬式をどう考えればいいのか
著者等紹介
島田裕巳[シマダヒロミ]
1953年、東京都生まれ。作家、宗教学者、東京女子大学非常勤講師。1976年、東京大学文学部宗教学宗教史学専修課程卒業。1984年、同大学大学院人文科学研究科博士課程修了(宗教学専攻)。日本女子大学教授、東京大学先端科学技術研究センター特任研究員などを歴任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
138
父の葬式は実家が檀家だった宗派の僧侶を呼んで執り行ったが、宗教と業者が手を組んだ葬祭の見たくない裏側をいろいろ見てしまった。そんなビジネスとしての葬儀を嫌った母は年忌法要をせず、今から「自分が死んだら家族葬で。戒名も位牌もいらない」と言っている。母と同じ思いをする人が増え、イエ制度の崩壊やコロナ流行もあって葬式自体が消えつつある。納骨堂も運営業者の破綻で安住の場を失うなど、墓のあり方すら従来の常識が覆されてきた。将来の葬儀は先日の英女王の国葬のように、やりたい人かやらねばならない人だけがするものになろう。2022/11/19
kinkin
84
読み終わった日、NHKのクローズアップ現代で、葬式の費用にまつわる問題がとても増えていることについて特集を組んでいた。広告で50万円と書かれているにも関わらずいろいろなオプションを勝手につけられてその倍くらいの見積りになったりするケースなど。昔は葬儀というと近くの公民館を借りて祭壇などは葬儀屋が組んで、下足番や受付などは近所の人に頼んでいたのを知っている。今は本にも書かれてるように駐車場の問題や近所付き合いがなくなったことでほとんどが葬祭ホールに変化した。低所得の人では今の葬儀は無理・・・・2025/12/08
がらくたどん
63
何となく「そういうもんだ」と思っていた葬儀場での仏式葬儀を成り立ちと費用の面から解剖しお葬式の形ってそこまで厳格な決まり事じゃなかったんだ!と目から鱗だった『葬式は、要らない』から12年。高額戒名・大規模葬儀への思い込みを再考する人が増えたことに加え、コロナ禍で図らずも葬儀を大胆に簡素化する実証実験ができてしまった現在の葬式事情を俯瞰する。印象的なのは「遺骨」問題。火葬炉を骨が残る仕様に最適化したためお骨がセラミック化して自然融解しにくいそうだ。拾骨習慣の東西差と合わせて命の循環の輪に戻りたい気もする。2022/10/04
けぴ
50
仏教徒で無くても葬式はなんとなく仏教式が殆ど占める日本。戒名という不思議な制度は日本独自のものでビジネスとして発達してきたもののようです。コロナで葬式が自粛されたこともあり、家族葬から家庭葬にシフトしてきている。長生きして社会からリタイアして久しくなってから亡くなることも一般葬が減少した一因。お墓も無縁になるかところが多く、従来の枠組みは今後更に変わっていきそうです。2024/03/02
よっち
41
自然葬、海洋葬を実際に行ない、葬送の自由を進めてきた著者が、葬式がどのように今のような形になってきたのかを踏まえつつ、これからの時代を見据えたお葬式を考察した一冊。直葬などの登場でお葬式はますます簡素で小さくなり、見送る遺族はお骨を持ち帰らないという葬儀も出現。高額な戒名も不要、お墓も不要となってきた現代は、コロナの影響も大きかったりで確実に家から家庭の葬式に移行しつつあるのかもしれないですね。親の世代がいるうちはそこまで変わらないにしても、これからどうかわっていくのかいろいろと考えさせられる一冊でした。2022/08/02