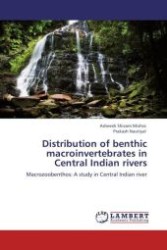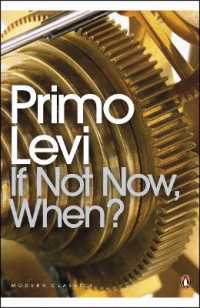内容説明
巨大墳墓を造った古代日本人が墓に執着しなくなったのはなぜか?それが近世に墓参を必ずするように変わり、そして今お墓を捨てる者まで現れたのはなぜか!?日本思想史の第一人者が列島の数多くの霊場をたずね解明した画期的な激変する他界観の正体「人は死んだら消えてなくなる」とした民族はこの地球上に存在しなかった!
目次
第1部 中世―近世の他界観のゆらぎ(遊仙寺(宮城)
医王寺(福島) ほか)
第2部 古代からカミと仏の習合へ(大湯環状列石(秋田)
箸墓(奈良) ほか)
第3部 近世に向けて失われる浄土世界(瑞巌寺(宮城)
岩船山(栃木) ほか)
第4部 近代―現代の仏をなくした他界観(モリの山(山形)
西来院(岩手) ほか)
著者等紹介
佐藤弘夫[サトウヒロオ]
1953(昭和28)年、宮城県生まれ。東北大学大学院文学研究科博士前期課程修了。博士(文学)。盛岡大学助教授などを経て、東北大学大学院文学研究科教授。専門は日本思想史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ネギっ子gen
62
【巨大墳墓を造った日本人が、「墓に私はいない」と歌い、墓を捨てるようになったのは、何故なのか?】日本思想史の第一人者が日本各地の霊場を訪ね、激変する他界観の正体を解明する書。2021年刊。巻末に「日本における他界観の今日に至るまでの歴史的推移・表」と参考文献。<死後の世界が実際に存在するかどうかという議論には、ここでは立ち入りません。むしろ重要なのは、これまでの人類の歴史において、その実在が所与の前提とされてきたことです。死者の世界をイメージしない民族は、この地球上にかつて一つも存在しませんでした>と。⇒2025/01/21
ピンガペンギン
29
著者は東北大教授(専門・日本思想史)。全宗派住職が読む雑誌の連載がもとになっている。通して読むと日本人の他界観の変遷が理解できる。写真が多くて親しみやすい。お坊さん向け雑誌だけあり、一般の人は興味は持たないような詳しい記述も多いが、面白く読める内容となっている。中世(平安時代後期)の浄土信仰の時代に、山寺(本堂)プラス奥の院というスタイルが確立し、奥の院は聖人(弘法大師、慈恵大師など)に関わる場所であり、P92にあるように納骨の場所であった場合もある。第20章は東北の津波跡地に関わる内容で、本格的な復興→2025/05/22
tecchan
1
人は死んだらどこにいくのか。日本人の死生観の変遷について全国の寺社等を訪ね歴史的に探る。「生者は死者を必要としている。人生のストーリーは、死後の世界と死者を組み込むことで完結」「生者と死者の関係は家を媒介した社会的な関係より個人同士の関係へと変化」という言葉に納得。2022/04/22
muuk
0
古代から中世、近世、そして現代と、人が死んだ後で、その魂が「どこへ行けばいいのか」を各地の社寺を巡りながら考察していく。権力構造や仏教伝来、経済事情、そして家族のあり方など、意外と「俗」な理由で宗教観や死者の弔いが変わっていくことがわかって面白い。3章までは「お勉強」として読み進めたが、身近な4章になると我が事としてぐっと内容に引きこまれていった。墓じまいが話題になる現代、私たちの魂はどこにいけばいいのか、改めて考えさせられた。2024/12/15
Junko Yamamoto
0
東日本の聖地が紹介されていて参考になった。2021/06/13