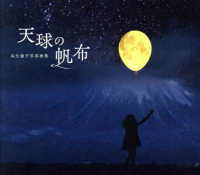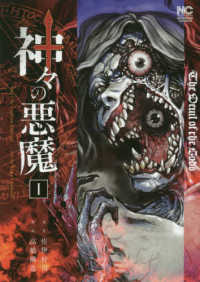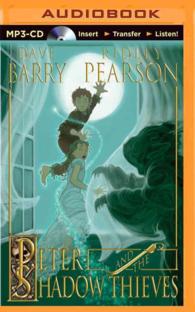内容説明
モノづくりの歴史をたどれば、日本が見える。小さな列島のなかで、有形無形さまざまなモノをつくってきた日本人。なぜつくったのか、つくったことで社会はどう変わってきたのか、そしてこの先は?日本の「モノづくり」の背景や環境を読み解き、未来への展望につなげる、歴史と文化のガイドブック。
目次
第1章 最高水準の狩猟採集生活から世界標準の農耕生活へ―縄文と弥生
第2章 倭国の時代のモノづくり 最初の日本列島大改造―西暦四〇〇年の日本
第3章 平安京をつくったら女流作家とサムライが登場―西暦八〇〇年の日本
第4章 サムライたちの国づくり 中央集権から地方分権の時代へ―西暦一二〇〇年の日本
第5章 冬の時代が終わると大江戸づくりがはじまった―西暦一六〇〇年の日本
第6章 富国強兵の時代―近代日本のモノづくり体系
第7章 富国軽兵の時代―現代日本のモノづくり体系
第8章 ハイパー・スーパー・超絶の時代―二〇〇〇年の日本
著者等紹介
入船もとる[イリフネモトル]
1955年、福岡県生まれ。幼少期よりSF小説に親しみ、やがて中国に関するものを中心に、父の大量の蔵書を耽読。中学時代より日本史に関心を寄せる。1980年、鹿児島大学大学院法学研究科修了(修論「集会における情報伝達」)。2003年、鹿児島大学大学院人文社会科学研究科修了(修論「日本の工業化過程についての職人史的分析」)。以降も研究を継続中で、現在は特に「大正デモクラシー」に心ひかれている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。