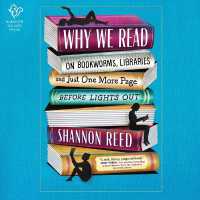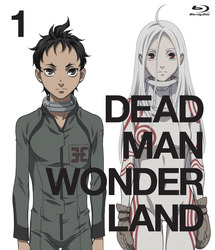内容説明
承久の乱に勝利した鎌倉幕府が京都六波羅に設置した、「幕府の出先として朝廷を監視し、武家の安全のためにしっかりがんばる」機関とされてきた、六波羅探題。いったい何をしていたのか?わかりやすくまとめてみた!六波羅探題がテーマの、初の一般書。通説と異論。研究史を詳細に跡づけるとその存在と役割が見えてくる。
目次
第1章 戦前の六波羅探題の研究(京畿および関西の諸政をすべ、兵馬のことを総掌する―和田英松の研究;六波羅は京都の重鎮―三浦周行の研究 ほか)
第2章 戦後の六波羅探題の研究―通説の成立(訴訟制度上に占める六波羅探題の地位―佐藤進一の研究;六波羅探題の成立と構造―上横手雅敬の研究 ほか)
第3章 通説に対する異論の展開―本格的研究の開始(「六波羅‐両使制」―外岡慎一郎の研究;公武交渉における六波羅探題の役割―森茂暁の研究 ほか)
第4章 その他の六波羅探題研究(在京人と篝屋番役―五味克夫の研究;在京人とその位置―五味文彦の研究 ほか)
著者等紹介
久保田和彦[クボタカズヒコ]
1955年、神奈川県生まれ。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。学習院大学大学院人文科学研究科修士課程修了、同大学院博士課程で単位取得。専攻は日本中世史(荘園、国衙領、国司制度、北条氏、六波羅探題など)。神奈川県立高等学校教諭を経て、鶴見大学文学部文化財学科、日本大学文理学部史学科非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
サケ太
22
六波羅探題という、鎌倉時代に存在した特異な機関という印象があった。あまり研究されていなかった戦前から、現代に至るまでの変遷がまとめられている。個人的には、六波羅探題も『守護』としての役目を持っていたことや、鎌倉幕府の時代において西国を監視する役割を担っていたというのは、あまり六波羅探題を知らなかった身としては目から鱗。室町時代に、おける鎌倉府と同じ役割であり、室町幕府の前身といえる存在ということか、と思った。2020/02/18
浅香山三郎
17
六波羅探題研究のハンドブックといふべきもの。近年の研究状況を解説する真面目な本だが、かういふマイナーな(とも思へる)テーマでの解説書に、どのくらい需要があるのだらうかと余計な心配もしてしまつた。2020/01/25
六点
13
「中世史ブーム」だとしか言えない現状だからこそ、出版されたとしか思えない、手堅すぎて「学問の本道此処に在り」と吠えたくなる本である。義務教育を終えた人間なら、誰もが知っている、鎌倉幕府の出先機関「六波羅探題」が日本史学においてどのように研究されてきたか。素人が通覧するには骨が折れる、基本書でありながら稀覯書になっている本もあるのだ。況や門外漢がそれを追うのは難事である。戦前から、戦後、そして現在に至るまでの研究史を丹念且つ明快に追っている。行間から伺える、先学に対する深い敬意と学問への情熱に震えた。2020/03/22
feodor
7
研究者ではないとそこまで知らなくてもなあ……と思いつつ読むが、六波羅探題って何なのか、ということをどの時期にはどの程度掘り下げてきたのかを知ることにはなる。そして、鎌倉時代の朝廷研究と共に、六波羅探題って単に幕府の京都出張所ではなくて、それなりに朝廷との関係もあったのではないの、ということだとか、あるいは得宗専制の頂点に達する北条貞宗の時はまた例外じゃないの、ということだとかが明らかになってくるのは、とてもおもしろい。2020/05/02
あまたあるほし
4
こういう本をどんどん出して欲しい。2020/02/24