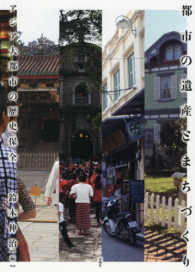出版社内容情報
真の主役は戦車でなく、砲兵だった!? 気鋭の戦史研究家が、新視点から描いた画期的な陸戦論!■真の主役は戦車でなく、砲兵だった!?
気鋭の戦史研究家が、新視点から描いた画期的な陸戦論!
世界大戦というと、戦車や戦闘機、またそれを用いた電撃戦などが有名です。
しかし、二つの大戦の勝敗を決定づけたのはそれら花形兵器ではなく、地味な存在の砲兵でした。
砲兵戦術の視点から、二つの大戦で、戦い方がどのように変わっていったかを解説していきます。
陸戦戦術の流れが分かり、その中で“変わらなかった戦術の本質が何か”が見えてきます。
■内容の抜粋
●砲兵戦術の進化で大戦は動いた
第一次世界大戦のカンブレの戦いでは、戦車が初めて大量投入され、部分的に塹壕線を打ち破りました。
そのため、戦車の集中投入による突破作戦の可能性を拓いた戦闘として有名です。
しかしこれまでイギリス軍が一的に陣地を占領しても、すぐに後方のドイツ軍の逆襲により奪い返されていました。
カンブレの戦いで占領した陣地を奪い返されなかったのは、イギリス軍砲兵が縦深制圧を行いドイツ軍に反撃を許さなかったためでした。
●「機動戦」vs.「火力主義」
機動戦というとドイツの電撃戦が有名ですが、当時、各国が「機動戦」理論を研究し、採用していました。
しかし実際に大戦が始まると、スマートな「機動戦」は打ち棄てられ、陰惨な「火力主義」へと回帰していきました。
●戦車は、ほぼ戦車以外に撃破された!?
いかに装甲と機動性をもつ戦車も、単独で動けばすぐに砲兵の餌食となる脆弱な存在であり、「火力の一部」にしか過ぎません。
撃破された戦車は8~9割が戦車以外によるものでした(北アフリカ戦線を除く)。
敵戦車を撃破するのは、戦車の役割ではなく、砲兵の役割でした。
ティーガー戦車とM4シャーマン戦車でどちらが強いかという問題は、さほど大きな意味をもたなかったのです。
第1章 第一次世界大戦と砲兵
ライフル銃の登場により、19世紀後半から砲兵の地位は低迷し、損害覚悟で近距離・直接射撃を行わざるをえませんでした。
第一次世界大戦の中で、膠着した塹壕戦を打ち破るために、砲兵戦術はどのような試行錯誤を重ね、どう発達していったかを検証します。
第2章 退化していった戦間期の砲兵
進化を遂げ、第一次世界大戦では大きな役割を果たした砲兵でしたが、大戦が終わると軽視されていきます。
その要因は何か、新しい戦術の潮流とは何だったのかを紹介していきます。
第3章 イギリス軍の砲兵ドクトリン
第二次世界大戦中、イギリス軍は「機動戦」を棄てて「火力主義」に回帰していきます。
なぜイギリスがそのような方向転換を行ったかを分析していきます。
第4章 ソ連軍の虚構と実際
ソ連軍は砲兵(火力主義)を重視した組織でした。
独ソ戦を通じて、ドイツ軍とソ連軍が「機動戦」と「火力主義」をそれぞれどのように実現していたか、実際の戦闘がどう行われていたかを分析していきます。
第5章 独自の進化を遂げたアメリカ砲兵
第一次世界大戦後、戦術的には遅れをとりながらも、機械化が進んでいたアメリカ軍は独自の進化を遂げていきました。
しかし第二次世界大戦に突入すると、アメリカ軍も戦術の本質を見直さざるをえない状況にぶち当たります。その過程を紹介していきます。
古峰文三[コミネブンゾウ]
著・文・その他
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
harass
yamatoshiuruhashi
スー
六点
りー
-

- 電子書籍
- WWM -極悪レスラー、ママになる- …
-

- 電子書籍
- わたしの飼育係くん 分冊版(3)