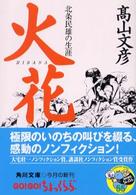内容説明
この本は、兄とわたしをめぐる物語である。有事においては歯牙にもかけられない、平時においても世界を変える力などないと思われている存在の中にこそ、ささやかで強靭な力が潜んでいるのではないかということが、この物語を書きながらわたしが意識を強めたことである。
目次
第1章 沈黙と声(たたかわないこと、しっそうすること;三月下旬 午前二時半に走り出す;現代の野蛮人・カタリナの構え;黙〓と叫び1;黙〓と叫び2)
第2章 蜜柑のはしり(ズレと折り合い;いくつかの死と;いくつもの死と;対面とリモート;夏みかんのしっそう;贈与のレッスン)
第3章 世界を撹乱する、世界を構築する(ボランティアのはじまり;満月とブルーインパルス、あるいはわたしたちのマツリについて;路線図の撹乱1;路線図の撹乱2;トレイン、トレイン)
第4章 急ぎすぎた抱擁(父とヤギさん;眠る父;転倒の先;失踪/疾走;旋回としっそう;燕の神話)
最終章 春と修羅(物語の終わりに)
著者等紹介
猪瀬浩平[イノセコウヘイ]
1978年埼玉県生まれ。明治学院大学教養教育センター教授。専門は文化人類学、ボランティア学。1999年の開園以来、見沼田んぼ福祉農園の活動に巻き込まれ、様々な役割を背負いながら今に至る(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アキ
108
兄は何度も失踪した。大声をあげて突然疾走し、どこか遠くでよく警察に保護された。財布も携帯も持たないままに。知的障害者と社会から烙印を押された兄は父と共に社会を変えようと働きかけた。本書は弟である人類学者の著者から見た兄の姿であり、しっそうとは兄の失踪と疾走のあわいで、そこから想起される様々な思想である。レヴィ=ストロース「野生の思考」をはじめとして、村上春樹や宮沢賢治、金子光晴などの小説家の引用もあり、兄とともに考え、障害の文化人類学をテーマとしてきた著者のエッセイ風の物語でした。2024/03/19
けんとまん1007
51
一人の人、人間としての存在。その間に横たわるものは、一体、何だろう。人と人の繋がりについて、希薄化が言われ、一方で狭い範囲での濃密さが言われる。また、その重要が喧伝あれることもある。ただ、立ち止まって考えてみると、深さが感じられないことが多い。そこには、時間の流れ、しかも、今この瞬間という指向性があるのではと思う。まずは、時間軸の置き方を見つめ直すことから始める。タイトルの「しっそう」が失踪であり、疾走であるということが、広がりを見出すことになる。2024/04/19
@nk
51
例えば電車の中で、誰かに付き添われながら大声をあげて動き回る人を見かける。その車輌に3歳になった息子と私が居合わせる。息子が目を見張りながら私に「あの人はどうしたの?」と問いかけたとき、「 “障害者” という人たちがいてね」という説明から始めてしまっていたように思う。本書を読むまでは。/著者の兄は唐突に走り出していなくなる。その「しっそう」にまつわる出来事や出逢い、考察が綴られていた。コロナ禍が浮き彫りにしたもの。多様性は必ずしも受け入れるだけのものではないこと。そしてあらゆる事件や運動についてなど、⇒2024/04/11
ほう
26
NHK「こころの時代」の放送を見て人類学者の著者を知った。自閉症である兄との関わり、そこから繋がった人びととの関わりが記されている。失踪または疾走という観点から起こるエピソード、考えかたの捉えかたなどが胸に響く。「コロナウイルス感染によって逼迫する医療や介護の現場において、障害のある人やその家族のほうが我慢を強いられる事が圧倒的に多かった」など、随所にとても大事な事が書かれているように思う。時間を置いてまた読んでみたい。2025/10/25
チェアー
8
この本は、人類学の本とは到底思えない。というか、そんなくくりは必要ない。ただ失踪する人がいて、それを見ていると言う本だ。そして、自分はなぜ疾走しないのかと問い返す本だ。 2024/01/23