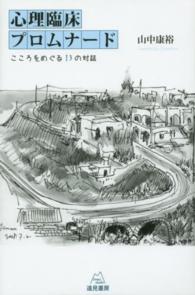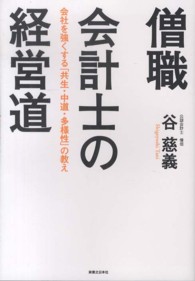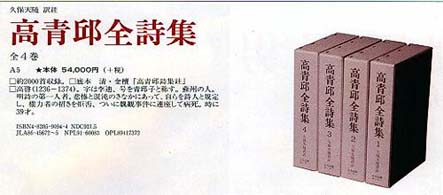内容説明
「見た目の強さ」より「コツ・カン」の働く心身を。元ラグビー日本代表の著者が、自身の実感と科学的知見をもとに「学び・スポーツ」の未来を拓く、救いの書。
目次
第1章 脱・筋トレ宣言
第2章 筋トレを警戒する人たち
第3章 豊かな感覚世界をめざして
第4章 「引退後」を言葉にする
第5章 感覚世界の見取り図―始原身体知
第6章 感覚世界の見取り図―形態化身体知・洗練化身体知
終章 脱・筋トレ思考
著者等紹介
平尾剛[ヒラオツヨシ]
1975年大阪府出身。神戸親和女子大学発達教育学部ジュニアスポーツ教育学科教授。同志社大学、三菱自動車工業京都、神戸製鋼コベルコスティーラーズに所属し、1999年第4回ラグビーW杯日本代表に選出。2007年に現役を引退。度重なる怪我がきっかけとなって研究を始める。専門はスポーツ教育学、身体論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Sakie
19
ラグビー選手として活躍した後、指導者としてのキャリアにある著者が、どのように反筋トレの考え方と折り合うのかと興味を持った。過剰な筋トレの弊害は『感覚世界の矮小化』であり『身体知の空虚化』であるとの見解に立ちつつ、筋トレをしても感受性を衰えさせない努力や方法が重要としている。天才と呼ばれる選手は筋トレの弊害を察してトレーニングを適度ですませるというが、どうしても筋トレを免れない環境にある子供や選手には、楽しむこと、感覚を確かめながら動くことを提言している。脱「筋トレ」ではなく脱「筋トレ重視思考」なのだ。2021/05/07
ta_chanko
11
目指すべきは、うまく立ち行かない場面に遭遇したときにも怯まず・焦らず・自身を失わず・辛抱強く・腰を据えて取り組むことのできる「しなやかなからだ」をつくりあげていくこと。特定の状況下で短期的・数値的に測られる力ではなく、いついかなる状況においても発揮できるような力を身につけていくことが大切。安易な筋トレは部分的な筋力の向上にはつながるかもしれないが、全体のつながりや柔軟性を損なう危険性がある。また筋トレ思考は経済の成長思考とも共通するところがあり、近視眼的な成果主義に陥りやすい。2021/08/20
太郎丸
5
自分はアスレチック施設で働いているが、筋肉がついている人でも、いかにも身体を重そうに使いながらクライミングをしている人をよく見かける。各パーツの重さで全体のバランスが崩れているような動きをしている。逆に鍛えた腕をうまく使っている人もいる。この書籍では筋トレが必ずしも運動能力貢献に向上しない問題について感覚的な視野から分析しているが、「ついた筋肉」と「つけた筋肉」が違う、という意見は腑に落ちる。実動作に結びつき、行う中で自然に必要な筋肉もついていくようなトレーニングが今求められているのだと思う2020/08/05
太郎丸
5
自分はアスレチック施設で働いているが、筋肉がついている人でも、いかにも重そうにクライミングをしている人をよく見かける。鍛えた腕をうまく使っている、というより重さで全体のバランスが崩れているような動きをしている。逆に鍛えた腕をうまく使っている人もいる。この書籍では筋トレが必ずしも運動能力貢献に向上しない問題について感覚的な視野から分析しているが、「ついた筋肉」と「つけた筋肉」が違う、という意見は腑に落ちる。実動作に結びつき、行う中で自然に必要な筋肉もついていくようなトレーニングが今求められているのだと思う2020/08/05
Akiro OUED
5
勝利至上主義に毒されたスポーツに対置する健全なスポーツは、選手の肉体の充実に由来する?こう言い切るのは筋トレ思考だね。 やってることが、『うまく立ち行かない』とき、脱・筋トレ思考的にもがき続けるためには、強靭な心があってこそ可能。心トレもお忘れなく。「心の言語化」が、本書の肝。2019/11/26