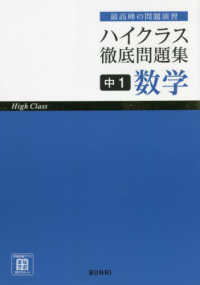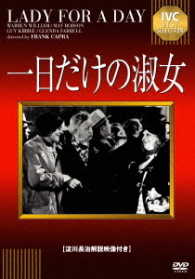内容説明
現代人よ、もっと、もっと、もっと寝よう!人気鍼灸師が実践する現代版・養生法。
目次
第1章 健康法の棚卸し
第2章 「ハレ」と「ラク」が招く不健康
第3章 「寝る・食う・動く」の時間を決める
第4章 「寝る・食う・動く」の質を高める
第5章 風邪は引き始めに東洋医学で治す
第6章 生活そのものが養生になる
著者等紹介
若林理砂[ワカバヤシリサ]
臨床家・鍼灸師。1976年生まれ。高校卒業後に鍼灸免許を取得。早稲田大学第二文学部卒(思想宗教系専修)。2004年に東京・目黒にアシル治療室を開院。現在、新規患者の受け付けができないほどの人気治療室となっている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アキ
39
鍼灸師の養生論で、東洋医学の推奨。まずは「寝る」を固定し遅くとも0時までには寝て7時間程度の睡眠をとる。次に「食う」を固定し、食事の半分が野菜、4分の1をタンパク質、4分の1が炭水化物にする。最後に「動く」を固定する。ラジオ体操と通勤時の歩行でいいと。不調の時は10時までに早く寝る。日常の不調のほぼ9割は風邪で、ひきはじめに葛根湯っていいかも。当たり前のことをなかなかできにくくなっている現代。今日は早く寝よう。2018/11/07
出世八五郎
25
愚図愚図して直ぐに行動に移せない。何日も先延ばしにする習慣は病気である!とネット掲示板などで言われていたと思う。しかし、本書では愚図愚図して直ぐ動けないのは体質の問題のような書かれ方をしていた。著者の他の作品でも似たような記述があり、心・精神的なものは東洋医学でも治療できそうだ。アメリカ精神医学会のDSMを妄信して何でも病気にして西洋薬を飲むよりはまずは東洋医学を頼った方がいいじゃないかと思った。黄帝内径・素問(こうていだいけいそもん)こんな本があるんだな。東洋医学は凄い。本書のレビューとならなく御免。2024/11/05
チャー
18
鍼灸師の著者が健康に過ごすための大切なことを紹介した本。特別なサプリや薬、あるいは健康グッズに頼らずに、日常生活の基本的な部分を見直し整えることの重要性が綴られている。健康の定義のハードルがかなり高く、なかなかこの域まで達しないという指摘には同意。特に特別なことをしなかった最近の長寿の方々を考えると、割と普通の食事で長寿は可能という点は確かにと思う。不健康なことをしなければ健康であるという指摘はその通りと感じた。腸内細菌の多様性がアレルギーを抑えることもあるとのこと。体調を知り都度調整することが肝要。2024/08/10
青木 蓮友
15
冷湿タイプでした。なんだか刺さるという表現がぴったりな言葉の数々、心の底から噴き出す物凄いエネルギー。何度もハッとしました。それでいて言ってることはいたってシンプルで、どこまでもが当たり前。正直勇気が要ったんじゃないかなと思いましたよ、それくらいの平凡レベルでした。この内容と「死ぬ」という言葉をあえて入れたタイトルのギャップに、言葉にできない勢いが感じられ。とてもいい本だと思いました。「なにも足さない。なにも引かない。」これ、名言ですよね。生き方にも通ずる深さ、というか東洋医学、陰陽、八卦、易経万歳です。2018/12/27
アカツキ
14
死んでしまうまでの間、年をとっても結構楽しんで生きられる良い塩梅のココロとカラダを作りましょうという東洋医学の養生本。ゲームの世界のたとえ話がわかりやすかった。RPGで宿屋に泊まれば全回復するのと同じように睡眠が一番体調を整えるのに良く、食事はHP回復、運動や趣味等がMP回復。生活に取り入れやすいように読者に寄り添う形で書かれているけれど、できるかというと自信が…。最近は眠る時間に気をつけるようになってきたけど、著者の基準では不合格だろうな。2025/04/06
-
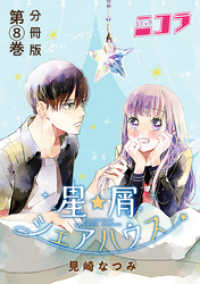
- 電子書籍
- 星屑シェアハウス 分冊版第8巻 コミッ…