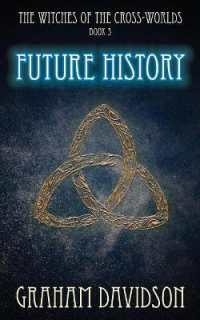内容説明
領収書の廃棄・改ざん、商品の横流し、ニセの銀行口座への振込、ペーパー会社への売上、架空循環取引…etc.会計思考で全てお見通し!!本書は資産の流用の事例を取り上げ、それが組織の経営、特に財務面に与える影響を会計思考で見える化したものです。同時にその背景を探り、再発防止の仕組みを提案しています。
目次
第1章 資産の窃盗・横領のカテゴリー(帳簿と通帳の残高が違う;破棄された領収書 ほか)
第2章 資産の不正使用のカテゴリー(資産・設備の業務外使用;消えた有価証券 ほか)
第3章 経費の水増しのカテゴリー(禁止されたバック・マージンの授受;キック・バックの要求 ほか)
第4章 不正な財務報告のカテゴリー(商品在庫情報の改ざん;商品の含み損の隠ぺい ほか)
著者等紹介
土田義憲[ツチダヨシノリ]
作家、公認会計士。新日本監査法人シニアパートナー、国際教養大学客員教授を経て、現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Mik.Vicky
5
まあ初歩的な話が多かった。発覚後は結構寛大な措置が多かったけど、もっと厳しい処分にした方が良かったのでは。 娘が、「不正取引の発見を防止する本」ってタイトルかと勘違いしたといっていて、爆笑した。 私も社内では結構責任ある立場いいるので、私もだが部下がこう言ったことをしないように警戒しておかなければならない。2022/10/03
ぺす
0
権限(現金決済・発注・入出庫指示・請求書発行)を特定の人物に集中させすぎていること、待遇に不満を持っていること、過剰なインセンティブ制度などの環境が、不正取引を生み出す土壌となっています。 参考になる書籍だと思うんですが、表紙でだいぶ損しているんじゃないでしょうかね?2023/03/22
-
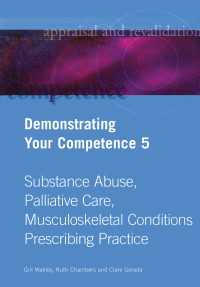
- 洋書電子書籍
- Demonstrating Your …