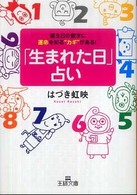出版社内容情報
初級者から上級者まで幅広い読者のニーズに応え、この1冊に論点を完全に網羅。不確定概念を多数の裁決・裁判例・判決から読み解く。みなし贈与課税に関する完全解説版!!
初級者から上級者まで幅広い読者のニーズに応え、この1冊に論点を完全に網羅!!
不確定概念を多数の裁決・裁判例・判決から読み解く、税理士・会計士必読図書!!
〇はじめに
近年、みなし贈与分野は資産税分野でも脚光を浴びてきています。それにはいくつか理由があります。主としてみなし贈与が絡む取引が特殊領域ではなくなってきていること、事業承継対策においてポイントとなる自己株式の取得等や組織再編成、事業承継に係る資本政策スキームにおいてみなし贈与について特に初期における税額シミュレーションの重大性が広く認識されてきていること、などが考えられます。
みなし贈与は、類書にあるような計算事例だけでも、後付けで税務申告書を記載したり、その他税務諸手続きをすることは確かに可能です。しかし、組織再編成や事業承継といったコンサルティング分野の領域においては、場合によっては税額が非常に多額に及ぶこともあるため、初期の段階で税額シミュレーションをし、クライアントに周知徹底すべき事項であり、そういった点において今後ますます重要性は高まると考えられます。
従来の類書であれば、「(相続税法上の)みなし贈与」「贈与の一形態」といったように補足的に記載されていることが常で、真正面から取り上げられることはありませんでした。
本書はみなし贈与だけに焦点をあて、完全解説と銘打ち、みなし贈与分野の「基礎」についてはこの一冊で事足りるような構成となっています。
本書の大きな特徴は、みなし贈与の分野だけに限定したことからと、以下の点に集約されます。
・みなし贈与分野における初級者から上級者まで幅広い読者のニーズにこたえるものを意識したこと
・論点は最新の税制改正まで(本書では平成30年度税制改正における無対価組織再編成の取扱いがあたります)網羅性を重視し、類書では軽く扱っている記載についても誌面の許す限り詳細な解説を加えていること
・裁決・裁判例・判例についても網羅性を重視し、できるだけ実務上のヒントになるような汎用性のあるものを厳選して掲載したこと
・みなし贈与は「不知・うっかり」で失念することが大半であり、苦手意識を持っている実務家が多いため表現はできるだけ平易に、また、随所に非常に簡単な「よくある」事例を組み込み、具体的な取引をイメージしていただけるようにしたこと、一方で実務上稀な事 例についても上級者向けに汎用性のある取引のみを厳選し掲載したこと
はじめに
第1章 みなし贈与の基本的な考え方
1 総則税法第7条の意義と考え方
(1)個本的な考え方
(2)過去の採決・裁判例・判例にみる基本的な考え方
(3)第三者M&Aにみなし贈与は発動されるか
(4)10年以上前に流行った租税回避スキームとみなし贈与の関係
2 相続税法第9条の意義と考え方
(1)基本的な考え方
3 みなし贈与の伝統的議論
4 民法上の贈与と税法上のみなし贈与
(1)民法上の贈与
(2)税法上の贈与
? 税法上の贈与とは
? 贈与の時期
(3)相続税の税務調査における具体的事例
第2章 みなし贈与が適用されるケース?株主間贈与以外?
1 保険料を親が負担した保険契約の受取人が子供の場合
(1)昭和58年9月国税庁事務連絡「保険料負担者の判定について」
(2)連年贈与
2 生命保険金等
(1)基本的な考え方
(2)人身傷害補償保険の保険金を取得した場合の課税関係
(3)損害保険契約
(4)生命保険契約の転換時の贈与課税
? 原則
? 貸付金が転換時に生産された場合
(5)相続税申告にあたってのかんぽ生命保険会社への照会
3 定期金
(1)典型事例
4 土地等を時価よりも安く購入した場合
(1)基本的な考え方
(2)混合贈与との差異
(3)典型事例
(4)相続時精算課税制度が絡んだケース(平成19年8月23日判決をベースに)
? 贈与税(みなし贈与)
? 所得税(譲渡所得)
? 相続税(相続時精算課税)
(5)相続税法第7条の「時価」と「著しく低い対価」について
? 「時価」について
? 「著しく低い」の考え方について
(6)債務弁済資力喪失者への定額譲渡
5 債務免除等
(1)基本的な考え方
(2)典型事例
6 利息の設定をせずにした金銭の貸し借り等
(1)基本的な考え方
(2)典型事例
(3)税務調査での基本的な考え方と同通達の趣旨
(4)代償分割に伴う負債の利子払いの課税関係
7 登記に係るみなし贈与
(1)基本的な考え方
(2)典型事例
(3)遺産分割のやり直しと贈与税
(4)遺言とい異なる資産分割
8 共有持ち分の放棄
(1)典型事例
(2)遺産分割と共有持ち分の放棄
9 財産の名義変更等があった場合
(1)基本的な考え方
(2)典型事例(贈与税の課税対象とならない場合)
(3)強制執行を免れるために財産の名義変更をした場合
(4)なぜ、預貯金については相基通9?9の適用はないのか?
10 その他の事例
(1)借地権の贈与
? 典型事例
? 使用貸借に係る土地の上にある建物等の贈与
? 平成19年8月23日東京地裁との関係性
? 使用貸借の場合のみなし贈与発動リスク
? 借地権の取引が同族関係者となされた場合
(2)信託
(3)夫婦間の財産移転
? 贈与税が生じるケース
? 典型事例
(4)ジョイント・テナンシー
(5)結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度
第3章 株主間贈与
1 総説
(1)簡便的なまとめ
(2)個別論点
? 著しく低い価額で同族会社に資産を譲渡した場合の贈与税
? 同族会社の増資があった場合の贈与税
? 同族法人の新株発行に伴う失権株に係る新株不発行
2 金銭出資
(1)パターン別株主間贈与
? 有利発行により個人⇒株主間贈与
? 有利発行による個人⇒法人への株主間贈与
? 有利発行による法人⇒法人への株主間贈与
? 高額引受けによる個人⇒個人への株主間贈与
? 高額引受けによる法人⇒個人への株主間贈与
? 法人株主による高額引受けによる有価証券の取得
(2)属人株による利益移転
3 自己株式の取得
(1)個人⇒個人間の税務上の評価額の適正時価
(2)個人⇒法人間の税務上評価額の適正時価
? 個人⇒法人間の非上場株式の移転についての税務上の適正評価額
? 個人⇒法人間の低額譲渡
(3)「著しく低い価額」の明文規定
(4)法人⇒個人間の税務上評価額の適正時価
(5)法人⇒法人間の税務上評価額の適正時価
(6)パターン別株主間贈与
? 低額譲渡による個人⇒個人への株主間贈与
? 低額取得による法人⇒個人への株主間贈与
? 低額取得による法人⇒法人への株主間贈与
? 高額取得による個人⇒個人への株主間贈与
? 高額譲渡による個人⇒法人への株主間贈与
? 高額譲渡による法人⇒法人への株主間贈与
4 組織再編成
(1)パターン別株主間贈与
? 被合併法人の株主による区分
? 合併法人の株主による区分
(2)債務超過再編にける無対価組織再編成
? 平成30年度税制改正前の債務超過再編における無対価組織再編成の留意事項
(3)平成30年度税制改正における無対価組織再編成の要件
(4)債務超過法人の組織再編成における株主間贈与
? 非適格合併の場合(合併法人の株主:個人、被合併法人の株主:個人)
? 適格合併の場合(合併法人の株主:個人、被合併法人の株主:個人)
? 合併の直前に合併法人が被合併法人の発行済株式の全部を取得する場合
? 平成29年度税制改正における適格分割型分割+清算スキームに係る贈与税
第4章 その他のみなし贈与が生じる可能性がある諸論点
(1)民法組合、LLC、投資事業有限責任組合(LPS)等
(2)中小企業のMEBOの手法におけるみなし贈与発動可能性
(3)医療法人の事業承継
(4)事業承継ストックオプションのみなし贈与
(5)失権株
(6)事業承継税制におけるみなし贈与の発動可能性
(7)中小企業M&Aの場合の税理士事務所の事業承継
(8)自己株式取得スキーム
(9)社長借入金を整理する場合の諸論点に係るみなし贈与
? 債務免除による方法
? 遺言書又は死因贈与契約で「債権放棄」を行う場合
? DESによる方法
(10)相続税法第66条第4項
(11)民法特例とみなし贈与
第5章 みなし贈与に係る裁決・裁判例・判例
1.相続税法第7条関係裁決・裁判例・判例
2.相続税法第8条関係裁決・裁判例・判決
3.相続税法第9条関係裁決・裁判例・判決
【補足資料】みなし贈与に関する国税庁情報
伊藤 俊一[イトウ シュンイチ]
著・文・その他
内容説明
初級者から上級者まで幅広い読者のニーズに応え、この1冊に論点を完全網羅!!不確定概念を多数の裁決・裁判例・判例から読み解く!!
目次
第1章 みなし贈与の基本的な考え方(相続税法第7条の意義と考え方;相続税法第9条の意義と考え方 ほか)
第2章 みなし贈与が適用されるケース―株主間贈与以外(保険料を親が負担した保険契約の受取人が子供の場合;生命保険金等 ほか)
第3章 株主間贈与(総説;金銭出資 ほか)
第4章 その他のみなし贈与が生じる可能性がある諸論点(民法組合、LLP、投資事業有限責任組合(LPS)等
中小企業のMEBOの手法におけるみなし贈与発動可能性 ほか)
第5章 みなし贈与に係る裁決・裁判例・判例(相続税法第7条関係裁決・裁判例・判例;相続税法第8条関係裁決・裁判例・判決 ほか)
著者等紹介
伊藤俊一[イトウシュンイチ]
1978年(昭和53年)愛知県生まれ。愛知県立旭丘高校卒業後、慶應義塾大学文学部入学。その後、身内の相続問題に直面し、一念奮起し税理士を志す。税理士試験5科目試験合格。一橋大学大学院国際企業戦略研究科経営法務専攻修士課程修了、現在、同博士課程(専攻:租税法、研究分野:エンプティ・ボーディング)在学中。慶應義塾大学「租税に関する訴訟の補佐人制度大学院特設講座」修了。都内コンサルティング会社にて某メガバンク本店案件に係る、事業再生、事業承継、資本政策、相続税等のあらゆる税分野を担当。同業士業からの御相談件数は10,000件(平成30年10月1日現在、公認会計士・弁護士・司法書士等からの御相談業務)を超えており、豊富な経験と実績を有する。所属学会:税務会計研究学会所属、信託法学会所属(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。