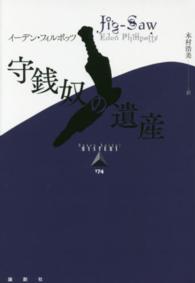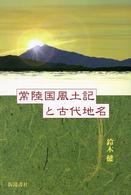出版社内容情報
「アクティブ・ラーニング=主体的・対話的で深い学び」を理論と現場視点で解き明かす。学習指導要領が変わり、センター試験が変わろうとしている今、学校では、また教師たちは、生徒にどのような力を付けることが大切なのかと模索し始めています。
「生きる力」と表現される求められている力はどのようなカリキュラムを作れば、生徒たちに身につけてもらえるのだろうか。熱意ある教師ほど、迷い、試行錯誤を繰り返しています。
そうした具体的な疑問に答える手引き書であり、アクティブ・ラーニングを理論的に理解するための解説書です。
はじめに
第1部 「アクティブ・ラーニング=主体的・対話的で深い学び」と「探究活動」??「理論」を学ぶ
1 「新しい学び」の時代
2 今、必要とされる「新しい学力」
3 「アクティブ・ラーニング=主体的・対話的で深い学び」とは何か?
4 「学校外の学び」から考える
5 教師に求められる2つの力
6 「探究活動」とは何か?
7 「探究活動」の2つのカリキュラムモデル
8 「探究」カリキュラムの3段階モデル
9 「調べ学習」と探究活動をつなげる
第2部 カリキュラムを「デザイン」する??学びの「作り方」
1 一貫したカリキュラムを作ろう
コラム 学習指導要領改訂と「カリキュラム・マネジメント」
2 「学習目標」から考える??カリキュラム作りの手順
3 「工学」と「羅生門」??授業を作る視点
コラム 「教育」は後からやって来る
4 「成果物」と「能力」??カリキュラムを作る視点
5 「学習者」を評価する
6 「授業」を評価する
7 カリキュラム作りの実際(1)??事前調査
8 カリキュラム作りの実際(2)??事業運営に向けて
コラム 「オルタナティブ教育」
第3部 さまざまな「学習方法」を学ぶ??学びの「原理」と「手法」
1 ファシリテーション??学びの「原理」?
2 ロールプレイ??学びの「原理」?
コラム 「役になりきる」ことの学び
3 ゲーム??学びの「原理」?
コラム 「ゲーム」で授業を作る
4 アイスブレイク??グループ活動に向けた手法?
5 協調学習??グループ活動に向けた手法?
6 コミュニケーション・トレーニング??「社会性」を育てる手法
7 ディベート??「論理的な思考力」を鍛える
コラム 机の上のディベート
8 レポート・ライティング??「書き方」を学ぶ手法
コラム 「文章チュータリング」とは何か
9 情報を整理する方法??「アイデア」を生み出す手法
10 「仮説」作りの方法(1)??アイデアを形にするサポート
11 「仮説」作りの方法(2)??検証に向けたサポート
ふろく 探究活動を「つながり」のなかで作る??「連携」の実務を知る
1 学校が「連携」をするとき
2 どうやって「連携」する?
3 連携「体制」をどう作るか??連携の机に着くまで
4 「連携」の実際と諸問題
おわりに
がもう りょうた[ガモウ リョウタ]
立命館大学文学部を卒業後、京都大学大学院教育学研究科へ進学。研究と並行して、京都市内の高等学校で教壇に立つ。現代文をはじめとした国語科の授業を担当、入試指導や進路相談も行いつつ、課外活動として「探究活動」を若手教員とともに実施。その後、学校の学科再編に伴う「総合的な学習の時間」再編ワーキンググループに参加し、カリキュラム分析・開発を行う。カリキュラム骨子完成後は企画部主任のアドバイザーとして授業運営を補佐。学校現場での活動を評価され、2014年度、京都大学総合博物館初の「教育学」をテーマにした展覧会特別展「学びの海への船出」を担当、さらに2015年度「京のイルカと学びのドラマ」プロジェクト&学修支援総括・企画構成を行い、京都を中心とした学校との連携事業、京都大学での初年次授業・教職授業、総合博物館でのワークショップ、「探究活動」発表大会などを企画・運営した。専門は、学修支援の総合的な臨床研究、「学校外の学び」についての現代史研究。現在は、関西大学・大阪薬科大学などで非常勤講師をしながら立命館大学生存学研究センター客員研究
員。京都大学大学院教育学研究科博士後期課程在籍。
目次
第1部 「アクティブ・ラーニング=主体的・対話的で深い学び」と「探究活動」―「理論」を学ぶ(「新しい学び」の時代;今、必要とされる「新しい学力」 ほか)
第2部 カリキュラムを「デザイン」する―学びの「作り方」(一貫したカリキュラムを作ろう;「学習目標」から考える―カリキュラム作りの手順 ほか)
第3部 さまざまな「学習方法」を学ぶ―学びの「原理」と「手法」(ファシリテーション―学びの「原理」1;ロールプレイ―学びの「原理」2 ほか)
ふろく 探究活動を「つながり」のなかで作る―「連携」の実務を知る(学校が「連携」をするとき;どうやって「連携」する? ほか)
著者等紹介
がもうりょうた[ガモウリョウタ]
立命館大学文学部を卒業後、京都大学大学院教育学研究科へ進学。専門は学修支援、「学校外の学び」についての現代史研究。現在は関西大学などで非常勤講師をしながら立命館大学生存学研究センター客員研究員。京都大学大学院教育学研究科博士後期課程在籍(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。