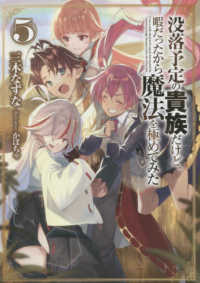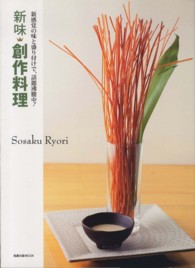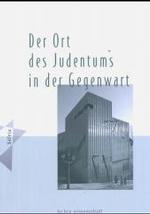出版社内容情報
勝手連型の「財産」作りとWin-Win型の「財産」作り、地主には有利とはいえなかった選挙区割、立候補制ではない選挙など、現…1890(明治23)年の第一回総選挙で当選して衆議院議員になった者の中には、実際には15円以上の国税納入資格を満たしていなかった者がかなりいた。彼らは、支持者たちの作った「財産」によって、資格を得たのである。中江兆民・植木枝盛・河野広中・尾崎行雄・島田三郎など、自由民権運動の著名な活動家をはじめとして、数十人は、そのような者であったといえる。本書は「初期議会=地主議会」という通説のもとで解明されずにきた「財産」作りの実態や選挙戦の有り様を、長年にわたる膨大な史料の博捜により解明、貴重な史実を明らかにする。
まえがき
序 章 「衆議院議員=ほとんど地主」をめぐって
第一章 「財産」はこうして作られた―被選人資格のタテマエと実態―
第二章 第一回総選挙はどのように行われたか
第三章 第一回総選挙の当選人
第四章 第一回総選挙の選挙戦
あとがきにかえて
稲田 雅洋[イナダ マサヒロ]
著・文・その他
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kenitirokikuti
8
講座派の理屈「自由民権運動は、明治維新によって成立した絶対主義政府に対するブルジョワ民主主義革命であった。ゆえに明治憲法の発布と帝国議会の成立はその敗北の確定である。初期衆議院議員=ほとんど地主である」。この見解は中公の色川大吉『日本の歴史21―近代国家の出発』(1966)にも踏襲されている。近年「地主」説は消えたが、第一回衆議院議員についての研究は今も存在しない。記述を欠く県史もあるほど。第一回当選者の2/3は府県議や郡長である。民権運動は革命勢力ではないので、敗北も失敗もなく、地方でふつうに継続した。2018/12/15
あまたあるほし
4
信念のこもった名著。第一回の選挙が、いかに間違って定義され続けてきたのかがわかる。地主ばかりの議会という認識は、なんとなく、うっすらと頭に残っていたから余計に。やはり、選挙には物語がある。研究書は10000円以上で売るのはおかしい、と安めの設定をした著者の心意気に拍手である。2018/12/06
パトラッシュ
3
政治分析の本は退屈なのが普通だが、これはドラマになるくらい面白い。日本でも上に政策あれば下に対策ありで、政府の都合のいい議会にしてたまるかという民権運動家とその支援者が立候補資格を作るため財産を分与する話など信じられなかったし、歴史書に書かれていた「初の衆院議員は地主出身者ばかり」という定説を呆気なく覆している。「したい人よりさせたい人に」というスローガンは、第一回選挙から実現できていたわけだ。病に倒れながら大量の史料にあたり、徹底的に調べ抜いた著者に脱帽するしかない。これこそ歴史家のあるべき姿であろう。2019/07/21
takao
1
ふむ2025/06/27
中将(予備役)
1
初期議会=地主議会との説を否定すべく、第一回衆議院選挙の納税額の実態、選挙制度、当選者集計、情勢や選挙運動を研究した意欲作。研究書でありながら読んでいて面白い内容だった。特に制度の範囲で立候補資格をごまかす財産作りと、区割りや非立候補制の制度解説は興味深い。従来説の有名な論文は貴族院についてはもっと初歩的な誤りをしているようだし、講座派の影響も初めて知った。2022/03/06