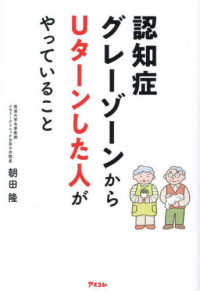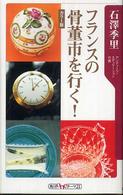目次
1 1945‐1954 シュルレアリスムと多様性―敗戦後の美術状況
2 1955‐1959 前衛―具体、九州派、アンフォルメル
3 1960‐1963 反芸術―ネオ・ダダとハイレッド・センター
4 1964‐1979 還元主義と多様性―もの派、概念派、美共闘
5 1980‐1984 脱前衛―80年代アヴァンギャルドと日本グラフィック展
6 1985‐1994 再現芸術―関西ニューウェーブから東京シミュレーショニズムへ
7 1995‐2009 マニエリスムと多様性―悪い場所、スーパーフラット、マイクロポップ
8 2010‐2014 搾取前衛―フクシマ前後の表現主義と反表現主義
著者等紹介
中ザワヒデキ[ナカザワヒデキ]
美術家。1963年新潟生まれ。千葉大学医学部在学中の1983年よりアーティスト活動開始(第一期:アクリル画)。卒業後眼科医となるも1990年、絵筆をコンピューターのマウスに持ち替えイラストレーターに転身(第二期:バカCG)。1997年、CGの画素を文字等の記号に置き換え純粋美術家に転身(第三期:方法絵画)。2006年、方法主義では禁じていた色彩を再び使用(第四期:本格絵画、新・方法、第四表現主義)。宣言「方法主義宣言」「新・方法主義宣言」(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
煮干し
1
これまでかすかにしか知らなかった(知ったかぶりをしていた)日本の芸術をおおまかに俯瞰することができました。個人的には戦争や政治や安保などの影響が薄くなりはじめたあたりの芸術に興味を強くもちました。2017/03/21
の
1
敗戦~現代に至る日本現代美術の歴史書。現代美術史は「前衛」→「反芸術」→「多様性」のサイクルを約30年周期で繰り返しているといった「循環史観」を基に、70年間で2回転のサイクルと現在の前衛を解説。シュルレアリスム、アンフォルメル、ネオダダ、と過去の芸術シーンのアヴァンギャルドな試みに度肝を抜かれつつ、こうした下地の(破壊の)上の村上隆やカオスラウンジの前衛性を理解できた。前衛も反芸術もやがて一般化し、多様化して古典と同じようなボーダーレスな存在として扱われる。これがスーパーフラットか。2015/03/14
puapua
0
日本の現代美術史を網羅的に見るには良い一冊。モノクロながら作品の写真も数多く載せられている。書き物としてはやや淡白な印象を受けた。2021/07/23
石橋 こわし
0
戦後の日本美術の歴史を網羅した本は、意外と無いから、とても面白かったけど、せめてカラーだったらな… でも、楽しかった。2018/01/22
-
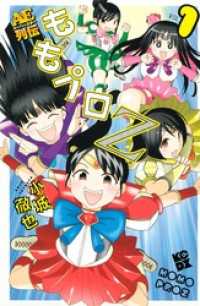
- 電子書籍
- ももプロZ AEスーパースター列伝(1)