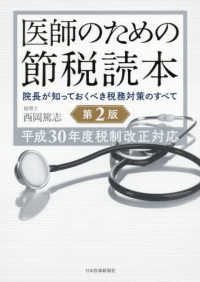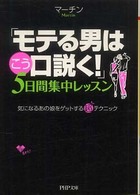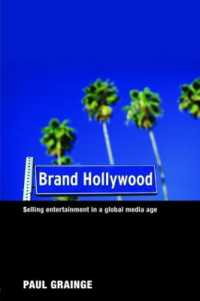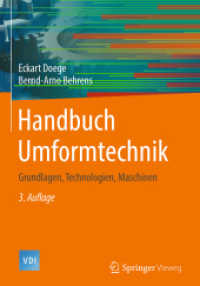内容説明
「恐るべき出来事」が呼び起こす場所と記憶の文化。
目次
序章 場所と怪異の民俗学
第1部 心霊スポット考(心霊スポットとは何か;真相としての仮構;モノと感覚)
第2部 心霊スポットの諸相(将門塚のこと―将門はどう祟るのか;八王子城跡のこと―怪異の変容;おむつ塚のこと―或いはたくさんのお菊)
終章 誰がための心霊スポット
著者等紹介
及川祥平[オイカワショウヘイ]
1983年、北海道生まれ。成城大学文芸学部准教授。博士(文学)。専門は民俗学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。