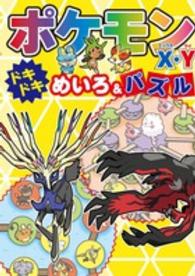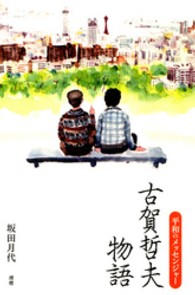内容説明
きみは神になりたいのか?そして、人間は、人文学は、いかに回復可能なのか?われわれは既に「これからの人間」として生きているのに、なぜこれほどまでに現代社会に適応できず、存在することの不安に苦しんでいるのだろう。気鋭の研究者が「他者」と「技術」を批判的媒介として探求する“存在論的メディア論”。
目次
第1章 閉じていく世界(他者;欲望の二重らせん;全体性とメディア;貫通;プンクトゥム;イコンと肖像画;世界のデジタル化;環境化するメディア技術;計数的な自然と存在の地図化;デジタルスティグマジー)
第2章 世俗的な神(メタプログラム的世界観;テクノロジー無謬説とテクノデモクラシー;仮想化批判の仮想性;身体の喪失と残忍さ;個人認証;3Dプリンタから世俗的な神へ;人新世;誰が人新世を見届けるのか;ポストヒューマンの人文学)
第3章 別様の未来(除去可能性ノイズ;存在論的ノイズ;デジタル化される生命観;マイクロバイオームから他者原理へ;脳死者と人間の条件;語り出す石;信頼;メディオーム;バイオアート、木、そして全体性;memento mori)
著者等紹介
吉田健彦[ヨシダタケヒコ]
1973年、東京都に生まれる。東京農工大学非常勤講師、大阪府立大学客員研究員。東京農工大学連合農学研究科農林共生社会科学博士課程修了。博士(農学)。専門は、環境哲学、メディア論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ニッポニテスは中州へ泳ぐ
7
☆=5/5 メディア論であり、技術論でもあり、環境哲学でもある他者論。私たちの周りに常に在り、先行している環境とはつまり他者(ままならないもの=私に対する一種の暴力)であり、私を成り立たせる条件でもあるその他者とつながるために私達は技術を必要とする。その技術の中でも他者との媒介を志向するものは全てメディアと見なし得る。 他者こそを私に先行するものとして分析しているという意味では、永井均哲学を軸にセカイ系の極北へと突き抜けた鈴木康夫の一連の著作と対を為す本とも言えます(ごく個人的な連想ですが)。2022/05/21