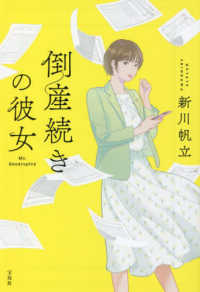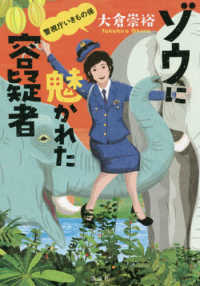内容説明
超出家主義・脱世俗主義。地下鉄サリン事件から20年を経て、今なお増える「オウム信者」。林泰男死刑囚の国選弁護人(宗教面担当)として事件を内側から見た著者が、オウム真理教が今も日本に投げかけている問題の核心に迫る。
目次
プロローグ 地下鉄サリン事件、二十年後の問い
第1章 オウム教団の変貌と事件
第2章 私の見た実行犯たちの実像
第3章 悲しい犯行動機、林泰男の弁護を担当して
第4章 若者を惹きつけた出家制度とヨーガの技法
第5章 殺人を正当化する経典の存在とその誤り
第6章 宗教とは現実である
エピローグ オウム出現の土壌としての日本の戦後
著者等紹介
中島尚志[ナカジマショウシ]
1933年東京生まれ。元判事・弁護士。東京大学経済学部を卒業ののち、同大学院印度哲学科修了。判事を経て、地下鉄サリン事件を契機に95年依願退官。96年四天王寺国際仏教大学教授。2003年退職。97年より国選弁護人として林泰男の一審・二審の弁護を宗教面から担当(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
黒猫
16
地下鉄サリン事件の林泰男の弁護を担当した元国選弁護人の本。一般の方からみたら、オウム真理教寄りの話も多く見られる。しかし、平成が終わる中でなぜオウム真理教が急速に信者を獲得し、殺人を肯定するという教義がどこにあったのかを知らなければ全ては奇特な集団がいたという昔話で終わってしまうだろう。なぜ破防法が適用されなかったのか、内乱罪にあたらなかったのはなぜか?分かりやすく述べられている。林郁夫が殺人を犯しても無期懲役で、誰も死者を出さなかった実行犯が死刑となった違いは何か?地下鉄サリン事件対応に一石を投じる本。2018/08/07
あっきー
12
✴3 麻原はオウム教団が日本を支配することによってフリーメイソンの陰謀から守るため自衛隊内部からのクーデター工作を指示していた、捜索による教団解体に対抗してサリン事件を起こす、三島は楯の會を創設し自衛隊訓練にも参加、左翼学生の内乱危機に血盟団事件をモデルにした奔馬のように切腹事件を起こした、著者は判事を辞めオウムの林泰男の弁護をしていて、本も出版する程仏教に詳しいのは豊穣の海の本多にそっくりだ、オウムと三島は輪廻転生などの考えも似ているし、いよいよフィクションとノンフィクションの区別が判らなくなってきた2019/04/21
トゥクトゥク
4
仕事で読む。どの人物を主軸にして物事を見るかによって、見えてくる世界がまったく違うのは分かる。でもオウム真理教に関しては判断が難しい。著者は麻原の初期の著書を(仏教本として)褒めているが、その理由を読者に納得するようには書いていないから、僕はそれを鵜呑みにする事はできないし、警戒感もあるから読んでいて「オウムに寄り過ぎてないか」と不安にもなった。ただ、悪いのはこの組織だけではないような気は少しする。(当時テレビで見た警察やマスコミの対応などを思い出すと…)2015/02/23
みじんこ
3
林泰男の弁護を担当した著者。林は相当反省しているように見えた。麻原を師と仰いでしまったのが失敗だろう。本書は仏教の話も多いが、殺人を容認するインド後期密教の経典は、当時のインドの修行者たちにも受け入れられていなかったというのは当たり前というか、常識的だったと思う。経済的豊かさに対して精神的豊かさを求める感覚は現代でも理解できるが、そこに付け込んで信者に反社会的活動をさせるのは許されない。著者や吉本隆明は麻原の宗教に対する見解などを一部肯定していたようだが、私としては異常なカルト教団の教祖としか思えない。2015/02/22
大熊真春(OKUMA Masaharu)
2
著者は元判事で、宗教に深い関心を持っていたのだが、地下鉄サリン事件にショックを受けて退官し、のちに実行犯の国選弁護士となった人。 ◆「オウムはなぜ消滅しないのか」について著者が下している結論は「すぐれた正しい宗教だから」である。 ◆著者は宗教というものを信じているようで、麻原の「空中浮揚」や「予知能力」を認めている。 ◆ま、いろんな人がいるんだな、という感じ。 ◆こういう内容(特に宗教的な面)の本を出すのに勇気がいるってことはないのかな、と思う2015/05/15
-
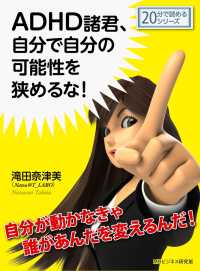
- 電子書籍
- ADHD諸君、自分で自分の可能性を狭め…


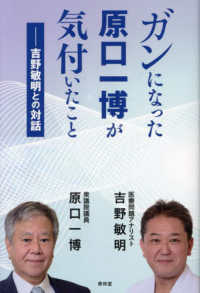
![適用構文の世界言語比較ハンドブック<br>Applicative Constructions in the World's Languages (Comparative Handbooks of Linguistics [CHL] 7) (2024. X, 1090 S. 31 b/w and 10 col. ill., 121 b/w tbl. 240 mm)](../images/goods/ar/work/imgdatak/31107/3110735482.jpg)