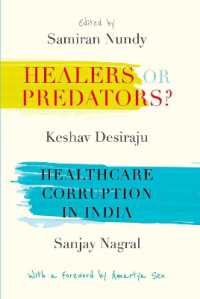内容説明
現代人はつねにネットワークに接続されている。それはなにを意味するのか。二人の哲学者が、記号論という名の古くて新しいプロジェクトをいま再起動する―。先史時代の洞窟壁画から最新の脳科学までを貫き、ヒトと機械のインターフェイス=境界面の本質を明らかにする、スリリングな知的冒険!ゲンロンカフェ発、伝説の白熱講義を完全収録!
目次
講義(記号論と脳科学 2017年2月17日;フロイトへの回帰 2017年5月24日;書き込みの体制2000 2017年11月24日)
補論(4つの追伸 ハイパーコントロール社会について)
著者等紹介
石田英敬[イシダヒデタカ]
1953年千葉生まれ。東京大学教授。東京大学大学院人文科学研究科博士課程退学、パリ第10大学大学院博士課程修了。専門は記号学、メディア論
東浩紀[アズマヒロキ]
1971年東京生まれ。批評家・作家。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了(学術博士)。専門は哲学、表象文化論、情報社会論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ころこ
37
記号を言語の閉じた集合と考えずに、視覚聴覚触覚的なあらゆる断片を記号として広く考えると、記号論がなぜメディア論なのかが理解できます。第2講義のフロイトの議論から非常に示唆を受けました。第1局所論を、分節化され意味として理解される以前に物表象として知覚され、無意識に痕跡を残しながら前意識では語表象となるというプロセスが説明されます。人文的なフロイトではなく、神経学者としての唯物論的で、光学的な隠喩を使った再解釈を可能にしています。睡眠によって注意力が解除されると、この流れが逆に送られるのが夢だといいます。2019/03/03
たばかるB
29
3回にわたる会談をまとめたもの。議論の基盤になる記号論の概要や変容にじっくり時間を割きつつ、現代でのメディアとの関係性、プラクティカルな話題を詰める。どちらの面でも題材が面白く、スピノザ-フロイトの結び付けだとか消費者生産者の意識構造だとか。最後にはうまく石田氏が全講義をまとめていて、これもまた色々例示されていてはあんとなった。2020/03/05
yutaro sata
28
4つの追伸を読み終えて、完走。GAFAというのは図書館事業の延長として考えるべきなのか、面白いなあ。人文知と現在の情報技術を、このように接続出来る、というよりは、接続しなければこれからの社会を批判的に検討していくことが出来ないですよ、というとても力のこもった一冊だった。これから石田さんの本だったり、この本の内容に関係することだったりにいろいろ手を出してみる。2023/06/19
しゅん
21
「記号」の意味を、「現代思想」を現代にアップデートしようとする野心的な試み。「人はみな同じ文字を書いている」という研究にはグッときた。コンピューターと人間が共有している基底として「記号」を考えていく話は政治にも芸術にも音楽にも言語にも記憶にも人間関係にも、要するに人の生活の全てに通じる話だと思う。フロイトの読解も独創的でおもしろい。とても学びがあった。2019/04/07
minochan
17
あらゆる言語の文字に共通のパターンが見られ、それが自然界のものに由来している話には正直めちゃくちゃ興奮した。記号論とテクノロジーの関係にも興味がわいた。0と1に結び付け可能な情報しかないネットばっかやってないで、身体性を伴った感動を求めてもっと街に森に出ようと思った。SNS でよくわからん他人の悪意にさらされるくらいなら、生身の人に会って喋ろうとも。2024/06/19
-
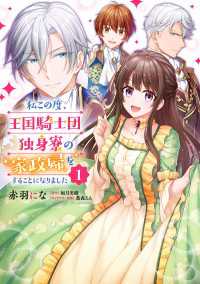
- 電子書籍
- 私この度、王国騎士団独身寮の家政婦をす…
-
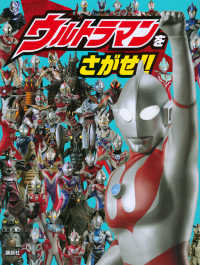
- 和書
- ウルトラマンをさがせ!!