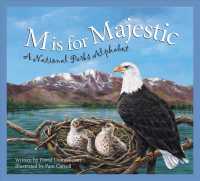内容説明
「ベンダーは図書館のパートナー、システムエンジニアは司書のパートナー」の想いが一冊に。システムエンジニアとして、話題の図書館のユニークな訪問記をまとめた著者の第2弾!
目次
第1章 図書館は誰がつくっているのか(ベンダーは図書館のパートナー:図書館システムの歴史;図書館と出版社をつなぐ:原書房成瀬雅人氏の講演会から ほか)
第2章 SEの図書館見聞録(変わりゆく図書館;まちへの愛をかたちにする ほか)
第3章 事件は図書館現場で起きている(人間関係のスキルをみがく:川合健三氏のクレーム対応セミナー基本編;職員を大事にするスペース:石狩市民図書館 ほか)
第4章 SEからみた可能性(エコノミック・ガーデニング;ビブリオバトル全国大会:生駒市図書館の取組みから ほか)
著者等紹介
高野一枝[タカノカズエ]
大分県生まれ。図書館システムの開発に20年間関わり、現在はライブラリーコーディネーターとして、NECネクサソリューションズ(株)ポータルにて、Webコラム「図書館つれづれ」を執筆中。また在職時から産業カウンセラーやキャリアコンサルタントなどの資格を取得し、若い方へのキャリア支援も(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゆずな
15
元SEが図書館を語る1冊。正直、「システムエンジニア」色はあまりない。SEとして図書館のシステムに関わった女性が、図書館を街の中の重要な位置付けとして捉えた論考といったところ。Webページでの連載をまとめたものとのこと。個人的には子供の頃にたくさん通った佐世保市立図書館が取り上げられていたのが嬉しかった。変わった佐世保市立図書館に是非とも行きたい所だ。2021/09/14
鳩羽
6
図書館システムのSEとして、図書館の中からも外からも関わったことがある筆者が、全国の様々な図書館を訪れて感じた記事をまとめた本。まちづくりの核に据えられることも多くなった図書館だが、箱物、あるいは場所だけあっても駄目で、当たり前だが人の集まりに適した場所とサポート、目的にあったコンテンツがうまく作用した時に、効用が発揮されるのだろうなと思った。いちからグループを立ち上げた方がよい時もあれば、既存のグループを取り込んだ方がよい時もある。図書館はこんなに何でも屋にならないといけないのかなという気もした。2019/02/13
おさと
6
様々な図書館の取り組みが紹介されていて興味深い。図書館の1ユーザーでしかないけれど、今後、何かしら関わっていけたらなあと思う。2018/12/31
月華
4
図書館 新刊コーナーで見かけて借りてみました。システムを作る人と、システムを使う人の齟齬はどこの世界でも同じなんだなと思いました。クレーム対応は学びたいと思いました。図書館は試行錯誤しながら、新しいことを取り入れているんだと思いました。2018/12/17
akiu
4
図書館SEの経験をもとに、今の図書館について語る本。著者の経歴が珍しいので読んでみた。内容は、面白い試みをする図書館や、現場で起きるさまざまな課題、エコノミックガーデニングなどといった新しい施策など、図書館そのものを巡るいろんな事例紹介でした。いずれも興味深く読む。自分の地域以外の図書館ってあまり知らない(知る機会も少ない)ですからねぇ。図書館システムに特化した内容はあまりなかったけど、システムも含めて、どういう図書館を形作っていくかという、大きなデザインみたいなのは、今後大事になってくる気がします。2018/11/08