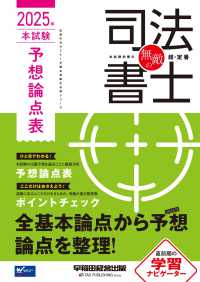出版社内容情報
この小論において試みるのは、日本語という一つの特殊な言語を通じてこの民族の精神的活動の根本的な一面を解釈しようとする精神史的な考察である。(本文5P)
―とにかく我々は問うてみる、「あるということはどういうことであるか。」(本文30P)
ドイツ留学でハイデッガーの『存在と時間』に刺激を受けた和辻が、日本語で存在論的問いをたてるための基礎付けを試みた論文。
国民の精神的特性が言語の構造にあらわれると考える和辻は、まず、日本語に名詞の性や動詞の人称が無いことや、「てにをは」など助詞の多さについて考え、日本語が理論的方面ではなく芸術的方面に発達した言語であると指摘する。
次に「もの」「こと」「ある」「いうこと」という、4つの日常のことばの意味を整理し、輸入された外国語ではなく真に日本語で哲学するための基礎付けを目指した。
【目次】
1 国民的特性としての言語
2 日本語の特質
3 日本語と哲学の問題
4 「こと」の意義
5 「いうこと」の意義
6 言う者は誰であるか
7 「ある」の意義
1 国民的特性としての言語
2 日本語の特質
3 日本語と哲学の問題
4 「こと」の意義
5 「いうこと」の意義
6 言う者は誰であるか
7 「ある」の意義
和辻哲郎[ワツジテツロウ]
和辻哲郎(わつじ・てつろう 1889?1960)
兵庫県神崎郡砥堀村仁豊野(現在の兵庫県姫路市)に生まれる。倫理学者、哲学者。著書に『古寺巡礼』『風土』『倫理学』『日本精神史研究』など。
内容説明
ハイデッガーの『存在と時間』に刺激を受けた和辻が、ドイツ留学から帰国後に取り組んだ論文。「もの」「こと」「ある」「いうこと」など、日常のことばの意味を整理し、輸入された外国語ではなく真に日本語で哲学するための基礎付けを目指した。
目次
1 国民的特性としての言語
2 日本語の特質
3 日本語と哲学の問題
4 「こと」の意義
5 「いうこと」の意義
6 言う者は誰であるか
7 「ある」の意義
著者等紹介
和辻哲郎[ワツジテツロウ]
1889‐1960。兵庫県神崎郡砥堀村仁豊野(現在の姫路市仁豊野)に生まれる。倫理学者、哲学者(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
うえ
式
edamamekirai
ふみ乃や文屋
doctor bessy
-
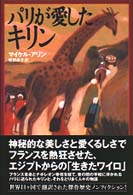
- 和書
- パリが愛したキリン