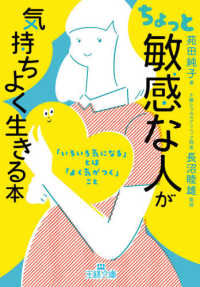内容説明
ジョルジュ・バタイユによるヒロシマ論。ヒロシマをさらに大きな濁流へ開かせながら、バタイユは、戦争回避の普遍経済学を模索する。原爆投下から一年半たたない1947年初頭に『クリティック』誌に発表された“夜をさまよう人”バタイユの意欲的論文。
著者等紹介
バタイユ,ジョルジュ[バタイユ,ジョルジュ] [Bataille,Georges]
1897‐1962。二〇世紀フランスの総合的な思想家。小説、詩も手がける。生と死の狭間の感覚的かつ意識的体験に人間の至高の可能性を見出そうとした。その視点から、エロティシズム、芸術、宗教、経済など、人文系の多様な分野で尖鋭な議論を展開した。キリスト教神秘主義、シュルレアリスム、ニーチェ哲学などに思想の影響源がある
酒井健[サカイタケシ]
1954年東京生まれ。現在、法政大学文学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
284
ジョン・ハーシーの『ヒロシマ』が「ニューヨーカー」に掲載されたのが、原爆投下の翌年8月。そして、これを読んだ強い衝撃の元に本論考が書かれたのは'47年の初頭であったようだ。バタイユはこれを自己が内的に思索すべきものとして、そしてまた人類史上未曾有の問題として受け止めている。『ヒロシマ』には谷本牧師の言葉として語られているが、他の人々の証言でも等しく語られるのが、「ピカ」の直後は自分たちの近辺だけが空襲の直撃を受けたと認識したものだ。やがて、それはヒロシマ全市に及んでいたことを彼らは知るのだが。⇒2015/12/26
nobi
78
原爆投下はボルドーでもブレーメンでもなく極東のヒロシマで起きたこと。それは多くの西欧人と同様バタイユにとっても「感性よりも思考のほうに多くを提供」する事実だった。その精神的隔たりをJ.ハーシーの「ヒロシマ」は一気に埋め合わせる。原爆の齎すおぞましい風景の中「この不幸を生きよう」とする人々がいた。その《至高の感性》の衝撃。その≪瞬間≫の輝き。それでもバタイユは人為的な不幸と恐怖の減少を希い夢物語のような普遍経済学を提示する。原子エネルギーを生産エネルギーに転化すれば衣食足りて戦争のない世界を実現しうる、と。2017/08/11
兎乃
40
『トルーマンの様な人間の態度は、ある種のおぞましい知性を順調に機能させ、原爆の威力は恐怖も嫌悪も与えず歴史の一コマに収まってしまう。』バタイユはトールマンの傍観者的態度を批判し、同時に憎悪あるいは嫌悪の感情的態度を排する。不幸の本質、ヒトが持つ多面体の一構成要素 その不幸の無意味さを正視する。終戦から70年、メディアは次へ 次へ そして次の話題へと移る。戦争を広島を長崎を知らない私は どうすればいいのか、この一冊はその手掛かりになった。わずか62頁、深く深遠な読書を経験した。2015/08/17
かおりんご
31
立花隆さんの本で、バタイユがヒロシマについて語っていたことを知り、本書を手にする。ハーシーが書いた「ヒロシマ」という本に対する書評なので、そちらも読まなきゃちょっと分かりづらいのかも。ページ数の割に内容が濃く、正直、私には難しく感じた。2022/01/21
双海(ふたみ)
25
ジョルジュ・バタイユによるヒロシマ論。分量としては非常に短いものです。原爆投下から1年半たたない1947年初頭に『クリティック』誌に発表されたとのことです。やっぱりバタイユは私にとって難しくて、もう。なんとなくわかるような気もするけれど、それ以上先に進むこと能はず・・・。2015/05/28
-

- 和書
- 次世代美容医療×アート
-

- CD
- 航空自衛隊/軍歌名曲集