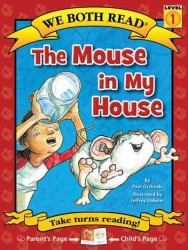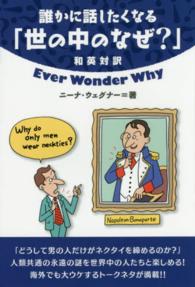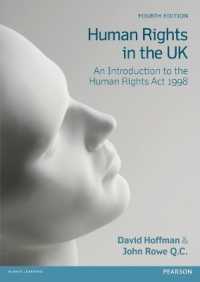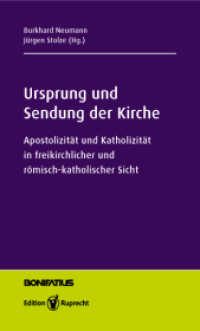目次
第1部 近世肥後農村の諸相(肥後藩領における農村構造の問題―名子の自立過程と質地作徳地主の形成;肥後近世山間地の土地集積―中村手永椎持村黒田家の場合;名子百姓の自立過程について―薩摩のケゴコとの対比;質地・譲地地主の土地集積―大津手永農村を中心として;寸志寸考―上益城郡矢部手永について;近世内牧の火災と手永役人の功労と意義;惣庄屋と光永円右衛門 ほか)
第2部 近世肥後の農民と民間宗教(藩体制下における地方神官の専業化―肥後国阿蘇末社社家男成氏の場合;近世の祭礼・諸興行と民衆―上益城郡矢部手永を中心として;肥後城北地方における庚申信仰遺跡について;〈参考〉肥後周辺における庚申塔の地域性と時代相;神社経営と氏子村々―小一領社と矢部手永の場合;近世のかくれ念仏考―九州南部諸藩の場合;近世肥後と薩摩の真宗三業惑乱事件―『肥後国諸記』を原典として)
第3部 肥後と薩摩の国境―長島をめぐって(肥・薩国境地における社寺堂塔―天草・長島の近世以降の信仰;肥薩の接地「獅子島」の史的考察;〈史料紹介〉慶長五年から寛永九年に至る薩摩国への逃亡(走り)百姓の史料について
御所浦島 海人集団の遺跡を歩く
鎌倉期天草領長島山門野の地頭職相論者の出自について
出水郡東町(長島)山門野の祭礼・信仰行事小考
倒幕期における天領天草と薩摩藩の動向)
付篇 近代干拓農村と農民―郡築小作争議(郡築小作争議の史的位置付けと小作農民の動向―郡築小作争議の研究・その一;小作農民の離村について―郡築小作争議の研究・その二)