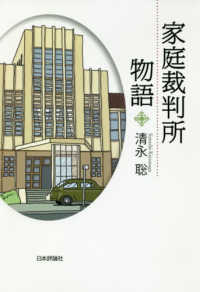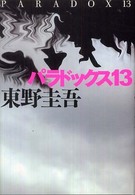内容説明
自殺願望と同性愛、言語像の革命と宗教思想の転回…知の巨人を育んだ精神のるつぼに近代日本の青春を読む。
目次
第1章 藤無染と折口信夫(柳田國男以前の折口;出会った日;関係の謎 ほか)
第2章 詩と学の出自(自殺未遂;捨て子幻想;「乞丐相」と「幼き春」 ほか)
第3章 漂泊のアナーキスト(境としての沖縄と神;柳田と折口;島嶼から見た日本 ほか)
著者等紹介
富岡多惠子[トミオカタエコ]
1935年、大阪市生まれ。詩人・小説家。評論に、『中勘助の恋』(1993、読売文学賞)、『釋迢空ノート』(2000、毎日出版文化賞)、『西鶴の感情』(2004、大佛次郎賞)などがある
安藤礼二[アンドウレイジ]
1967年、東京生まれ。文芸批評家。多摩美術大学美術学部芸術学科准教授。著書に、『神々の闘争 折口信夫論』(2004、群像新人文学賞、芸術選奨新人賞受賞)、『光の曼陀羅―日本文学論』(2008、大江健三郎賞、伊藤整文学賞受賞)などがある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
浅香山三郎
11
『釋迢空ノート』を前に読んだので、折口信夫の青春時代については、知識ゼロではなかつたが、安藤礼二さんの仕事によつて、折口の全体像の深掘りができてゐてとても面白い。近代の本願寺の改革派、宗教的一元論、言語学、、短歌論、景教、『死者の書』と、釋迢空=折口信夫の学問と文学両方の様々な著作が、ちやんと意味あるものとして理解できると、やつと折口がその同時代の潮流からだう影響を受けてゐたかが見へてくる。まれびとなどへの視線と、大阪といふ土地柄、文楽や歌舞伎の確かな批評も、文楽やひと連なりのものだといふのも納得できた。2017/10/21
うえ
2
「出雲は、明治期に国家神道の流れから切られる…そこら辺りに、折口信夫にとっての神道というものの核心がある…折口には、出雲とは何かという問いに、もう一度自分なりの解答を与えようとする…藤無染と一緒に暮らし始めたのが明治三八年、別れたのが三九年で、そのすぐあとに神風会に入っています…この仏教から神道への揺れが、いままで誰もわからなかった…神風会の記録を見て驚いたのは、「折口信夫君だけがあまりの熱心さに國學院大學の試験を無視して来ている」などと記され…一所懸命に寄付をしている。しかも友人たちを巻き込みながら。」2024/09/08
NагΑ Насy
2
『折口信夫芸能論集』を読んで、その巻末の編者解説の文体がしっくりときた。しばらくして、『霊獣』を読む。藤無染という謎の僧侶が、折口信夫と空海を結ぶこの論考の空白のコアだった。柳田國男に師事する前の10代から20代の形成期の折口信夫についての研究は資料も少ないことからか、内側からは見えにくい事柄なのかあまり語られて来なかったという。富岡多恵子は文学的な興味から『釋迢空ノート』として、戒名のような法名を筆名としていた文学者としての折口信夫の陰を辿る。二人の対話から折口信夫の人の闇が浮かび上がる。2013/09/03
koji
1
非常に満足した安藤礼二さんの「場所と産霊」を読んだのが3年前。「釈超空ノート」の富岡多惠子さんとの対談でしたので期待したのですが、一寸感じが違いました。折口信夫の青春は、私の興味の範囲とずれていました。やっぱり折口信夫の著作(死者の書等)をしっかり読むことから始めたいと思います。2013/11/09