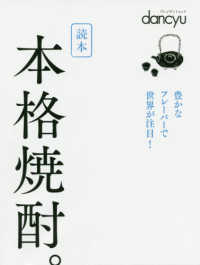内容説明
叛乱の世紀が到来した。『叛乱論』『結社と技術』が、60年安保と「68年革命」のふたつの闘争のあいだを往還しながら切り拓いた大衆叛乱の地平。両書を合本・増補改訂して復刊、21世紀の現在、資本主義を終わらせ、世界各地の民衆叛乱に日本でも呼応するべく新たに煽動する。
目次
第1部 叛乱論(叛乱論;叛乱と政治の形成;戦後政治過程の終焉;戦後政治思想の退廃;付・安保闘争におけ共産主義者同盟―党内闘争のための総括 ほか)
第2部 結社と技術(結社と技術―叛乱の組織問題;主体性の死と再生―自分は誰なのか;大衆にたいしてストイックな“党”―レーニンの結社;ブランキスト百年―私のブランキ;欺瞞的で自由なゲリラ―戦後のあとの時代における政治と生の世界 ほか)
著者等紹介
長崎浩[ナガサキヒロシ]
評論家。1937年生まれ。東京大学理学部卒業、同大学院数物系中退。63‐70年、東京大学物性研究所助手。以後、東北大学医学部、東京都老人総合研究所、東北文化学園大学に勤務。第一次共産主義者同盟(ブント)で活動、東大全共闘運動に助手共闘として参加(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
uehara
0
再読。近代世界への叛乱をまずそれ自体の内部をアジテーターと大衆の相克(一人の叛乱者の内部に)として描く。 『結社と技術』の諸論考に軸を置けば、現実に存在する「私」と、抽象化され「市民」「労働者」等に規定された「我々」の葛藤関係に「政治」の端緒があるとして、その葛藤を排したところに近代テクノクラート的な、「参加」と操作の政治がある。叛乱はまずそれに抗する行為であり、「政治」の葛藤を露呈すると同時に、先述近代政治と異なる均衡状態を志向する、それも葛藤状態たる「政治」のヘゲモニーをよびよせる。2025/03/17
-

- 電子書籍
- 異世界転生したら、推しの敵役のメイドに…
-
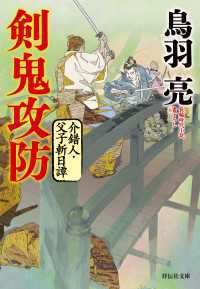
- 電子書籍
- 剣鬼攻防 介錯人・父子斬日譚〈四〉 祥…