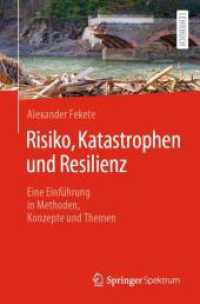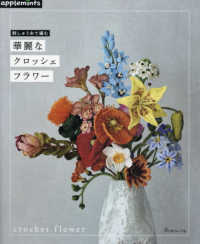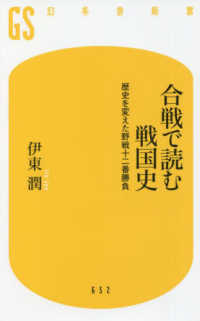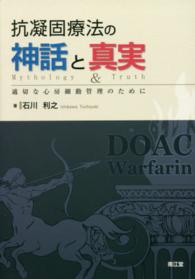内容説明
「日本で唯一のマルクス主義への殉教」「老人の美しい死」―本書旧版の出版と、その翌年の著者夫妻の「死出の旅路」の衝撃。その一方で、人民戦線事件、満鉄調査部、『資本論』出版の舞台裏などのあからさまな記述。「『プロレタリアート独裁』と『暴力革命』とに死ぬまで固執」しながら、ペーソスとユーモアに溢れる文体で、自らの人生を飄々と振り返る。1983年の青土社版に単行本未収録原稿を追補。旧版から40年、待望の復刊。老マルクス研究者の遺言。
目次
第1部 戦前・戦中篇(ごく簡単な履歴書;第一高等学校文科甲類;東京帝国大学文学部;東京帝国大学経済学部;不屈の闘士西田信春のこと ほか)
第2部 戦後篇(『資本論』との再会;九州大学まで;九州大学教養部―社会主義協会草創のころ;九州大学から法政大学へ;『資本論辞典』(青木書店版) ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まこみや
49
再読。一度目(青土社版)は“悲劇”として読んだ。「老マルクス学者夫妻の死出の旅路」という惹句と岩波版『資本論』翻訳における向坂逸郎との確執や不当な措置に強く刻印されていたから。しかし今回は、プロレタリアート独裁と暴力革命とを一対のものとする、机上マルキストの人生を“喜劇”として受け止めた。ソ連の崩壊は既に遠く、共産主義を標榜する中国や北朝鮮の、自由を圧殺する独裁政治を目の当たりにするにつけ。だが、資本主義の混迷はますます深く、マルクスが提起した貧富の格差の問題の出口は一向に見えてこないままである。2024/07/23
チェアー
9
なんて面白い文章なんだろうと思う。 筆者はマルクスの書いたこと、言ったことを一言一言自分の中に浸透させていくことが楽しかったのだ。そして、その核心を他人に伝えたいと思ってきたのだ。 彼はマルクスを離れる。マルクスを離れれば、彼にはもう何も残っていない。あるのは荒涼たる現実だ。あきらめとほんの少しの安堵があったのではないか。 2023/06/17
sober
5
マルクス経済学者の岡崎次郎による回想録である。呉智英氏のコラムで興味を持ち、読んでみた。岩波刊の資本論は現在でも向坂逸郎訳とされているが、岡崎がほぼ単独で全訳したことを暴露している。本書は前半と後半でかなりカラーが異なる。告発は後半に詳述されている。「下訳とは何だ!」という言辞に岡崎の無念が端的に示されている。後に新訳を作成しようとしたところ、周囲の協力者へ隠然たる圧力をかけたり、出版社に対して激越な抗議文を送ったりしたとされる向坂の横暴ぶりのエピソードの披瀝もあり、ゴシップ的面白さもある(続)2024/02/01
こけこ
4
マルクス研究の第一人者、岡崎次郎氏。資本論の翻訳者だし哲学的でつまらない本なんだろうと読み始めたら大間違い。人間として味のある面白い人なんだなと思った。背景を知ったうえで、改めて岡崎氏の資本論を読んでみようかな。2023/11/24
けっと
4
『資本論』を3回も翻訳した「マルクス研究者」の自伝です。さぞお堅い人なのだろうと思いきや、遊びに勤しみ、満鉄調査部の仕事をサボっていた話を自虐的に書いており、イメージとのギャップに少し笑いました。一方で岩波文庫版『資本論』の実質的翻訳者であるにもかかわらず「下訳」扱いとされて揉めた話や、新訳に協力している大学院生が大御所から「商売がたきになるからやめろ」と脅された話といった業界の裏も包み隠さず暴露しており、筆者の恨みの深さが滲み出ています。当時のエリート文化の雰囲気や内情を知ることができる興味深い本です。2023/10/14