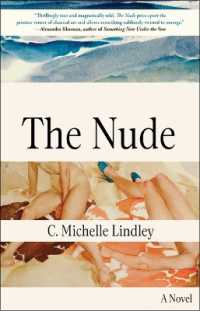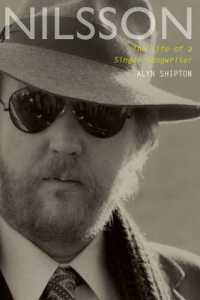出版社内容情報
エコノミックアニマル、小市民、カネが全ての時代。閉塞感漂う二一世紀社会の端緒は七〇年代後半にあったのだ。若者が若者の体温を持っていた七〇年代。その時代の光と影を記す。
目次
座談会 平熱が高かった70年代、そしていま(中山千夏;北村肇;雨宮処凛;平井玄)
1970 阿久悠、社会現象を創った男「歌は世につれ」ではなく「世が俺の歌につれ」たのだ
1970 田中美津と榎美沙子 ウーマン・リブが担った矛盾とはざまを今も凝視する
1970 検定官を萎縮させた家永三郎 三二年の教科書訴訟
1970 現代人の「まつり」に爆発させた岡本太郎の意志と野望
1970 ちばてつや「あしたのジョー」が渡った一九七〇年という橋
1970/1971 三島由紀夫と高橋和巳 学ぶべきものはすべてこの二人に学んだ
1971 ニクソンショックがドルの大幅下落とマネー経済病を生んだ
1971 日活ロマンポルノ 日本映画低迷期に吹いた新しい風
1971 『二十歳の原点』と高野悦子が残した激動の日々の記憶〔ほか〕
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かふ
17
映画『狼をさがして』を観てそういえば積読状態だった、この本があった、と読んだ。週刊誌編集なので、各年(1970~1979)の話題の20のトピックで、芸能文化から社会的事件まで。全体として総括したというより個々の時代のカラフルさを感傷的に懐かしんでしまう雰囲気になる。なんだろう80年代(10歳下の自分はこの世代だ)はTVの影響が大きくなるのだが、まだTV以前の媒体がいろいろあったのだ。80年代は総TVっ子という感じ。今はネットがあるから、70年代に近いのかも(引き込まなければ、いろいろなものが並んでいる)。2021/04/12
元気伊勢子
5
私は、昭和の最後の方の生まれで昭和の時代に関心がある。現在の「消費社会」が誕生したのはこの頃だったか!など、様々な事柄が少しだが繋がっていった。どう生きるか真剣に考え、休みの日の必ずどこかは、読書、思索の時間に充てることから始めよう。2023/01/14
竹薮みさえ
1
同世代の筆者たちの書くものを、卒業文集を読むような感じで読んだ。単純だった社会のレイヤーが一気に多層化した時代なんだなとあらためて確認した。70年代に若者だった人たち(50年代生まれ)の経験した変化の量はものすごい。政治/経済だけに集中した団塊世代のあとの複雑なレイヤーを呼吸して、なおかつ旧来のライフスタイルも知っているものたちの責任は大きいとこれを読んで実感した。 2013/01/17
まんだよつお
1
ぼく自身にとっての70年代は、中学生から社会人になるまでの疾風怒濤の10年間で、「人生に大切なすべてのことはこの10年間に学んだ」と言っても過言ではありません。本書の執筆者が持っている、過去があって現在がある、という視点にブレはなく、70年代を今も日々の暮らしや戦いの根っことしている彼らの文章からは、学ぶべきことが多いと思います。70年代にあって、「身の回り1メートルのことにしか関心のない」人々があふれる現代日本にないものは、つまるところ個人と他者の関係、「連帯感」の有無につきるのだと思う次第です。 2012/11/12
ぐだぐだ
0
たぶん。冷戦って構造下での思想の対立。その熱。それが政治、経済、文芸、人権問題を沸騰させた。熱に浮かされるのが若者たる所以ってか。過激な思想が行きついた先には、なんにもなかったみたいだね。2017/02/11
-
- 洋書
- The Nude