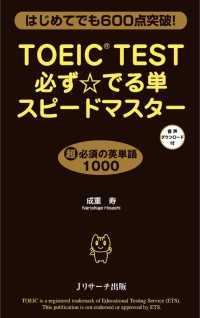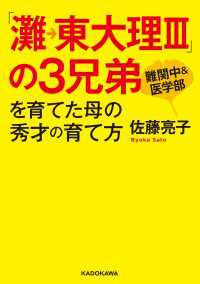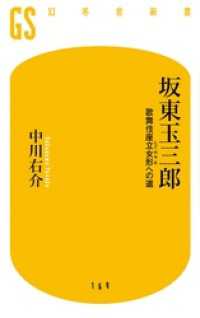内容説明
1926年、印刷会社の歴史的な労働争議に参加し、解雇され、失業した著者が、自らの経験を題材に書き上げたプロレタリア文学の記念碑的作品。労働者のギリギリの闘いと最底辺の街の記憶が、80年の時を超えて生々しく甦る。平井玄による必読の解説「21世紀の太陽のない街へ」を収録。
著者等紹介
徳永直[トクナガスナオ]
1899年‐1958年。プロレタリア作家。小学校卒業前から、印刷工・文選工など職を転々とした。その後勤めた熊本煙草専売局の仲間の影響で文学・労働運動に身を投じ、1920年に熊本印刷労働組合創立に参加。22年山川均を頼って上京。博文館印刷所(後の共同印刷)に植字工として勤務。26年、共同印刷争議に敗れ、同僚1700人とともに解雇される。29年この時の体験をもとにした長編「太陽のない街」を雑誌『戦旗』に連載。労働者出身のプロレタリア作家として支持を得た。弾圧下の37年には時代の圧力に屈して『太陽のない街』の絶版宣言を行なったこともある。病死。享年59
平井玄[ヒライゲン]
1952年、東京生まれ。音楽、思想、社会等の領域を独自の視角と文体で論じる。早稲田大学文学部抹籍。現在、横浜国立大学教育人間科学部非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。