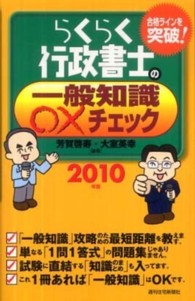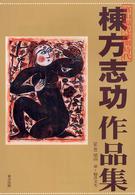出版社内容情報
●養育に関わる全ての人のための入門書
●虐待に象徴される家族の解体をいかに超えるか。いまこそ家族・個人・社会の「養育力」が問われている。
●ファミリーソーシャルワーカーの制度が二〇〇四年度から全児童福祉施設に施行された。民間児童養護施設「光の子どもの家」が長年にわたり取りくんできた家族関係の現場から、理論と実践の重要な参照枠を提示。
●目次 ファミリーソーシャルワーカーとは何か/「社会的養護」とは何か~民間児童養護施設と「法」との関わり/「養育の社会化」をめぐって/家族と「家族の原型」/ファミリーソーシャルワーカーの仕事/「光の子どもの家」の家族関係への取りくみ/児童相談所と児童養護施設のあいだ/真実告知をめぐって~「イノセンス」の解体/ネグレクトと成長障害《コラム》「光の子どもの家」のマザーたち/家族の再統合/「後保護」の長い道を伴走して/出発のためのジャンプ台としての家族~親を「見切ること」《コラム》 ワーカーへのことづて
【BOOK著者紹介】
1939年、秋田県羽後町生まれ。青山学院大学物理教室助手、婦人保護施設「いずみ寮」、児童養護施設「城山学園」「愛泉寮」を経て、1985年、児童養護施設「光の子どもの家」を設立、施設長を務める。聖学院大学・足利短期大学・日本社会事業大学講師。日本地域看護学会会員。
内容説明
“養育”活動の原点をえがく。
目次
「社会的養護」とは何か(民間児童養護施設と「法」との関わり;「養育の社会化」をめぐって)
家族と「家族の原型」―「解体」する家族像のなかで
ファミリーソーシャルワーカーの仕事―児童養護施設と「家族との関わり」の原則
「光の子どもの家」の家族関係への取り組み―「家族的処遇」と「家族との関係の保障」
児童相談所と児童養護施設のあいだ―子ども受け入れの姿勢について
真実告知をめぐって―「イノセンス」の解体
ネグレクトと成長障害―家庭引きとりの困難さをめぐって
家族の再統合(親の願い、子どもの願い、そして…;「後保護」の長い道を伴走して)
出発のためのジャンプ台としての家族―親を「見切ること」について