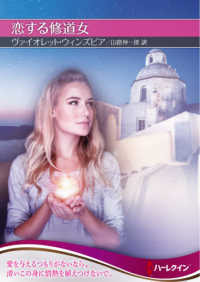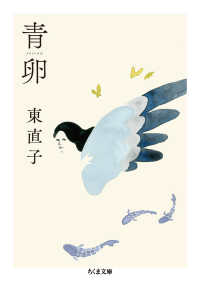出版社内容情報
人文科学の諸分野を専攻する気鋭の研究者たちが集い、現代の人間経験に切実にふくまれる問題群の具体(たとえば高齢者の住宅環境、食事介助など)から、他者・行為・物・環境などの諸言説を根底から問い直し、人間科学の再構築をめざして、執筆と横断的な討論を重ねた共同論作。
川野 健治(1962年生まれ。国立精神・神経センター精神保健研究所心理研究室室長、発達心理学)/圓岡 偉男(1964年生まれ。早稲田大学人間科学部講師、理論社会学)/余語 琢磨(自治医科大学看護短期大学専任講師、文化人類学)/太田 俊二(1967年生まれ。早稲田大学人間科学部助教授、環境生態学)/木戸 功(1968年生まれ。早稲田大学人間科学部講師、家族社会学)/橘 弘志(1965年生まれ。千葉大学工学部助手、建築計画学)/原 知章(1970年生まれ。大分県立芸術文化短期大学国際文化学科専任講師、文化人類学)/三嶋 博之(1968年生まれ。福井大学教育地域科学部助教授、生態心理学)
「人間科学の比重が、言語、意味、現象から、物、行為、身体、システムへ移行しつつある。…こうした人間科学の動向には、以下のような特色がある。行為は局所においてみずからを形成すること、つまりそこでの知識は自己領域化すること、またそれが全体的な見取り図から配置を受けるものであるどうかを一切括弧入れすること、複数の行為連関は、複雑に絡み合うこと、しかも行為連関は浸透するのであって、因果関係とも、論理的前提関係とも異なることである。人間科学は、確実に新たな地盤へと向かって胎動し始めていることが、実感できる。(河本英夫/週刊読書人 1999)
内容説明
環境生態学、生態心理学、発達心理学、建築計画学、文化人類学、家族社会学、理論社会学に視座する気鋭の研究者たちが、現代の人間経験に切実に含まれる問題群の具体から、他者、行為、物、環境などの諸言説を根底的に問い直し、来るべき人間科学の構築をめざして、執筆と横断的な討論を重ねた共同論作。
目次
自然のなかの人間
心理学の生態学的根拠―ココロの起源としての知覚‐行為循環
人工的環境への適応―高齢者居住施設にみる人間・環境システムの形成過程
「もの」をめぐる文化的行為―意味の器としてのやきもの
「文化」の再想像―「全体としての文化」から「メディアに媒介された文化」へ
私の家族・他者の家族・家族というもの
介護における行為の協調関係について―食事介助場面の検討
他者と社会システム
討論