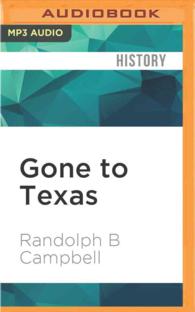出版社内容情報
東洋と西洋の「文化の起源」に巨大な影を落とす「古イランの宗教・文芸」の解明に先駆的業績を残したウプサラ学派の巨匠ヴィカンデルの主要論文集成。
◇1938年、ウプサラ大学(スウェーデン)に提出された博士論文『アーリヤの男性結社』は、オットー・ヘフラーの大著『ゲルマンの秘密結社』(1934年)を拡張し、インド=ヨーロッパ語族の文化の基底にある男性戦士結社の存在を召命するものだったのだろうか。この時代、ヨーロッパを野蛮と腐敗の暗黒に導いたナチズムの組織の範型もまた男性戦士結社であった。◇男性結社生成の秘密は、新石器社会から歴史社会までを通底する文化生成の根源にかかわる制度の課題を提起している。◇本書は、古イラン学の基本文献であるとともに、1930年代思想の原像を考える上でも欠かすことのできない著作であり、現代になお問われるべき思想的課題を示唆している。
【主な目次】第1部 アーリヤの男性結社―インド・イラン言語宗教史研究[序論/第1章 Merakとziyanak/第2章 maryaとmairyo/第3章 アーリヤ語彙における儀礼上の 対立/第4章 男性結社の神話/第5章 カーヴェの旗とパルティア建国/結語] 第2部 論文諸篇[ペルシアおよびインドの叙事詩におけるインド・イラン共通基盤について/ミスラスの秘儀研究/ウラノスの後裔たちの歴史/ゲルマンとインド・イランの終末観/クルド人および『アヴェスタ』における祭り] 解説:ヴィカンデルと同時代の精神たち(前田耕作)/あとがき(桧枝陽一郎)
オスカル・スティグ・ヴィカンデルは、スウェーデンの生んだもっとも独創的なインド・イラン学者。1908年、ウプサラの西方の町ノルテルジュに生まれる。1925年、ウプサラ大学に進み、セム系言語学者としてスタートしのちに高名なイラン学者となったエンリコ・サムエリ・ニーベリ(1889~1974)の指導を受ける。1930、31~32年にはパリ留学。帰国後はニーベリのゼミナールに参加、1937年、ニーベリの主著『イランの古代宗教』が刊行されたが、これにはヴィカンデルの協力が大きかったという。38年、ヴィカンデルは本書の中心をなす博士論文を発表、39年に出版された。のちに印欧比較神話学に大転換をもたらすこととなったデュメジルは、31年10月から33年 7月までウプサラ大学にフランス語教師として奉職、10歳年下のヴィカンデルの博士論文に大きな示唆を受けている。著作として『ワユ―インド・イラン宗教史にかかわるテキストと研究』(1941)、『小アジアとイランの火の祭官』(1946)、『ミスラスの秘儀をめぐる研究』(第1分冊、1950)などがあるが、単行本未収録の重要な論文も多く、本書では主立った論文のいくつかを第2部としてまとめた。1983年、死去。
「イラン学における注目すべき著作が出版された。…本書はデュメジルの『印欧語族の三区分イデオロギー』にも影響を与えた重要な著作であり、その内容は多岐にわたり、しかも高度な言語学的分析をいたるところで駆使した学術論文である。…ヴィカンデルによれば、ゾロアスター教の二元論はササン朝以降の神学文献により確立されたものであり、しばしばゾロアスターの宗教改革に結びつけられるアフラとダエーワの対立も、古代アーリヤ人の儀礼上の対立を十分に説明するものではないのである。この事実を明らかにしたのが、本書の題名とにもなった「男性結社」の存在と、それに結びつく宗教儀礼である。」(岡田明憲/週刊読書人 1997)
内容説明
1938年、スウェーデンのウプサラ大学に提出された博士論文『アーリヤの男性結社』は、O・ヘフラーの大著『ゲルマンの秘密結社』(1934年)を拡張し、インド・ヨーロッパ語族の文化の基底に男性戦士結社の存在を証明するものだったのだろうか。この時代、ヨーロッパを「野蛮」と「腐敗」の暗黒に導いたナチズム組織の範型もまた男性戦士結社だった。男性結社生成の秘密は、新石器社会から歴史社会までを通底して文化生成の根源にかかわる制度の課題を提起している。その意味で本書は、古イラン学研究の基本文献であると共に、30年代思想の原像を考える上でも欠かすことのできない著作であり、現代になお問われるべき思想的課題を示唆している。
目次
第1部 アーリヤの男性結社―インド・イラン言語宗教史研究
第2部 論文諸編(ペルシアおよびインドの叙事詩におけるインド・イラン共通基盤について;ミスラスの秘儀研究;ウラノスの後裔たちの歴史;ゲルマンとインド・イランの終末観;クルド人および『アヴェスタ』における祭り)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
DELEUZE
thuzsta