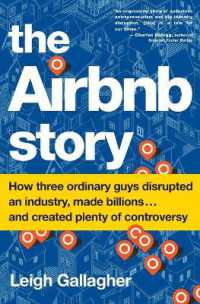内容説明
言葉を「石」とする詩の建築によって20世紀はじめの時代の亀裂から垂直に立ち上がる詩の世界文明へ向かった孤独者の碑。ソ連時代の“流刑の詩人”として知られたマンデリシュタームの詩集は究極的に言葉そのものを始まりとする。それがこの時代には最も反社会的行為とされるのだろうか。時代や空間を超えて語る相手を見出すのは詩の言葉だけである―真の言葉が向かう対話の相手について語ったエッセイ「対話者について」を付録。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
松本直哉
24
繰り返されるイメージはロシアやローマの建築物やパリのノートルダムであり、石を積み重ねて造られた堅牢な伽藍に人間の技の極致を見いだし、自らの詩もまた、確かな手ざわりの〈石〉のような明確な言葉による構築を希求しているように見え、それは同時に、曖昧朦朧のイメージを弄んできた象徴主義との訣別をも意味する。詩論「対話者について」では、詩人バリモントの、対話を拒否する傲慢な個人主義を厳しく批判しつつ、瓶に入れて海に流した手紙のように、いつの日か誰かに読まれることによって命を得る詩を書くことへの決意が述べられる。2024/07/28
S.Mori
11
硬質な言葉で書かれた美しい詩集です。詩を書く自分の核を「石」と表現しているところが、ソ連の文学者らしいです。個人の内面を表現することがタブー視されたソ連だったら、それぐらいの気迫がなければ、活動を続けられなかったでしょう。最期は収容所で命を落としたそうで、痛ましいです。エッセイの中で自分の作品を、砂の中に埋もれた瓶の中に入った手紙にたとえていたのが印象に残ります。ソ連時代は弾圧されたとしても、彼の作品は時を超えて、心を込めて書いた手紙のように、読む人一人一人の心の中に届いたと信じたいです。2019/11/29
manabu
2
詩人の言葉は石。投げ落とされた石で建築されたメッセージは、時空を超えた未知の名宛人に語りかける。 む、これは龍安寺の石の庭?
fumya
1
稀代のアクメイスト、詩人オシップ・マンデリシュターム。ぼくはマンデリシュタームから「美」を学んだ。
mimosa
1
私を詩の森に誘いこんで迷わせた本
-
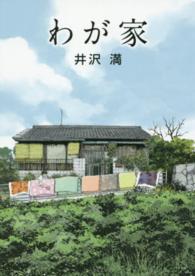
- 和書
- わが家 竹書房文庫