目次
1 古代―里(吉野川流域における農耕文化の成立と展開―畑作文化の形成)
2 中世‐近世―山の暮らし(山村の生業と山口祭―資源維持慣行としての「祈り」;近世後期の鮎喰川流域の「所請」制度について;幕末期の阿波国美馬郡半田口山と三好郡加茂組六ヶ村・租谷山落合名との山論について)
3 近世‐現代―海に生きる(塩田面積や塩生産高等からみた徳島県の塩業―塩田の発祥から廃止まで;明治前期の徳島船場肥料問屋と北前船―「日記」「書翰」にみる山西家徳島支店の肥料取引;漁村における共同と連帯―東・西由岐浦史料にみる)
4 近代―里と街(一九三〇年代における農家副業の展開と農村女性の組織化―那賀郡の藁工品生産と「愛農婦人会」を中心に;人形浄瑠璃芝居一座の経営―上村源之丞座の近代史へのアプローチ)
-

- 電子書籍
- 機動戦士ガンダムUC RE:0096 …
-
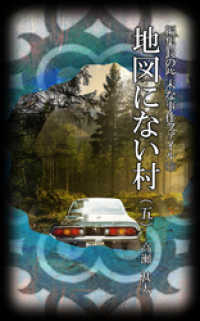
- 電子書籍
- 編集長の些末な事件ファイル158 地図…





