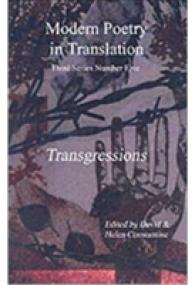- ホーム
- > 和書
- > 児童
- > 学習
- > 文明・文化・歴史・宗教
目次
初級編(しりとりの魅力;しりをとらないしりとり;しゃれとだじゃれ;ごろあわせ;早口言葉)
中級編(「かけことば」であそぼう!;清音・だく音であそぶ!?;アナグラムって、何?;ぎなた読みの由来;畳語であそぼう!;オノマトペであそぼう!)
上級編(山号寺号って、何?;無理問答しよう!;回文とは?)
著者等紹介
倉島節尚[クラシマトキヒサ]
1935年長野県生まれ。1959年東京大学文学部国語国文学科を卒業、三省堂に入社。以後、30年間国語辞典の編集に携わる。『大辞林』(初版)の編集長。1990年から大正大学文学部教授。2008年名誉教授
稲葉茂勝[イナバシゲカツ]
1953年東京都生まれ。大阪外国語大学、東京外国語大学卒業。国際理解教育学会会員。子ども向けの書籍のプロデューサーとして多数の作品を発表。国際理解関係を中心に著書・翻訳書の数は80冊以上にのぼる
ウノ・カマキリ[ウノカマキリ]
1946年愛知県生まれ。日本テレビジョンのアニメーターを経て、イラストレーターとして独立。「平凡パンチ」などさまざまな媒体で、風刺漫画、ユーモア漫画を中心にひとコマ漫画家として活動。1991年および2011年に日本漫画家協会賞・大賞受賞。2016年現在日本漫画家協会常務理事、「私の八月十五日の会」評議員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
遠い日
11
おもしろい。「日本語そのものが、だじゃれのかたまり」という考えかたが実感できる。同音異義語の多さが、脳を鍛えるのだと感じる。しりとりでも、あたまとりになったとたんに、高級なことば遊びに変身。初級編で紹介されているけれど、なかなか難しい。ぎなた読み、畳語となると、さらに頭の回転の早さを要求される。上級編の「山号寺号」「無理問答」ともなれば、もはやセンスもなければ、ただ考えるだけではおもしろくない。これは、ことばに対する見方が変わる本です。2016/08/06
勝部守
9
知的な言葉あそびの世界。既に廃れてしまっているものも。小学校や中学校の国語の時間にこういうのを教えてもらえば、楽しく勉強出来たであろうに。2016/08/11
絵本専門士 おはなし会 芽ぶっく
8
初級編・中級編・上級編と、平安時代から現代までのことば遊びについて書かれています。気にしていなくても結構使ってます。特にダジャレ(笑)2025/04/01
みよちゃん
5
知らない遊び言葉もあり、面白かった。2016/08/14
るい
3
平安時代から現代までの言葉遊びが書かれている。しりとりやだじゃれなど、そんな昔からあったのかということに驚かされた。折句や沓冠には、ほ〜っとため息が出るような感動があったし、区切るところで意味が変わる文を読むのを「ぎなた読み」と言うことも初めて知った。学びがいっぱいの1冊だった。2018/12/28
-

- 電子書籍
- 武田修羅伝(小学館文庫) 小学館文庫