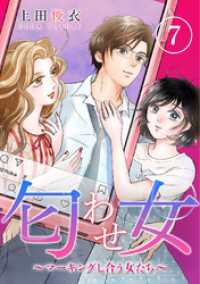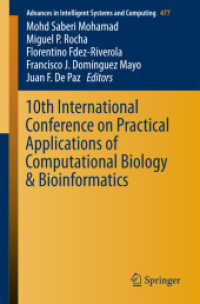内容説明
手塚治虫『ブッダ』からナーガールジュナ「中観」まで、知的で愉しい仏教論。
目次
第1部 仏教をめぐる、やや通俗的な入り口(仏教とは;宗教を描く;輪廻の解釈学とオカルト批判;宗教家の力;ブッダと日本仏教)
第2部 宗教と「この私」(仏教学と体験性;神秘体験と救済;実存を問う病;愛と渇愛;現代人の四苦)
第3部 仏教と社会(善悪の彼岸)
著者等紹介
宮崎哲弥[ミヤザキテツヤ]
1962年、福岡県生まれ。評論家。慶應義塾大学文学部社会学科卒業。政治哲学、仏教論、サブカルチャー分析を主軸とした評論活動を行う
呉智英[クレトモフサ]
1946年、愛知県生まれ。早稲田大学法学部卒業。評論家。マンガ評論、知識人論等の分野で執筆活動を展開。日本マンガ学会会長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さきん
24
本来の仏教とは何か、あらゆる宗派に属さないながらも仏教徒を自認する宮崎氏と宗教関係の評論に造詣が深いが仏教徒ではない呉氏との対談。多少仏教関係の書物を呼んでいたから3割ちょっとの用語は理解できたが、残りの書名や用語は知らないものばかりで大変勉強になった。自分も仏教徒ではないが、仏教の哲学や考え方には惹かれるものがある。近代哲学がやっと論じた内容をすでに仏教内で論争されていたりする。日本に渡ってきた仏教とその後の激しい変容を経た仏教は、もはやブッタの思想とはいえないことを改めて感じる。2017/01/05
うつしみ
17
呉氏も宮崎氏も、仏教は知的技術であるという捉え方をされている。私も同感だ。仏教の教えは全て悟りの為の方便で、川を渡る筏の如く、要がなくなったら捨て去るべきものだ。唯我独尊という前提から出発し、十二支縁起全てが虚構、前提に過ぎない事を理解し無我を悟った瞬間に全て消えるのである。だからと言って仏教は別に無敵の人を作りたい訳じゃない。「知的な準備なしに言語を超えた世界を覗くのはとても危険」で、これが分かってない曲学阿世はオウムと変わらない。昨今の社会の独我論的風潮は正に無明そのもので、仏教的にも誤りだとわかる。2025/02/09
月をみるもの
14
テレビで時々見る評論家のおっさん、、としか認識してなかった宮崎さんが、ガチの仏教徒だと初めてしった。儒教徒(?)たる呉さんとの対談ということでかなり読みやすい。Wikipedia 見たら経歴に「(なんかいも大学に入りなおしたあとで)ニューラルネットワークのビジネス応用を主業務とする会社を設立。評論家となる。 」とあって、脈絡のなさに笑った。。この本自体が惹起する知的興奮度の高さもさることながら、紹介されてるマンガとか本とかが、いちいちどれも面白そうなんですわ。。2019/05/02
白義
13
呉の「つぎはぎ仏教入門」をベースに仏教の原点と現代における乖離、そしてそこから個の実存、リベラリズム対共同体主義、仏教の脱社会性と多岐に渡る話題を縦横無尽に語り合った刺激に満ちた対談集。とりわけ仏教徒であることに力点を置きながら普段の評論活動では多く仏教を語ることのない宮崎哲弥の、本領発揮とも言えるディープな仏教話は見もの。単に博識であるというだけでなく、例えば子どもが自殺してしまった親に仏教徒という立場からどういう言葉をかけるかという実践的な話題まで正直に語られている。祝福王など宗教漫画ガイドも興味深い2017/11/03
モリータ
12
呉智英・宮崎哲弥の対談による啓蒙的な仏教論。入口は宗教マンガ談なのでどうかと思ったが、仏教の体験性、社会的に規定された実存苦の問題など、気になるポイントが宮崎哲弥の豊富な仏教・仏教学的知識と呉智英の中国思想との対比に裏打ちされつつ論じられていて面白く読めた。宮崎×佐々木閑の『ごまかさない仏教』も勉強になったし、宮崎×各宗派の教理問答本も期待できそう。個人的には黒崎宏の一連のヴィトゲンシュタインと龍樹・空思想の比較本も非常に気になる。2018/02/26