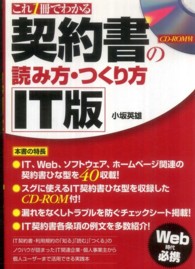内容説明
世界社会の現在と生存権の論理。“個人の自立”の徹底によって近代主義を超える可能性。人称論を手がかりに、現代の世界社会像を構築する清新な社会科学論。
目次
第1部 三人称と社会認識の論理(社会科学の規範的基礎をめぐって―吉野源三郎『君たちはどう生きるか』を読む;「夕鶴」の射程―木下順二への社会科学の応答;三人称としての社会科学―(コミュニケーション的生産力)に立脚した言語へ
三人称の超近代主義的可能性)
第2部 “市民の自立”から“万人の自律”へ(“自立した個人”の概念について;“自立した労働者”の概念について;市民概念を超えて)
第3部 アメリカ・日本・東アジアと生存権の論理(アメリカ史像の転換と日本版「啓蒙の弁証法」;アメリカ個人主義と社会的シティズンシップの分裂;戦後日本の公共性の変遷;戦後民主主義から社会文化まで;帝国臣民から傀儡国民へ;戦後責任と東アジア共同体;生存権の歴史的位相と論理)
著者等紹介
竹内真澄[タケウチマスミ]
1954年高知県生まれ。桃山学院大学社会学部教授。京都自由大学講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
he
0
森有正の引用、「自分から出発することはできない。すでにある社会から出発するのである」は至言。戦後の日本社会は、急激な経済成長によって精神的価値から切り離されてしまった。西洋の市民社会と比較して、構造としては近いものを持ちながら人々の市民化が為されていないのは、目に見えない価値に対する懐疑的態度が一因しているのではないか、とのこと。スキルの上辺だけを複製し続ける、いわゆるマニュアル社会を見ていると頷けるところもある。必要以上のマニュアルを求める社会とはつまり、自我の許容に至らない社会の一側面である。2014/06/23