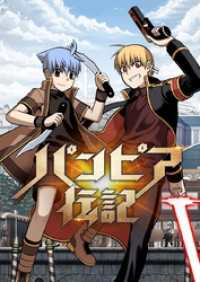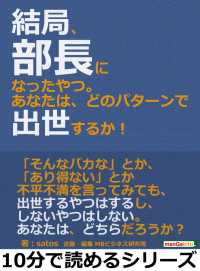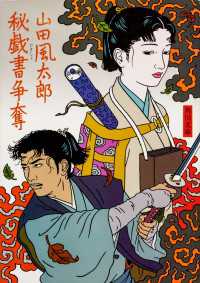目次
プロローグ 世界は科学であふれている
第1章 科学は「それは何か?」と問えない(科学を身近に感じる;スープはなぜ腐るのか ほか)
第2章 「分類の迷宮」という罠(イヌはなぜ犬なのか;ヒトはなぜ人なのか ほか)
第3章 どうすれば「正しい」といえるのか―果てしなき検証―(権威ある研究機関で行われている心雲現象や超能力の検証;科学的に「原発」の「絶対安全」はありえない ほか)
第4章 科学の「真偽」、人間の「善意」(科学は「真偽」しか決められない;科学の価値とは何か ほか)
エピローグ 科学の美と快楽
著者等紹介
長谷川英祐[ハセガワエイスケ]
進化生物学者。北海道大学大学院農学研究院教授。動物生態学研究室所属。1961年、東京都生まれ。子どもの頃から昆虫学者を夢見る。大学時代から社会性昆虫を研究。卒業後は民間企業に5年間勤務。その後、東京都立大学大学院で生態学を学ぶ。主な研究分野は、社会性の進化や、集団を作る動物の行動など。特に、働かないハタラキアリの研究は大きく注目を集めている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件