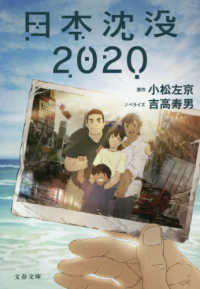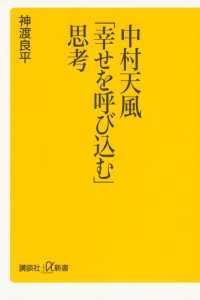内容説明
ワンダ・ガアグ『グリムのむかしばなし』の刊行の際に翻訳者、松岡享子の講演を一冊にまとめまたもの。
著者等紹介
松岡享子[マツオカキョウコ]
1935年神戸市生まれ。神戸女学院大学英文科、慶応義塾大学図書館学科を卒業後、渡米。ウエスタン・ミシガン大学大学院で児童図書館学を学んだ後、ボルチモア市公共図書館に勤務。帰国後、大阪市立中央図書館勤務を経て、東京の自宅にて家庭文庫を開き、児童文学の翻訳、創作、研究を続ける。1974年、石井桃子氏らと東京子ども図書館を設立し、現在同館名誉理事長。童話『くしゃみくしゃみ天のめぐみ』でサンケイ児童出版文化賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヒラP@ehon.gohon
21
ワンダ・ガアグの「グリムのむかしばなし」の2巻を読んで、今まで読んだグリム童話と一味違う原因が分かる本でした。 原文の比較ではないので、邦訳によって違いも出てくるのでしょうが、ワンダ・ガアグのアレンジは、子どもの心を引き付けることに苦心したことがよくわかりました。 グリムの残酷さの生々しさを、安心できる表現に置き換えたこと、ユーモアを大事にしたこと、簡潔に伝えることで受け容れやすくしたこと等、同じ物語でも伝え方で印象が変わるというマジックが、解説されていました。2024/03/29
がんぞ
4
グリム兄弟は、はじめ大人のために民話集を発表したが版を重ねるにつれ子供向けの話に進化していった。ガアグは十五歳のとき父をなくし、病弱の母親を助けて家事をこなし投稿で賞金を稼いで家計を助け時間のあるときには高校に通った。「自己を表現するだけでなく、他のアーティストの内的葛藤の代弁者となる」特別な才能。『百万匹のネコ』のような普遍的寓話/むかしばなしはニューズの無いときに語るものだったが、21世紀はニューズがありすぎて古典を語る余裕がない。せめて子供には童話を語り、その寓意性を見抜く生活常識を身に着けてほしい2019/11/15
まーたろ
3
最近ガアグの『しらゆきひめと七人の小人たち』を読んだので。我が家では『100まんびきのねこ』がイマイチ受けず残念に思っていたが、『しらゆきひめと…』は気に入った様子だった。それで、ガアグの昔話に興味を持ったのだが、ガアグ自身がこれほどの熱意を持ってグリムに取り組んでいたとは知らなかった。「文章と絵を同じ人がかいているからこそ達成できる面白さ」という部分を読んで、先日子どもが食い付いていたのもまさにその要素有ってこそ、と気付いた。次は「グリムのむかしばなし」を読んでみよう。2019/08/08
ちかこ
0
ガアグのグリムを原書で読める英語力が自分にあったらいいのにと思う。2020/05/03