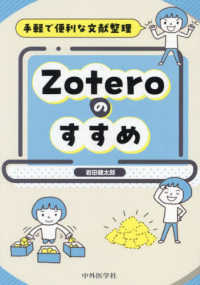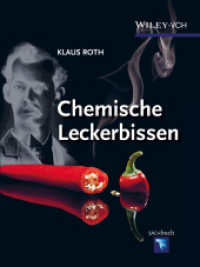出版社内容情報
人口の7000人の町の本屋、「ウィー東城店」。山間の田舎の書店に望まれることの多くは、こわれた電気機器の相談や、年賀状の宛名書きなど、高齢者たちの生活の相談にのることでした。そんな店にある日、「学校に行けなくなった子どもをなんとかしてほしい」と相談がもちこまれ、店の運命は大きく変わっていきます。
地域の小売店の可能性と、そこで成長する若者たちの姿を描く感動作。
装画、挿絵は『急がなくてもよいことを』で注目を浴びる漫画家、ひうち棚さんです。
内容説明
町の人たちがなんでも相談にくる山間の本屋、「ウィー東城店」。地域の小売店の可能性と、そこで成長する若者たちの姿を描く。
目次
1章(八戸ノ里の大学生;とでやの息子;本屋の父 ほか)
2章(手品をする本屋;複合化の時代;本屋とコンビニ ほか)
3章(前田夕佳さんの話;妹尾秀樹さんの話;大谷晃太さんの話)
著者等紹介
佐藤友則[サトウトモノリ]
1976年広島県生まれ。大阪商業大学中退。愛知の書店チェーン「いまじん」にて修行後、2001年よりウィー東城店に勤務。現在、株式会社総商さとう代表取締役
島田潤一郎[シマダジュンイチロウ]
1976年高知県生まれ。日本大学商学部卒業。2009年に株式会社夏葉社を創業(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ケンイチミズバ
123
この人はとてもいい人。この人のような大人が世の中の救いだと思う。社会にある沢山の基準、異性と結婚した方がいい、その生活は長く続いた方がいい、結婚したからには子供はいた方がいい、子供は学校へ休まずちゃんと通ったほうがいい、それは大人が若者に押し付ける締め付けかもという考えは優しいね。私も賛成。不登校の子たちを雇用することになっての彼の気づきです。書籍はお客さんの顔が見える商品です。ミステリー好き?悩みを抱えてる?資格取得を目指してるんだ、頑張れ!園芸が趣味なの?事務的な接客より私も話しかけられたい方です。2023/04/12
けんとまん1007
91
山間の大きくはない町での本屋の意味を問われている。しかし、それだけはない。俗にいう田舎(大都市に対する地方、市町村の中心部に対する地域など)での、そこに住む人たちへ向ける視線、つまり哲学を問われている。大事なのは、そこに住む、いろいろな年代に目を向けること。さらに、今の時代の便利さの間にいる人たちへの視線。形は違うが、オードリー・タンさんの視点に通じるものがある。「最も使うのが困難な人に合わせ、明朗な設計をすればいい」・・この哲学と視線に通じる。忘れてはいけないものがある。2023/07/26
ナミのママ
87
広島県の山間にある本屋「ウィー東城店」。書店で手にした時にあまりに装丁が良くて見入ってしまったのだが、それがこの店舗のイラストだった。ISBNバーコードが帯についているので綺麗な一枚絵になっている。夏葉社の発行と知り納得した。手にした時の大きさ、紙の質、文字間、匂いまで「紙の本」の良さがギュッと詰まっている。傾いた実家の店を任されて現在に至るまでのストーリー。その土地を生かし、そこに住む人を理解し、本屋+アルファで経営を立て直していく、その知恵がなんとも楽しい。散りばめられた言葉の中に哲学がある。2023/03/01
tamami
77
様々な経緯から曾祖父が創業した山間の小さな本屋、通称「とでや」を継いだ著者は、これも紆余曲折を経て、その支店「ウィー東城店」で働く事になる。本書は、その間の修業遍歴時代と「ウィー…」での店長時代を記した、著者の半生記。本書の至る所に出てくるのは、本というモノを介して人と繋がり、店という場で人を育ててきた著者と仲間たちの姿である。不登校だった彼、社会に馴染めなかった彼女たちが、著者の言葉と、本や店を巡る魔法仕掛けの仕組み(!)で、独り立ちしていく。本書には、そんな本当に奇跡なような物語が幾つも紡がれている。2023/04/10
ムーミン
74
これからの日本社会が目指すべき方向が見えた気がしました。2025/03/01
-

- 電子書籍
- 私のことは諦めてください!~策士な皇太…