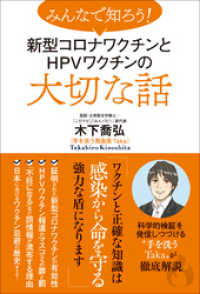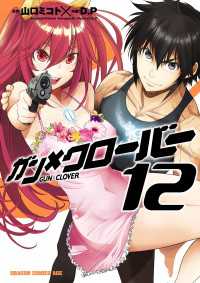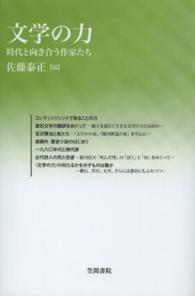- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 文化・民俗
- > 文化・民俗事情(海外)
内容説明
人はその食べるところのもの。東京外国語大学の世界各地・各ジャンルの研究者たちが腕によりをかけて贈る30の「食」文化エッセイ。
目次
東アジア
東南アジア
南アジア 西アジア
東ヨーロッパ 中央ヨーロッパ
西ヨーロッパ 南ヨーロッパ
アメリカ オセアニア アフリカ
著者等紹介
沼野恭子[ヌマノキョウコ]
東京外国語大学教授。専門はロシア文学、食文化、比較文学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
佳音
93
この本は素晴らしい。東京外国語大学の海外各国を専門とする先生方が「料理」をテーマに専門家らしい視点を保ちながら、中学生(おそらく小学校高学年も)にもわかりやすく解説している。料理から見える各国の文化は国際理解につながりやすいだろう。なによりコラム的なエッセイが必見。紛争などネガティブな国際理解より料理でしょ?(^_^)2016/09/22
syaori
70
東京外語大の教員が専門地域の食について、文化や歴史、思い出を絡めて紹介する本。ベンガルやセルビアもカバーできるのはさすが。一読して感じたのが、古来からの人や文物の往来や近代の植民地支配により、一口にどこの国の料理といっても多様な国や地域の影響があるということ。台湾料理に添えられる「タクアン」は日本統治時代に受容され、エジプトのコシャリはインドのキチュリがメッカへの巡礼者によってもたらされ変化したものというように。世界はそのように混り合いながら独自の文化を作ってきたことを、食を通して見せてくれる一冊でした。2023/01/24
seacalf
41
各国の料理を個性豊かな外語大の先生達が自由に紹介。ひとつひとつが程よい長さなのでさくさくと読みやすい。フィリピンのアドボ、ベンガル料理キチュリ、アラブのコシャリ、リトアニアのシャルティバルシチュイにジャガレーレイ、外語大ポーランド専攻の学生が「必修」で作るチーズケーキのセルニク、セネガルのチェブジェン、今回も食べてみたい料理が満載だ。世界に広がる日本料理の紹介コラムや、ケチャップやフルコースの本元は実はあの国等々意外な雑学もちらほら。食事方法そのものにも各国の文化の違いが現れて、本当に楽しい一冊だった。2018/09/20
野のこ
32
いろんな専門分野の外国語大学の教員のかたが世界の食について語り合ってできた本。その国ごとに著者が違い、型にはまらない紹介。各国の文化や歴史から繋がる伝統料理のエピソードが分かって面白かったです。「初恋の味」であるカルピスはモンゴルの馬乳酒のピントから生まれた。ベトナムでは「これからフォーを食べに行く」と言うと「浮気相手のところに行くのか」とからかわれたりする。とか豆知識たっぷり。「もう食べた?」と言うあいさつが東南アジアに多いのはおもてなしの素敵な心。ココナッツミルクで炊いたごはんが気になりました。2017/10/05
くさてる
29
東京外国語大学の研究者による世界各地の名物料理の紹介とレシピ。そしてそれにまつわるうんちくなど。異文化紹介としても面白かったし、なんとなくイメージだけでとらえていた国の料理の実態が知れた。ベンガル料理やリトアニア料理など、まったくイメージがわかなかった料理が、それでもおいしそうだったりたのしいものだったりするのも興味深い。写真もカラーで読みやすい一冊です。2016/08/03