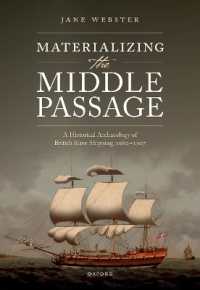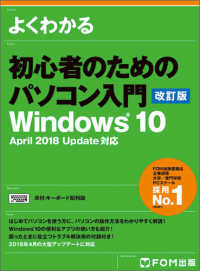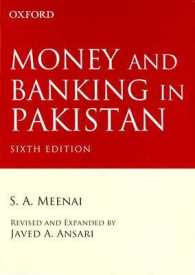- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 文化・民俗
- > 文化・民俗事情(日本)
目次
1 秋田民謡―明治・大正時代の姿(記録された秋田音頭や秋田の盆唄;秋田オハコ節と大葉子節;佐藤貞子や関屋敏子の活躍;後藤桃水に出会う鳥井森鈴の飛躍)
2 秋田民謡―昭和初期から戦前まで(小玉暁村や田口織之助と仙北民謡;UK放送がもたらしたもの;東北民謡試聴会;郷土民謡公演)
3 郷土芸能による地域の再生(全県芸能競演会がもたらしたもの;優れた民謡人が育てた「民謡の国・秋田」;「生保内民謡正調の会」から「田沢湖町郷土芸能振興会」へ)
著者等紹介
麻生正秋[アソウマサアキ]
昭和24年(1949)秋田市に生まれる。秋田大学教育学部卒、大学では地理学を専攻。学生時代より社会地理学、民俗地理学を基礎にしながら「民謡の伝播と定着に関する地域研究」を続ける。秋田県内の高校勤務の他、昭和54年からの秋田県教育庁文化課勤務をかわきりに、県教育委員会では、主に文化行政、文化財行政、生涯学習行政等に携わる。平成22年3月、秋田県立近代美術館副館長を最後に退職。あきた郷土芸能推進協議会事務局長、秋田県歴史研究者・研究団体協議会理事等を務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
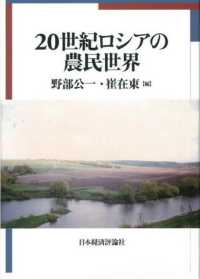
- 和書
- 20世紀ロシアの農民世界