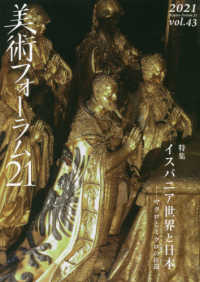内容説明
地方ローカル線の未来を問う答えは敷設の歴史の中にこそ秘められている。未だ不通区間を抱える只見線のドラマチックな敷設の歴史を追うノンフィクション。
目次
七世紀~江戸時代―魚沼・奥会津・会津の歴史と只見線
一八六八年(明治元年)~一八八六年(明治十九年)―一八八七年(明治二十年)~一九四五年(昭和二十年)八月十五日―戦争の時代と只見線一部開通
一九四五年(昭和二十年)八月十六日~一九六一年(昭和三十六年)―戦後復興と電源開発と只見線
一九六二年(昭和三十七年)~一九七一年(昭和四十六年)―只見線全通
著者等紹介
一城楓汰[イチジョウフウタ]
全国各地を巡り鉄道風景写真を撮る中で、それぞれの路線の敷設に関する歴史に強く惹かれるようになる。さらに最近では、地方が抱える観光振興問題や地方ローカル線存続問題などへとフィールドを広げ、精力的に活動を続けている。東京都出身(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
重石稔
1
かなり古い時代のところから書かれています。読んでて眠くなりますが必須な部分であると思いました。明治に入り文明開化の大義名分の中から日本が戦争にかかわり鉱山資源の利用のためであったり水力発電所の建設のためであったり。旧国鉄という大組織の使命と問題点を抱えながら全通に至った沿線住民の努力は計り知れないものがあると感じつつ、マイカー時代の到来で只見線のみならず全国のローカル線が赤字運行の現実。各地の赤字ローカル線が全くなかったころに何故、そこに鉄道を敷くようになったのか興味が他の路線にも興味が行くような本です。2015/09/23
佐倉 海人
0
七世紀から始まる街道の歴史から只見線全線開通までの歴史までが綴られています。街道の歴史から鉄道開通までの歴史を辿れ。更に計画路線の話まであり「えっこんな計画が?」という驚きもありました。 Google earthの航空写真を参照しながら読了。先に読んだ「只見線物語」とは一寸違った視点で開通までの歴史を見ることができました。2022/09/23