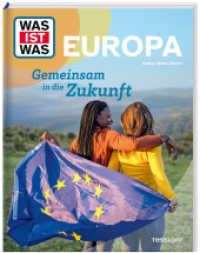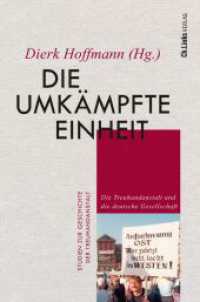内容説明
帝政ロシアの植民地であった中央アジアは、1917年のロシア革命による社会主義化と、1991年のソ連解体にともなう独立国家の誕生という、世界でも例をみない二つの大規模な変革を経験した。本書は、ソ連の誕生から崩壊に至る70年間の歴史を、ウズベキスタンの人びとに焦点をあて、人びとの記憶の観点から考察したものである。彼らが語る「記憶の中のソ連」とはどのような世界なのだろうか。直接インタビューにより、人びとの生の声を掘り起こした労作。
目次
序章
第1章 近現代史の概観
第2章 スターリン時代におけるソビエト化と一般国民の生活
第3章 第二次世界大戦
第4章 スターリンの死と時代の終わり
第5章 停滞の時代か、黄金時代か
第6章 ソ連時代のコミュニティ観―マハッラの事例から
第7章 宗教と社会
第8章 ソビエト国民の諸相:民族と言語
第9章 独立後に現れたノスタルジー
著者等紹介
ダダバエフ,ティムール[ダダバエフ,ティムール][Dadabaev,Timur]
1975年ウズベキスタン、タシケント生まれ。筑波大学人文社会科学研究科准教授、東京大学人文社会研究科付属次世代人文学開発センター客員准教授。コロンビア大学ハリマン・インスティチュート客員研究員(日本学術振興会優秀若手研究者海外派遣事業)(2010年)、ケンブリッジ大学(東京財団教員海外派遣プログラム)客員教員(2006‐2007年)、オックスフォード・イスラーム研究センター(OCIS)Al‐Bukhariフェロー(2006年)、東京大学東洋文化研究所助教授(2004‐2006年)、国立民族学博物館・日本学術振興会外国人特別研究員(2002‐2004年)、国連大学秋野豊基金フェロー(2004‐2005年)、UNESCO‐小渕恵三基金フェロー(2002‐2003年)を経て現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Toska
おおた
ありさと
T_Galnel