内容説明
障害者の地域生活に根ざした介助という営み、その歴史と現状をつぶさに見つめつつ、「介助で食っていくこと」をめぐる問題群に当事者が正面から向き合った、これぞ必読の書。
目次
第1章 とぼとぼと介助をつづけること、つづけさすこと
第2章 障害者ホームヘルプ制度―その簡単な説明と課題
第3章 障害者介護保障運動史そのラフスケッチ1―七〇年代青い芝の会とその運動の盛衰
第4章 障害者介護保障運動史そのラフスケッチ2―公的介護保障要求運動・自立生活センター・そして現在へ
第5章 障害者運動に対する労働運動の位置と介護保障における「労働」という課題
第6章 障害者自立生活の現在的諸相―介助者・介護者との関わりのあり方から見て
あとがきにかえて―介助者たちは、どう生きていくのか
著者等紹介
渡邉琢[ワタナベタク]
1975年名古屋生まれ。2000年、日本自立生活センター(JCIL・京都)に介助者登録。2004年、JCILに就職。京都市における24時間介護保障の実現に尽力。2006年、仲間とともに「かりん燈~万人の所得保障を目指す介助者の会」を結成。介助者の生活保障を求める活動をはじめる。反貧困ネットワーク京都などにも参加しつつ、様々な立場の運動のつながり、人々のつながりを模索中。現在、自立生活運動の事務局員、介助派遣部門のコーディネーター、ピープルファーストの支援者として、日々葛藤の中にいる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
s-kozy
46
障害者の地域での自立生活、それを支える介助という営み。この営みが仕事として定着したのはつい最近のこと。社会福祉基礎構造改革から支援費制度、障害者自立支援法、障害者総合支援法と法制度が変わっていった結果、ヘルパーを使いながら自立生活を送る障害者が増えた(ただし、当事者の運動が少ない地域ではなかなかそのようにはなっていない)。この流れは70年代から始まる障害者の自立生活運動に端を発する。青い芝の会、府中療育センター闘争、自立生活センターの台頭と本書で語られる障害者介護保障運動史は資料としてもとても価値が高い。2019/07/26
Mao
8
障害者の「自立」とは。 自己決定の権利が保障されることと、社会的に周りの人との関係の中で互いに存在意義を認めあえること、この二つの側面がどちらも大切。 介護が仕事として一般化したのは2000年代に入ってから。これからも皆で考え進化させていくべきものである。2017/02/16
tu-ta
2
約1ヶ月かけて読書メモ書きました。 http://tu-ta.at.webry.info/201604/article_7.html2016/03/29
ひつまぶし
1
介助者の立場から障害者運動について整理し、その中で介助者がどのように位置づけられ、どのような役割を担ってきたのかを整理している。おぼろげにすら知らなかった、知りたいと思っていたことにちょうど答えてくれる一冊だった。自立生活運動というとずいぶん古い話のように思っていた。しかし、考えてみれば24時間介護の実現がたかだか1990年代のことで、そこから介助者について語れるようになったのは本当につい最近ということになる。当事者だけでも支援者だけでもダメなのだということを語り始められたのもまた、つい最近にすぎない。2022/11/17
takao
0
ふむ2025/12/24
-
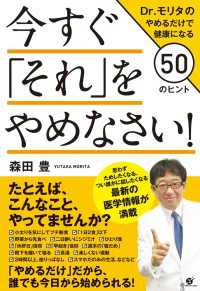
- 電子書籍
- 今すぐ「それ」をやめなさい! Dr.モ…








