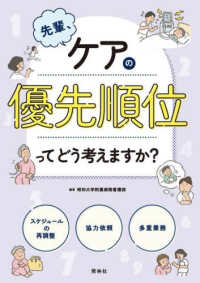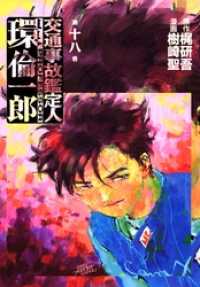目次
第1章 ロシアの女性誌の誕生(女性誌の黎明;社会の変化と雑誌メディアの発展)
第2章 新しいソヴィエトの女性たち(『労働婦人』、『農業婦人』;旧い価値観との闘い ほか)
第3章 非合法のフェミニズム雑誌とソ連の現実(『女性とロシア』、『マリア』;疲弊する女性たちとソ連の現実 ほか)
著者等紹介
高柳聡子[タカヤナギサトコ]
福岡県生まれ。早稲田大学第二文学部卒業。同大学大学院文学研究科ロシア文学専攻博士課程修了。文学博士。専門はロシアの現代文学や女性文学、ジェンダー史。早稲田大学などで非常勤講師としてロシア語、ロシア文学を教える(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ふろず
3
仕事と家庭の両立を国が推奨し、さらに家事育児はアウトソーシング、シングルマザーがモデルとして雑誌に登場。西側フェミニズムは家庭のケア労働からの脱却・経済的自立を目指したのに対してロシアフェミニズムは「家庭に帰る」だから驚き。『共産主婦』と併読したい。2024/11/23
Mana
3
雑誌からソ連の女性事情を解説する。マイナーどころででなかなか興味深いけど、ちょっと文章が難しい。西側のフェミニストに理想化されてた面もあるソ連も、女性の家庭と社会の二重の負担は免れなかった。自立した女性として一時期シングルマザーが推奨されていたのは面白い。2018/12/30
Fumitaka
2
ソ連時代、女性の労働が強調されたことに対し、「仕事と母親の両立は難しい、家庭に帰らせてくれ」という、ある種保守的にも思える主張が出たというのは興味深い。ソ連時代の労働環境の産物とはいえ、女権拡張運動も当地の事情に影響されることの証左ではないだろうか。後目を引いたのは、個人の問題が社会的に解決されるとボリシェヴィキは説いたが、それに対し個人の問題と社会の問題は違うという反応が出たという奴である。バクーニンは言った、人間とは社会の産物であると。だが、個人が必ずしも社会と重複しないのも、それはそれで事実である。2018/12/01
Juonn Izuhara
1
革命後のロシア女性の生活がリアル。西側のフェミニズムと異なる本音も重要。2020/12/22
トム
0
面白かった。革命後ロシアの女性史、フェミニズム史の一端が伺える。1920年代、女性失業者はセックスワーカーになるほかなかった、という記述を読み、じゃあ映画『ベッドとソファー』の結末後ヒロインは…とゾッとした。ソ連初期は家事・育児など女性負担のケア労働のアウトソーシング化と男性と同等の工場労働が推進され戦間期以降は打って変わり男性と同等の労働量が保持されたままケア労働の内部化が推進されたために女性の負担が増大しそこからの「解放」が叫ばれた、という流れは興味深かった。2021/08/14